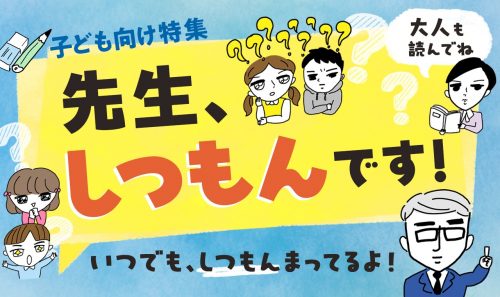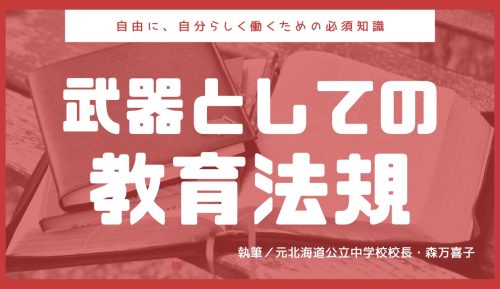小学生が「使える英語」を習得するためのポイントとは?
算数や国語などと並ぶ教科として「外国語科」が採用されました。しかし、どうすれば子供たちの英語力を伸ばしてあげられるのでしょうか。今回は長年公立小学校で子供たちに英語を教え、英語の読み書き能力の獲得方法について研究してきたアレン玉井先生に、使える英語を習得させる指導ポイントを聞いてみました。

目次
言葉は生きた文脈の中からしか育たない
2020年度から、小学校で学ぶ英語が大きく変わりました。
中学年から「外国語活動」が始まり、高学年では外国語が教科化され、学習目的も「英語によるコミュニケーション能力の素地や基礎を養うこと」となり、「使える英語」を身に付けることが重要視されるようになりました。
教科化に伴い学ぶ内容も、「聞く」「話す」だけでなく、「読む」「書く」学習も加わり、中学校の学習の土台を作ることになりました。
また小学校では600~700語程度、中学校で1600~1800語程度、高校では1800~2500程度の単語が導入されることとなり、合計すると4000~5000語、つまり従来の倍の語数となります。
新しい教科書をご覧になった先生方も、そのボリュームと単語量、難しさに驚いたことでしょう。
では今後、小学生では子供たちに対し、新しい言語である英語をどのように学ばせていくとよいでしょうか。
言語を学び始める時には、意味のある文脈の中で新しい言葉と出合っていくことが望ましいでしょう。
言葉は生きた文脈の中からしか育たないからです。
大人が新しい言葉を学ぶときは、論理的、分析的に頭で言葉を整理し理解しようとしますが、子供は違います。言葉全体を丸ごと、生きた文脈の中で体や感覚を使って吸収していきます。
例えば、「イチゴはstrawberry」「犬はdog」と単語だけを覚えさせるのではなく、“Wow! Tasty!It’s a strawberry.(わー! 美味しいね。これはイチゴだよ)”、“That’s a big dog. Her tail is cute!(大きい犬! しっぽがかわいいね)”などと、文脈の中で「イチゴ」「犬」をいう言葉を教えていくとよいでしょう。
意味のある楽しい会話の中で「おいしかったな」「かわいかったな」という気持ちと一緒に新しい言葉を経験させ、「もっと知りたい」という意欲を育てていくことが大切なのです。
英語らしいリズムやイントネーションを文全体で覚えさせる
また、単語だけでなく、会話文全体を英語らしい発音、イントネーション、リズム、アクセントを含めて丸ごと覚えさせたいものです。「banana」という言葉だけを覚えるのではなく、「Do You like bananas?」という質問をイントネーションや抑揚含めて一緒に覚えさせるのです。
そうでないと、単語の言い方は覚えられても英語のリズムや音調というものは身に付きません。
私が初めてネイティブ・スピーカーの先生から英語を学んだのは大学に入学してからでした。その先生はいつも英語の会話を暗唱させるときに、必ず鉛筆で軽く机を叩き拍子を取りながら暗唱させたのです。そして、リズムが合わないと何度もやり直しさせられました。
そうやって文全体のリズム、イントネーション、アクセントを徹底的にたたき込まれたおかげで、英語らしい表現を身に付けることができたのですが、本来はこうした指導はできるだけ学習者の年齢が低いうちに取り組ませるほうがよいと思います。
一見難しそうに見えますが、文を音として全体で捉える覚え方は、年齢が小さければ小さいほど実は適していますし、思春期頃になると、自分が周りからどう見られているか気にし始めるので、英語らしい発音やイントネーションをすることを恥ずかしがる子供も出てくるからです。

「読み・書き」の力をつけるためにはまずは「文字」、特に「小文字」の練習を
日本に生まれた子供たちは大方自然に日本語を聞いて理解し、話せるようになります。しかし「話す」「聞く」というスキルと違い、「読み」「書き」には指導が必要であり、学校でも先生の技量が試されるところでもあるでしょう。
これは英語も同じです。
まず英語を書く上では、音とスペル(綴り)の関係を知っておくことが非常に大切です。
例えば「neck」という単語を聞いて、「首」であると意味を覚えさせることはそれほど難しくありません。しかし「neck」という単語を見て、ネックと発音できるようになる。もしくは「neck」と言われて意味を理解し、音を頭の中で再生しながらスペルが書けるようになるためには、時間がかかります。
そしてこれは子供を英語に触れさせていれば自然に身につくわけではなく、ある程度のルールやリテラシーを指導する必要があります。
まずは、しっかりとアルファベットの形を覚えさせ書けるようにする必要があるでしょう。
私の経験から子供は大文字を覚えるよりも、小文字を覚えることが3倍くらい難しいと思います。形が小さくなるため特徴が少なくなるにもかかわらず、また文字の高さも複雑になるからです。
ですから、26文字のアルファベットの文字の形と音を徹底的に練習することが大事です。特に学習速度が遅い子供には、時間をかけて小文字の練習をしてあげるとよいでしょう。
音と綴りの関係性を覚えると、初見の英単語が読めるようになる
音とスペルの関係性を学ばせるには、フォニックスという学習法が有効です。
英語圏では幼い子供はこのフォニックスを使い英語の読み書きを学んでいきます。中国や韓国でもかなり普及しているのですが、日本の小学校でまだ十分に取り入れられておらず、非常に残念なことだと思っています。
このフォニックスを学んでおくと、英語の勉強がぐんと楽になるからです。
例えば「A・B・C」は「エー・ビー・シー」でなく「ア」「ブゥ」「クゥ」と発音させる。「wh」なら「ウ」と読む、など音とスペルの関係性を学ばせることで、「neck」は「/n//e//k/」「ネエク」と発音するなど、初見の英単語でも比較的簡単に読めるようになります。
漢字も同様ですよね。読めない漢字は、自分で書くことも難しいでしょう。ですから「スペルを見て音を想像し、声に出して読む」という練習はとても大切なのです。
「読み・書き」の力を身に付けると、英語への不安も軽減する
「読み書きを教えると英語が嫌いになる。不安を助長する」と言う先生がいますが、私は逆だと思っています。読めない、書けない状態で単語を教えると、どうしてもローマ字読みに頼るようになってしまい、いつまでたっても自信がつきません。
私は2010年から都内の小学校で英語を教えているのですが、高学年の子供たちに時々、中学校の教科書を見せることがあります。そして「来年の今頃はこんな教科書を使って英語を学びますよ」と伝えると、子供たちは、難しそう」「面倒だな」と思わずに「面白そう」「とにかくちょっと読んでみよう」と言って自分たちで読もうとします。ざっと文全体を見てある程度でも英語として読めるようになると、より英語が楽しくなるし、達成感をもって次の学習に進めるようになるはずなのです。
そういう意味でも、中学校以降の英語の学習に対する苦手意識や不安を和らげるためにも、やはり小学校のうちから読み書きを学ぶことは大切だと実感しています。

小学生にはタブレットよりも鉛筆・紙を使わせたい
デジタル化における英語教育については、いろいろな議論があると思います。
私は英語に親しむ上で、タブレットやスマートフォンのアプリを使うことはよいと思いますが、読み・書きについては、やはり鉛筆と紙を使って学習させるほうがよいと思っています。
初等教育の段階では、文字を指でタブレット上で書くのと、鉛筆を使って紙に書くことは身体性という意味で大きな違いがあると思うのです。
ICTを活用した英語学習を否定するわけではありませんが、特に小学校ではノートに自分で文字を書き、そのノートを見直してみる。指を使って文章を読む。そうした身体性が読み書きの上達には非常に重要だと思っています。
語彙力を増やすと、コミュニケーションが豊かになる
英語の授業数は増えましたが、本当の意味で「使える英語」を身に付けるためには、英語に触れる回数をもっと増やす必要があります。
可能であれば、授業以外でも英語と触れるチャンスをつくっていただきたいものです。子供は「この単語を知っている」「この話を英語で読んでもらったことがある」「聞いたことがある」と感じると、「得意だ」という意識が芽生え、英語が好きになります。好きになれば、「好きこそものの上手なれ」で自分から学び出します。
そもそも新しい言葉を知っている、分かるというだけでもうれしいものです。
例えば、休み時間や家庭で絵辞典などを使い、絵や写真を見ながら楽しく英単語に触れてみるのもよいと思います。
私が監修させていただいた『英語ことば図鑑5000』は、5000語の単語を収録しています。動物や食べ物の他、メイクやスポーツ、身体の動かし方、感情などカテゴリーも豊富なので、必ず興味のある分野や授業で使いやすいカテゴリーを見つけることができると思います。大人でも知らない単語がたくさんあるので先生方にとっても興味深い内容になっていると思います。
語彙力だけでコミュニケーションが成り立つわけではありませんが、単語を多く知っていれば、それだけ豊かなコミュニケーションが可能になります。
「世界市民として生きる」という意識を持つ
英語を覚えなくても生きていけると考える人もいるかもしれません。
しかし、国際化はすでに日本のいたるところで起こっています。
都心だけでなく、人口や産業が少ない地域でも、英語が必要となる場面も増えてくるでしょう。
グローバル化の時代、多様性が求められる時代を生きるすべての人にとって、コミュニケーション手段としての英語力は大切な能力なのです。
ぜひ「世界市民として生きていく」という意識をもち、楽しみながら英語を日々の活動に取り入れていただきたいと思っています。
取材・構成・文/出浦文絵 撮影/横田紋子(小学館)

■アレン玉井光江
青山学院大学文学部英米文学科教授。教育学博士。幼児や児童がどのように英語の読み書き能力を獲得していくのかを長年研究。日本児童英語教育学会会長。『名探偵コナンと楽しく学ぶ小学英語シリーズ』『英語ことば図鑑5000』(いずれも小学館)など著者多数。

■音で学べる!英語ことば図鑑5000 タッチペンつき
監/アレン玉井光江 編/小学館辞典編集部
はじめての英語から本格英語学習まで1冊で5000語の英単語が学べる英語図鑑。豊富な語彙が身につく幅広いジャンルから130のシーンを切り取り、楽しいイラストとともに英単語を紹介しています。
新学習指導要領にも対応し小学校の授業で習う600~700語をすべて収録している他、英語圏で第2言語として英語を学ぶESL(English as a Second Language)に使われる教材やテキストを研究し、ネイティブの子どもたちが日常生活の中で自然に身につける単語をふんだんに取り入れています。ネイティブスピーカーの発音を耳から学べるタッチペン付き。