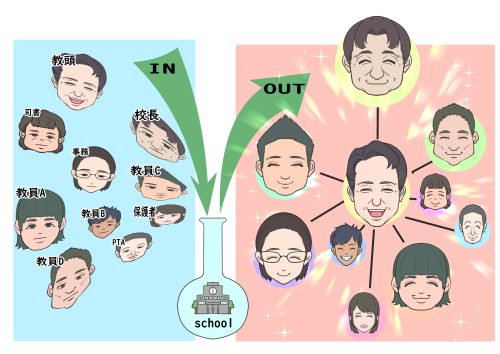素直、従順、受容への回帰【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第28回】

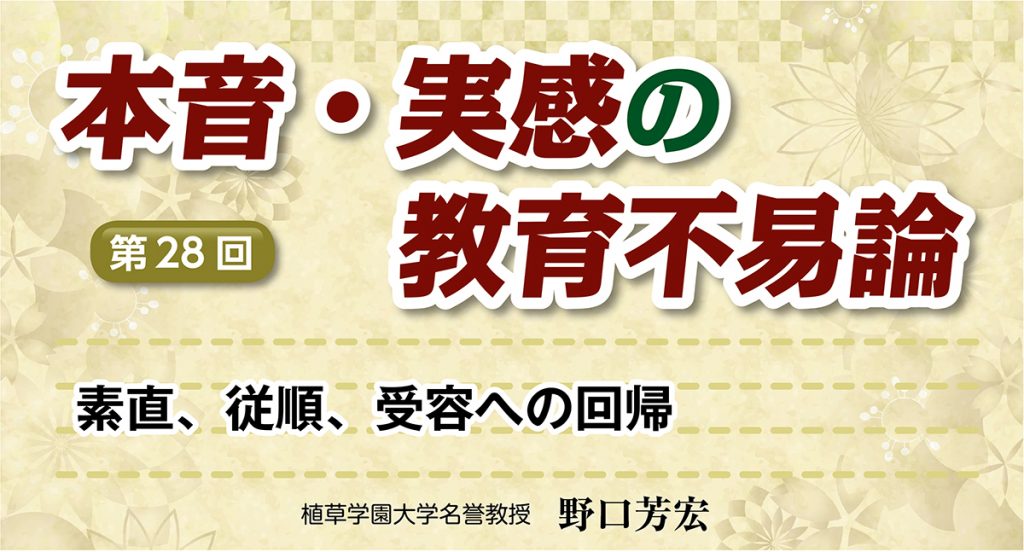
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第28回は、【素直、従順、受容への回帰】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 指示や命令への対し方の傾向
注意する。叱る。仕事を頼む。手伝わせる。──これらには、働きかける側に多少の遠慮やためらいや後ろめたさがある。できるならそれらを働きかけずにおくか、自分で何とか処理したいという思いがある。
しかし、相手の為を思うと、そういう自分の内部的心情を超えて、注意したり、叱ったり、仕事を覚えさせたりしなければならないという場合もある。
そういう折には、相手の出方、反応がどうしても気になる。簡単な話が、相手が気持ちよくそれに応じてくれれば嬉しいし、ほっとする。反対に、むっとしたり、反抗的になったり、という不快な表情、仕草を見せれば、こちらにいささかのためらいがあるだけに、言わなければよかった、頼まなければよかったという悔いの気持ちがよぎることにもなる。
そういうことに重ねて出合うと、自然にあの人には、あるいはあの子には、もう言うまい、言っても無駄だ、言わない方がいい、という思いを抱くようになる。そういうことが重なれば、だんだん、話しかけるのも、口を利くのも億劫になって、結局は当たらず障らず、疎遠な間柄になっていくことになる。──こんな経験や体験は誰にもあるのではないか。私は、この頃になって、そういう類いの思いが増えてきているように感じている。
注意する。叱る。頼む。手伝わせるなどということは、一般に親や教師が子供に対する場合が多い。つまり、これらの事態は親子関係、師弟関係に多く生ずることと言えるが、広く言えば上司と部下や、時には夫婦のあり方にも通用することだろう。
これらに共通するのは、昔よりも現代の傾向に多く、結局のところ「自分中心」という思いが生んでいる事態ではないかという一点だ。さらに気になるのは、そういう事態によって幸せになる者は誰もいないという皮肉な結末である。
かくて、お互いにだんだん楽しさが減り、不平や、不満、何だかすかっとしないもやもやした漠然とした不快感が広がっているのが現代なのではないか。この問題をもう少し詳しく考えてみたい。

2 指示や命令への「受容」の教育
いきなり注意されたり、叱られたりするということは、一般的には稀である。その前に、「こうするといい」「こうしなさい」「それはやめた方がいい」「直しなさい」というような、告知や指導や依頼や指示がなされるのが普通である。そのような場合に「はい」と受けとめて相手の意向を受け容れて従えば、その場で全ては明るく、楽しく、円滑に進行していく。これが理想的な状態であり、これをこそ重視、徹底する指導や教育が必要なのである。
受容される場合には、指示者も、受け手も、快感に満たされ、楽しく、嬉しくなり、そして事態も順調に推移する。つまり、「三方よし」となり、「生きる力」までもが培われ、人間的成長も期待できる。
実は、敗戦までの日本の教育はこの一点を重んじ、徹底することが共有されていた。老若男女、貧富上下を超越して、これこそが大事なのだということが暗黙の常識知として行き渡っていたように思うのだ。
その一つの証拠に、入学式や卒業式、その他の儀式などに来賓を招いた折の祝辞がある。私は国民学校の4年生の8月に敗戦に遭っているので、敗戦までの来賓の祝辞を思い出すことができる。来賓各位は次のような意味の祝辞をすることが多かった。「親の言い付けをよく守り、先生の教えを身に付けて立派な人になりなさい」と、どの来賓も異口同音に、と言ってよいほどに同じことを話された。大方が同じことを言うので1年生でも憶えてしまう。中には来賓の口真似を上手にやってのけて、笑いを誘う者もあったくらいだ。
祝辞の一致している内容は「親や先生の言うことは必ず守りなさい」という一点である。逆らったり、無視したり、軽んじたりしてはいけない。そんなことをすれば、「立派な人」にはなれないのだ、と諭したのである。つまり、子供というものは、親や先生、大人、長上の言うことは「受容」しなさい。そうすれば「立派な人」になれるのだと「教え」「諭した」のである。
だから、私が子供だった頃、それもとりわけ「敗戦」までの「子供」は、親や先生の言うことは「聞くものだ」「聞かなければならないのだ」と思いこんでいた。どの子も、そういう子供なりの経験知による常識を共有していたと言ってよい。
そして、実際に「言うことを聞かない子」が出た場合、それをそのままにしておく親や教師はいなかった。家により、教師によってその強弱に差はあるにしても、子供は相応の罰を受けた。痛い目に遭うこともあったが、それを世間は、むしろ当然のこととして認めていたし、歓迎さえもした。そのようにして子供は、大人や世間を甘く見ることの怖さを知り、自らを悔い、改めたのだ。素朴ながら、これが教育の原点だ。
いじめは昔にもあった。しかし、大方が一過性で「継続的に」ということは極めて稀であった。いじめた子供が親や教師から手厳しい罰を与えられ、こりごりしていじめから手を引いたのであろう。今のように「面倒な理論」はなかったが、現在の陰湿で計画的で継続的ないじめなどはなかった。今は、複雑で高度な「理論」は多くあるが、いじめがそれによって減ってはいないという「現実」をどう解釈したらいいのか。
「単純かつ明快な教育でいじめが少ない」のが昔で、「複雑で難解な理論が多くあるが、現実のいじめは増えこそすれ依然として減らない」のが現在である。──どこかに、何か、重大な勘違いがあるのではないか。そう思われて仕方がない。
3 欠けている「従順」「素直」の教育
私の本を求めて下さった方からサインの所望をされると、近頃私は決まって「素直が一番」と書くようになった。「素直が一番」というのは、今、最も強く私が伝えたい思いであり、それが私の「本音・実感」である。「従順」と言ってもいいし、「服従」とさえ言ってもいいと思う。
何度もいろいろなところで書いたり話したりしていることで恐縮なのだが、ここでもまた繰り返しておきたい。千葉大学附属小学校の教諭だった折に、心から敬服し、師事していた四宮晟校長先生に、酒の席で私は「伸びる人と、伸びない人とでは何が違うのでしょうか」と伺ったことがある。先生は私の問いに対して即座に答えて下さった。「それは、野口さん、素直さですよ」。そして、「素直な人は必ず伸びる。素直でない人は伸びませんよ」と付け加えられた。今もあの折の言葉がそのまま耳朶(じだ)に甦ってくる。
あれから40年もの時が経つが、時を経るほどにこの言葉の重みと正しさとを思う。身近な知友のあれこれを思い浮かべてもいよいよこの言の確かさを実感する。
「素直さ」とは何か。その正体とは何か。
「素直さ」とは、「相手本位」「相手中心」の心、あるいは「私心を去ること」ではないかとこの頃私は考えている。
教えや、導きや、注意や、叱責をして下さる「相手」に対して、「はい、有難うございます」と心から「受容」できることが「素直」ということの実像、正体ではないか。それらを「私心」によって遮り、受け容れなければ、どんなに価値ある助言や導きも何の意味も持たなくなる。そういう者が「伸びない」のは当たり前だ。
さて、敗戦後の学校教育で「素直」という言葉が社会的なキーワードになったことがあるだろうか。学習指導要領の中に重みを持って位置づけられたことがあっただろうか。不明にして私にはその記憶がない。
敗戦後の教育のキーワードとしては、一貫して、「子供の主体性」「子供の自主性」「子供の個性」「自ら考え、自ら判断し、自ら行動する」等々が叫ばれてきたし、今もその流れが続いている。
これらのキーワードに通底するものは、「自分中心」「自分本位」であり、それらは「相手中心」「相手本位」の「素直さ」とは対極の考えだ。つまり、「素直さ」の教育は、ついぞ日の目を見る機会を与えられぬまま今日まで過ぎてきたのだ。
先に私は「どこかに、何か、重大な勘違いがあるのではないか」と書いたが、その勘違いとは、「自分」と「他者」のどちらを中心にするかという問題なのである。
一部の論者は、「従順、素直な教育が、国民の批判力を弱め、それが敗戦という大失敗を生んだ元凶だ」として、「懐疑、批判、抵抗」の教育が必要だ、と言う。一理はあるが、大人の社会についてならともかく、それをそのまま子供の教育の世界に持ちこむのは如何なものか。ごくごく大まかに言うと、戦後教育は、「一部の論者」の主張どおりに展開してきたとは言えないか。その流れは今にも尾を引いて続く。
突然だが、ある本に、GHQの日本占領の根本目的は、「二度と日本が世界の脅威となることがないように日本を弱体化すること」だった、とあった。今、日本人の精神は、大きく、利己的、刹那的、享楽的に傾き、犯罪、詐欺、殺人、脱税、贈収賄が多発している。それが子供の世界にまで影を落とし、いじめ、万引き、不登校なども後を絶たない。これらは「占領政策」の成果だと言えなくもないように思うのだ。
占領政策の根本目的が「日本の弱体化」にあったとすれば、その目的は見事に成功しているのではないか。「一国の衰微は、外からの力ではなく、内からの人心の崩れによって生ずる」という意味の格言があった。「自己中心的な利己主義の広がり」「権利の主張はするが、義務は果たさない」「自分の責任は棚に上げ、他者の非を突くことに執心する」「振りこめ詐欺の横行」「一流企業の内部的腐敗」「家庭崩壊」「学校崩壊」などの傾向は、「内からの人心の崩れ」の表れとも言えよう。
4 「主体性」「自主性」? その前に
「主体性」「自主性」「個性」を大切にするということそれ自体は結構なことだ。真っ向から反対することはできにくい。
問題は、「それらの主体」である。善人の、あるいは分別ある者の、「主体性、自主性、個性」は大切にされて然るべきだ。
だが、犯罪者や公序良俗を乱す者の「主体性、自主性、個性」の重視に賛同する者はあるまい。「主体性、自主性、個性」が重視されるべきは、それにふさわしい見識の持ち主に限られる。この肝心な認識がしばしば軽視されてとんでもないことになるのだ。
ところで、「子供」の本質とは何だろうか。私は、「無知、未熟」こそが子供の本質だと考えている。
だが、私のこの考え方は「袋叩き」に遭いかねない世相、世論、世情にある。「無限の可能性を孕(はら)むそれなりの完成体」としての子供を何と心得るか! との声も聞こえる。かかる甘言、言説は「今受け」をする。これを私は「子供天使観」と呼び、「子供中心主義」の前提になっていると見る。
素直に長上の教えを吸収すべき原点を忘れて、「無知、未熟」な者の「主体性」「自主性」などを過信するのは危険なのだ。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ
『総合教育技術』2019年7月号より