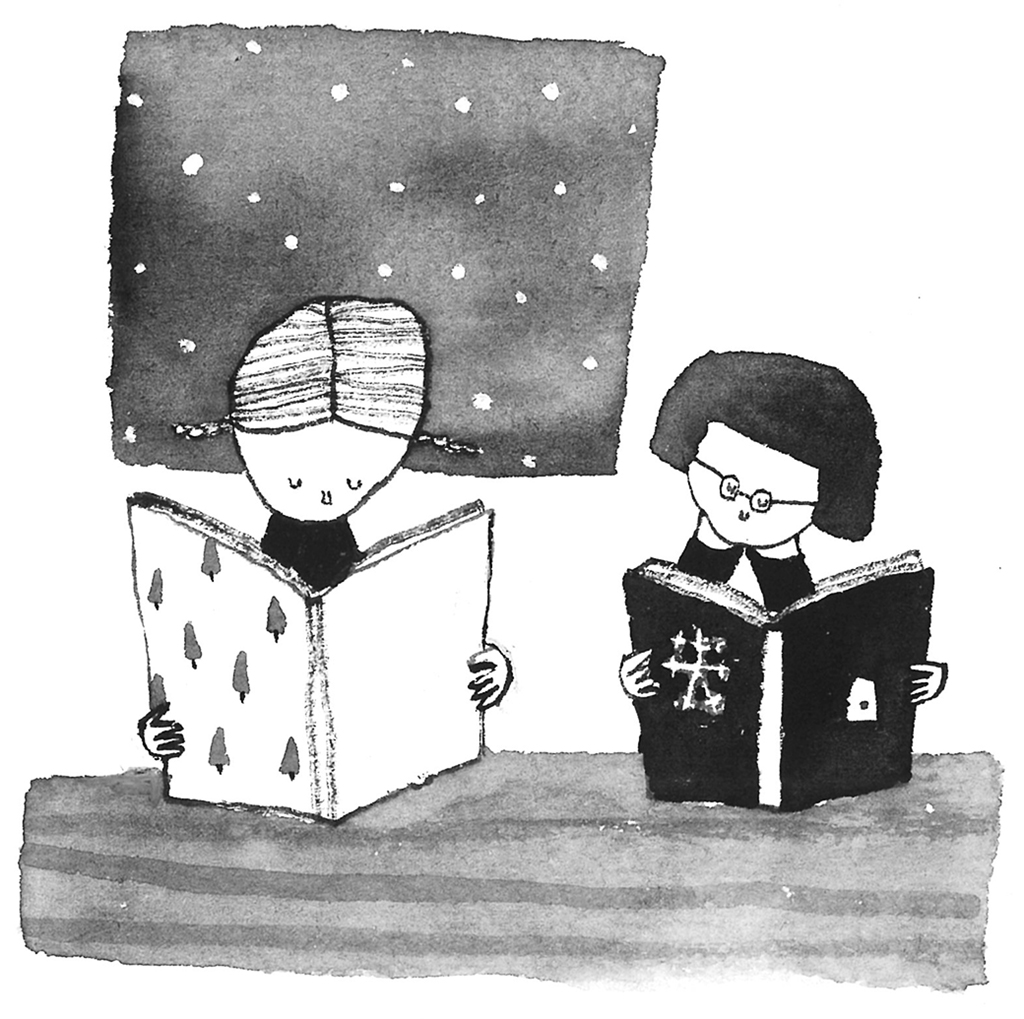今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その3) ─校内研究計画の功罪(下)─【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第62回】

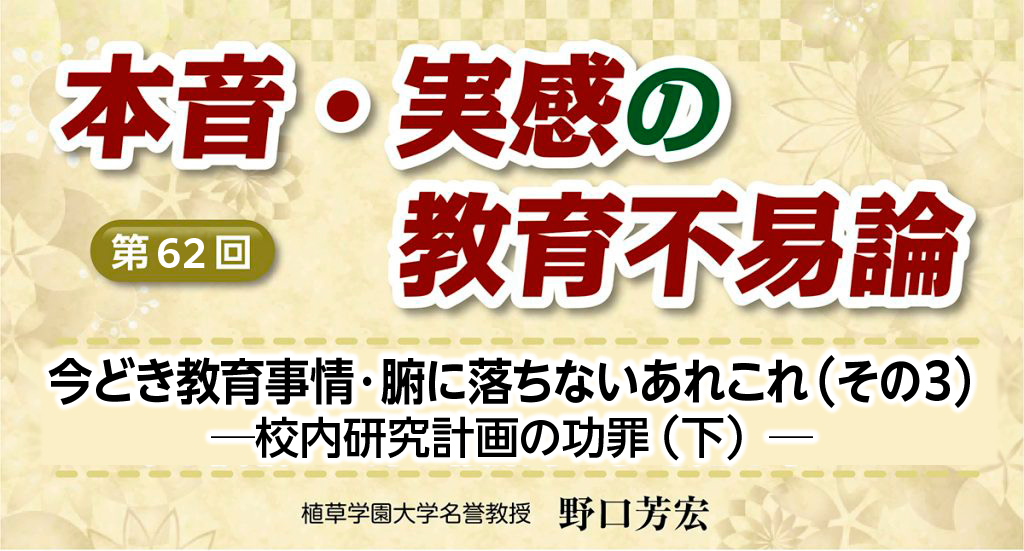
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第62回は、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その3)─校内研究計画の功罪(下)─】です。
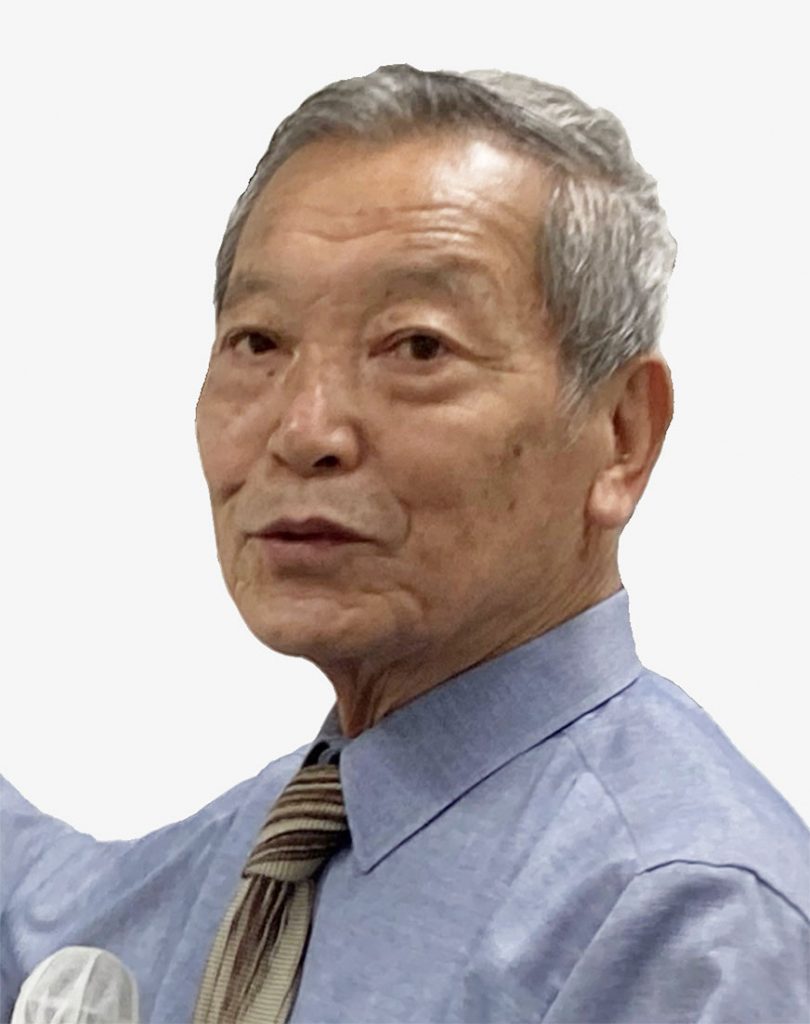
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
「研究計画」作成の功罪(承前)
自然科学の研究計画では、研究主題、研究課題について充分なる研究経過や研究成果を調べ上げ、現在の研究の到達水準に照らして何が未解決なのか、その原因はどこにあるのか等々を明らかにしたその上で、一つの「仮説」を立て、問題を解明していくことになるのであろう。
だが、人文科学分野に属する教育の、それも指導法や授業法に関する改善策という問題になると、大方は、「反省と気づき」に基づいて、うまくいかなかった所を「考察、分析」し、改めるべき所を「工夫」して試してみるということの繰り返しによって解決し習得していくというのが、王道ではないか。先の『女教師の記録』や、『二十四の瞳』の教育実践の成果は、そういう単純明快な中から生み出されてきたものであろう。
研究主題の設定も、仮説の設定も、それぞれの「設定の理由」もない。それらを明文化したり、されたりした中からの産物ではない。むしろひたむきな教育愛に基づいた、剝き出しの実践に挑み、首尾よく進めばそのまま続け、うまくいかなかったら謙虚に先達の教えを乞う。自らも考え、工夫し、再挑戦に挑むという飽くなき前向きの繰り返しの中から輝く成果を生みだしていったのであろう。
以下は、いくつかの具体的な項目についての考えである。
➀研究主題の抽象性
ある学校の研究主題は次の通りである。
「全ての子供が主体的に学習に取り組むようにするための授業のあり方」
全ての子供が、主体的に学習に取り組むようになればすばらしいことで、これに異を唱える者はいないだろう。そのようにするための指導のあり方が明らかになったらどんなによいだろう。これにも異論を唱える者はあるまい。
だが、改めて「主体的に学習に取り組む」とはどういうことなのだろうか。改めてこの言葉の内実は何か、ということになると簡単には答えられない。分かったような、分からないような言葉である。確かにそれは「主体的ではない」よりはずっとよさそうである。だがそれから更に先に進むとするとやはり難しい。難しいけれども、大方の学校の研究主題というものの表現はこれと大同小異というところではないか。
翻って、授業をしている教師にとって、目の前に生起する実態は、例えば次のような片々のいくつかである。
ア、発言する子がいつも決まっている。改めたいが──。
イ、発言を促してもその傾向が改まらない。
ウ、「なぜか」と問うと沈黙してしまう。
エ、ノート作業をさせると時間がかかって授業が進まない。ノート作業の個人差も大きい。
オ、発言が結論だけで短い。筋道を立てて話せない。
カ、発言の声が小さくてみんなに届かない。
キ、ノートを取ることができない子が目立つ。
ク、ノートの文字が乱暴だ。
ケ、宿題を出してもやってこない子がいる。
コ、学用品をそろえられない子もある。
サ、私語が多い。などなど。
これらの片々が日常なのである。あるいは毎時間の様子だとも言える。そして、これらが重なると授業は進みにくくなり、予定した進行ができない。つまり、大方の教師は子供らが「主体的でない」ことになんか困っているわけではないのだ。
ところが、「研究計画」に書く「研究主題」としてはやはり何やら「それらしく」書かないといけないというプレッシャーがかかり、教室の現実、事実、実態どおりを書くわけにもいかない。かくて、体裁のいい抽象的な表現になるのである。その表現でいいかどうか、ということで何回も会議を重ねたりすることにもなるのだが、そんなことにどれほどの価値があるのだろう。
先に挙げたアからサまでの現実的な気がかりは、職場のベテランに尋ねればすぐ教えてくれるだろうし、教わった通りにすれば即座に解決することなのだ。それらは大方ベテランの「工夫」によって生み出されたものであり、技術、方法、手立てなのだ。一校が一年かけて取り組むようなテーマではあるまい。
②役に立たない仮説と成果
研究主題が抽象的なのだから、それを解明する仮説も抽象性を免れない。
「ひとりひとりに自分の考えを持たせ、失敗や間違いを恐れないように授業すれば、どの子も主体的に学習に取り組むようになるであろう」
この文言自体にも、さほどの問題はあるまい。当たり前とも言える。「検証」「実証」をするまでもないことだとも言えよう。換言すればそれぞれの教師の「努力目標」である。こんな仮説でも、教員全員が納得、共有できるようになるには何回かの話し合いが必要だ。それなりの時間もかかることになる。
さて「仮説」を「結論」あるいは「定説」とするには、研究の手続きを経て実証しなければならない。そこで、「実証の為の授業」が必要になるのだが、これがなかなか難しい。ずばりと言えば、実証のしようがないからである。形の上ではそれなりに検討された、実証の為の授業をし、ビデオに撮ったり、録音したり、子供のアンケートを取ったり、参観者による授業分析をしたりという手続きを取るだろうが、果たしてそれが「実証」に値するかというと、それも怪しい。結局は、尤(もっと)もらしい論文風の文章に作文することになり、「紀要」や「報告書」となって一件落着となる。市や県から「研究指定」を受けると、このような「整然」とした部厚い「報告書」を作り上げてその任を果たすのが一般である。その「研究主任」になると、その労力と心労は、大変なものになる。引き受けた学校も大きな負担になる。
負担が大きくても、「成果」が上がれば、それなりの価値があり、心労も苦労も報われることになるが、実際はその実効は殆(ほとん)ど分からないと言ってよいだろう。教育委員会や研究所には毎年このような「研究冊子」が届けられるが、それらが、現場の教育実践を充実させたり、教師の負担が軽くなったり、子供の学力が向上したりという話はあまり聞いたことがない。
研究主題も、その設定理由も、仮説も、その設定の理由も、教室の実践や悩みや問題とはかけ離れた「研究計画」なのだ。その面倒な手続きには従ったのだが、さて、それが本当に日本の教育の進展に「役に立った」と言えるのだろうか。

③残された課題に進化がない
しばしば、次のような後書きに出合う。
「この研究に一応の区切りはつけたものの、実は研究は始まったばかりで、残された課題は多くある。これらの課題に向けて今後とも頑張っていきたい」
正直な本音だろうが、その課題の解決に向けて歩み続ける学校は稀である。「研究指定校」は次の番がすでに決まっている。指定した機関の関心は当然のように次の新しい指定校に向けられていく。
指定を解かれた学校はほっと胸をなで下ろして「残された課題」は、間もなく「忘れられた課題」になっていく。そして、先に挙げたアからサまでのような片々の、当面の課題は愚痴の種として延々と続くままだ。大方の読者の方が、私がここに書いてきたような指摘に共感を持って頷いてくれるのではないか、と私は思っている。敗戦後78年も経過することになるが、一体この78年間に、義務教育機関の小学校、中学校の教育に具体的な向上や進展はあったのだろうか、とふと考えてしまう昨今である。
④「研究」と「修養」のアンバランス
「教育は人である」と、昔から言われてきた。ここで「人」というのは、「教育をする人」を意味している。もう少し踏み込んで言うなら、教員の人格、人間性ということである。教育という「崇高な使命」を担う教員の「教養の深さ、教養の豊かさ」と言い換えてもよいだろう。
教育をする人の資質の向上を期待して、教育基本法第9条は次のように書いている。
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
私は、〈教員〉の在り方を述べたこの条文を襟を正す思いで読む。自らが選んだ職業が「崇高な使命」を担っているのだと言われれば光栄この上ない。誇りに思う。その次に続く「絶えず研究と修養に励み」という文言にも私は深い感銘を覚えるのだ。
いろいろな所で、何度も書いていることを、ここでもまた繰り返さずにはいられない。「研究と修養」という部分である。
「研究会」「研究計画」「研究主任」「研究公開」「研究報告」などなど、「研究」という言葉は、耳に胼胝(たこ)ができるほど教育界に広がり、使われている。だが、もう一つの「修養」という言葉は、学校という職場でも、教育界でもついぞ聞いたことがない。また、この事実に気づいている人も殆どいない。「研究と修養」と書かれているのに、教育界は敗戦この方、昔も、今も全く「修養」という言葉を口にも耳にもしていない。これこそが、教育界最大の、敗戦後の汚点、過誤、だと私は考えている。「研究」という名で行われている教員の営みは一切合財、全てが「子供改善」である。教師の関心の全てが「子供の学力」「子供の読書」「子供の道徳性」「子供の体力」なのだ。そのように導く「自己」「自身」の「学力」「徳性」「読書」「生活習慣」などについての自省、内省、向上、錬磨が話題になったことは殆どない。教師の「自己改善」は関心の外であり、「棚上げ」状態のままなのだ。
「教育は人である」という格言は、「子供改善」という「他者改善」のその前に、まずは「自己改善」に努め、励まねばならないのだ、というのがその真義であろう。
子供改善は「教える」ことによって子供を「学ばせる」という営みであり、これを「研究」と言っている。教員は、「教えること」「学ばせること」は大好きなのだが、自分自身が「教わること」「学ぶこと」は大嫌いなのであるらしい。「修養」という言葉が、昔も今も殆ど学校では使われず、聞かれないということが何よりも雄弁にその事実を語ってくれている。
教師自身が、自らの未熟と非才にまず気づき、「絶えず」謙虚な自省に基づく「修養」という「自己改善」に励むならば、日本の子供の現実は大きく変わると私は確信する。官民ともに「修養無視」という全国的な法令違反をしていることに気づくべきだ。子供よりも教師の方が学び、子供よりも教師の方が本を読み、子供よりも教師の方が徳性を高め、まさに模範の師となった時、子供も保護者も教師を尊敬し、信じ、慕うようになること間違いない。
昔は、そのように信じられ、敬され、慕われるように師道を歩んだ教師の下に教育が実りを見せたのだ。役に立たない研究ごっこには見切りをつけ、工夫に工夫を重ねつつ、自らを磨き、高めることに教員が目覚めることだ。それによってのみ教育は大きく前進するだろう。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ