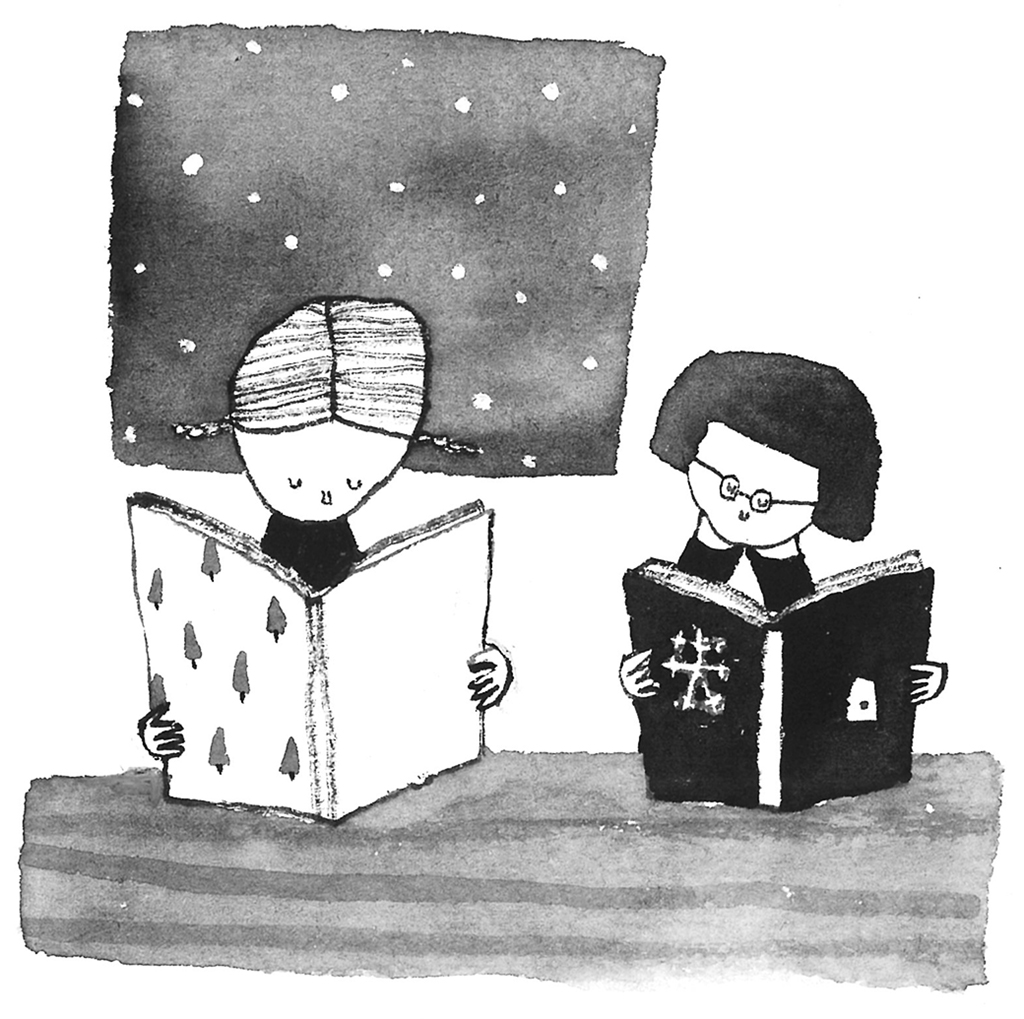今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その2) ─校内研究計画の功罪(上)─【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第61回】

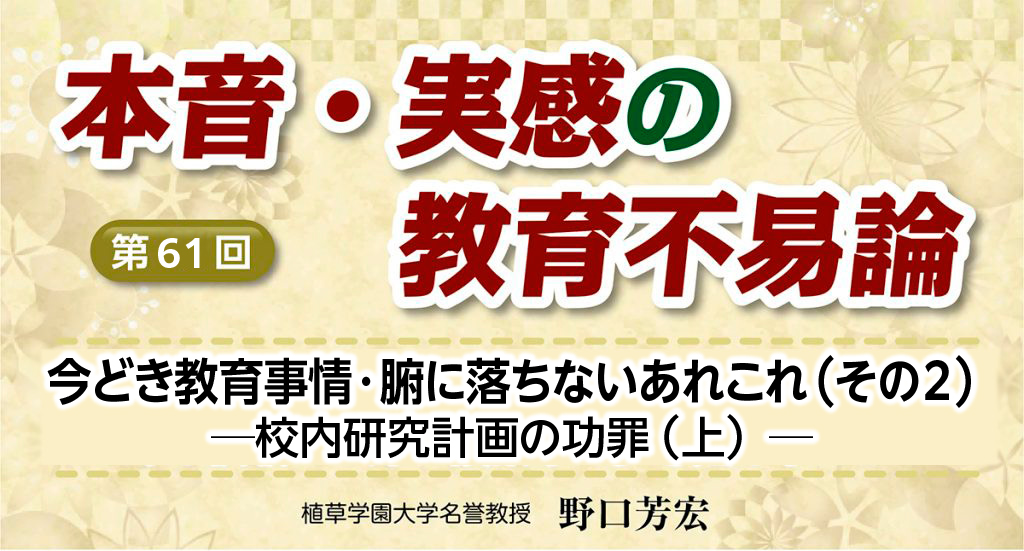
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第61回は、【今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その2)─校内研究計画の功罪(上)─】です。
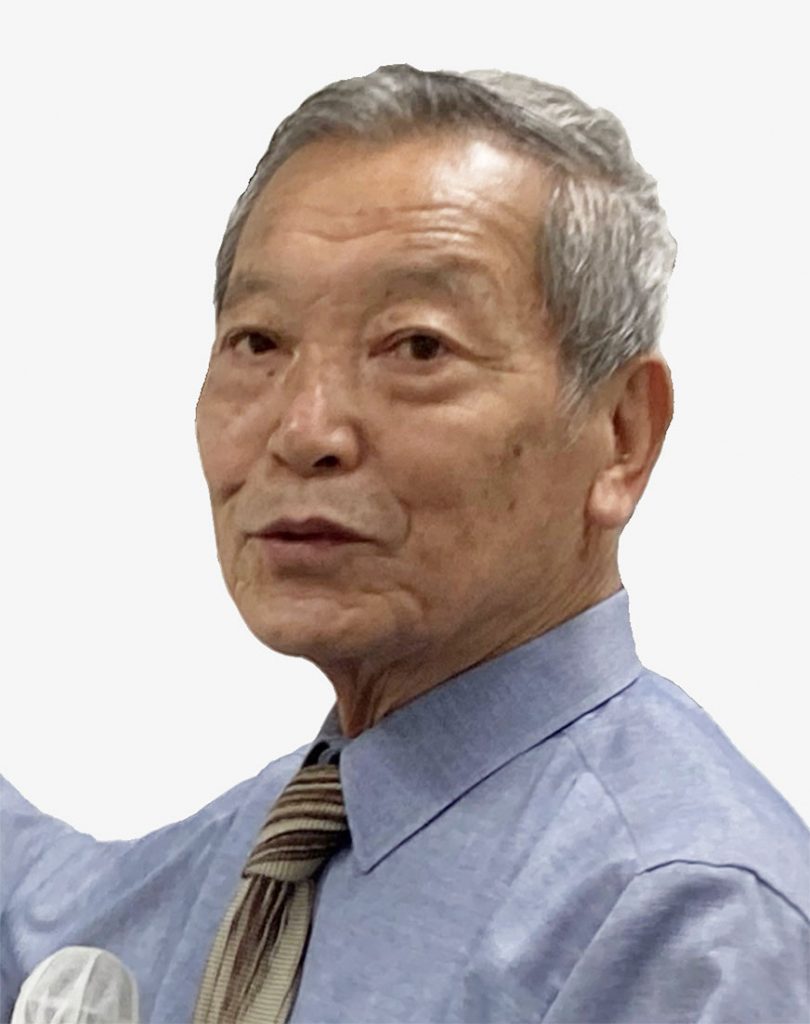
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 校内研究会充実の一事例
ざっと30年もの昔のことになるが、某市の教育センターから、市内の研究主任の研修会の講話依頼があった。「頼まれたら断らない」というのが私流の信条なので有難く引き受けさせて貰った。講演のテーマは「校内研究の充実を求めて―研究主任の役割とは―」というようなものであった。
校内研究、とりわけ授業研究に限ればその果たす役割は大きい。私が初任以来5年間勤務した学校の校内研は、今振り返ってみても実に「充実」したものであった。あの5年間が、私の教師人生の土台、基礎、根底を築いてくれたと心の底から思う。あの5年間がもしなかったら、今の私は全く存在しなかったに違いない。
その実際をかいつまんで述べれば次の通りである。
ア、指導講師は、県下第一の実力者のみ
何よりも有難かったのは講師の陣容である。国語ならばこの人。社会科ならばあの人。算数ならこの人、――というように県下第一の実践家を校長が直々に招いてくれた。そういう力のある先生に指導を受けるのだから、我々もそれに応えよう、という覚悟で誰もが授業に臨んだ。
教科の本質に立脚した指導の言葉は、我々のやる気を促し、高め、元気づけた。
イ、事前研究会のあり方と厳しさ
国語科を中核としていた学校だったが、その事前研究会は本物だった。全員が全学年の国語教科書を持っていた。まず15分で教材を黙読し、その作品の「主題」をそれぞれが黒板に板書する。指導書に書いてある主題を丸写しする者などなかった。自分の力で読みとったことを書くのである。様々な「主題」が書かれる。
30分ほどの討論、議論が楽しみだった。力の有無、見識、教養の高低、深浅は隠しようもない。頼りになるのは自分だけだ。その討論で読みの力も鍛えられた。
作品の読みとりが確かになれば、発問や板書は授業者が考えろ、と突き放されて事前検討会は終了だ。だから、授業後の討論が盛り上がる。ハウツーは授業者の責任である。共同立案などは全くなかった。話し合うのは「根本、本質、原点」に関わることに限られた。だから力がつくことになる。当然のことだ。
ウ、授業研究会当日は半日授業
3・4時間目に授業公開6学級。45分間に講師と共に3学級の授業を見る。全校で12学級だったから、国語科についての公開授業は年間各6回。最後は全校で国語科授業の市内、県内向けの公開研究会が伝統になっていて鍛えられた。
午後の授業はなく、全児童下校する。校内研で培った高い力を子供に返せば十分に学力は身に付くとの信条が共有されていた。
それは君津町立貞元小学校。農村部にある12学級の小規模校であったが、子供の学力は高く、近隣の小学校では上位を誇っていた。校内研が子供の学力を高めていたのである。地域も学校の研究方針を応援し、ここから多くの優れた教師が輩出した。
私は当時の貞元小学校の授業研究会によって授業の本質を叩き込まれたと思う。いわゆるハウツーは問題にされず、教育の本道、指導の根本、授業の本質を学んだ。教育研究の本来的な姿が具現化されていた職場である。形式や流行やハウツーは無視する気概があった。

2 「研究計画」作成の煩瑣(はんさ)と成果
さて、冒頭に述べた「研究主任研修会」である。私は、第一声を次の問いで始めた。「研究計画を立てる。その場合、研究の仮説を設けるだろう。校内研究を進めていく上で研究仮説が必要だと思う人は○を、必要ではない、という人は×をノートに書いて下さい。」
この結果を読者諸賢はどう想像するか。回答者は全員研究主任である。×を書くものがあったか。――実は、ひとりもいなかった。全員○である。――当然だろう。
続いて私は次のように求めた。
「では、自分の学校の研究仮説を、ノートに書いてみて下さい。」――と。
さて、この結果を読者諸賢はどのように想像するか。全員が、さらさらと書いたか。
実は、満足に書けた研究主任はひとりもいなかった――のである。この事実をどう考えたらよいのだろう。いろいろ出よう。
ア、研究主任としてそれは望ましくない
イ、そっくり覚えているのは無理だ
ウ、要らないから覚えないのだ
エ、研究そのものが形骸化していないか
オ、学校の本務は研究活動ではないから
この中にあなたの考えに近いものがあったか。以下は私の意見である。
学校現場の研究活動のあり方に大きな、否、革命的とも言うべき影響を与えたのは、群馬県教育研究所連盟が刊行した教育研究の科学的なあり方を述べた一書だと私は考えている。私もその一書を持っていたのだが、たまたま、書庫を解体する話が出て仲間数人が、書籍処分の為に片端から紐で結んで捨てる仕事をしてくれたので当該書を見つけることができずじまいになった。だから、刊行年も正しい書名もわからない。何しろそれは60年もの昔の事である。従って以下は私の不正確な記憶に頼る他ない。誤りは御指摘を保って正したい。
その本が出るまでの教育研究の成果は、その大方が、実践者の丹念な「実践教録」に頼っていた。私の手許には有名この上ない『女教師の記録』(平野婦美子著、国土社刊、1994年1月)がある。
本書の原著は、戦時下の昭和15年(1940)4月、西村書店刊であり、私の物は復刊本である。復刊本の解説者中野光は次のように述べている。その一節である。
「当時の教育界に新鮮な感動をよびおこし、その売れ行きも記録的だった。(中略)古書店で求めた2冊の1冊は30版めのものである。発行は、初版からわずか3ヶ月しか経っていない7月15日となっている。他の1冊は1942年12月発行の106版である。30版のものは「文部省推薦」とあり、表紙の裏には城戸幡太郎の次の文がある。」
平野婦美子さんによってペスタロッチのゲルトルートは現代の日本に新生せしめられた。この書物は世界に誇る日本の教育文学として永遠に保存されるべき記録である。
本書がいかに多くの読者に愛読され、大きな影響を与えたことか、驚くべき成果だ。
さて、この不朽の名著の刊行は、群馬県教育研究所の『教育研究法』(正しい書名は不明)出版のはるかに前である。壷井栄のこれまた不朽の名作『二十四の瞳』の刊行は1952年(昭27)である。本書は何本も映画やドラマでも紹介され、広く知られている。全国の教員の中にも、大石久子先生に憧れ、学んだ者の数は夥(おびただ)しいことだろう。
手許の『女教師の記録』は、国土社の『現代教育101選』中の一冊「52」である。このシリーズの中の教育実践者としては、『学級革命』の小西健二郎、『村を育てる学力』の東井義雄、『村の一年生』の土田茂範、『第三の書く』の青木幹勇、『授業を創る』の大村はま、『授業入門』の斎藤喜博らがいる。このシリーズにはないが、向山洋一、有田和正、酒井臣吾らの名もぜひ加えたい思いである。
いずれの実践者も、それぞれに持ち味を存分に発揮した面々だが、それらの成果は、一言で言えば、誠実、真剣、謙虚な実践上の「工夫」を重ね、反省と改善を積み上げたことによって生み出されたものであろう。
現在全国的に展開、実践されているところの形式的でややこしい手続きの末に作り上げられた「研究計画」の成果だとは、私には到底思えない。
私事に亘って恐縮だが、私の実践者としての教員生活を振り返ってみても、私なりに吟味を尽くした「研究計画」のお陰で今日があるという「実感」は極めて稀薄なのだ。否、もっとはっきり言えば、「研究計画」の作成、その検討、協議、共有に至る面倒な手続きや会議の殆どが無駄だったのではないかとさえ思うのだ。
今の私は、無職の身であり、組織の中の一人というしがらみもないので「研究計画」を立案する立場にはない。縛られてもいない。だが、授業についての考察、吟味、実践、発表などはかなり今でも本気で続けている。日本言語技術教育学会、日本教育技術学会にも所属しているし、役員も務めている。
また、実感道徳研究会、鍛国研、授業道場野口塾、木更津技法研などにも所属し、広い意味での教育研究、教育実践を続けている。しかし、全国の、おそらく殆んどの学校で作っているだろう「研究計画」を作ったり、協議したり、書き直したり、再々提案をしたりという面倒な、「手続きの呪縛」からは解放されている。やれやれである。
3 「研究計画」作成の功罪
群馬県の教育研究所が発刊した『教育研究法』では、従来の研究の仕方の批判が前提になっている。
日本の教育研究は、実践者の経験や体験に対する個人的な考察を述べた実践記録風のものに偏り、科学的な、「研究」とは言えない。研究とは本来科学的な手続きを経た実証的、合理的なものであるべきだ。そうではないか、という極めて説得力のある提言で、これが全国的な反響を呼んで急速かつ広範囲に受容され、広まったのだ。そして現在も色濃くその思潮を踏襲している。
そもそも、研究である以上「テーマ」と「テーマ設定の理由」、その研究によって得られるであろう成果は「仮説」として示し、いかなる理由によってその仮説が生まれたのかという経緯や論拠を「仮説設定の理由」として明示する。ここまでの理論や手続きが論理的に整合していることが必須であり、そのことによって、仮設の実証、立証が可能になる。「仮説実証の手続き」によってそれらを示す。また、立証の根拠事例として学習指導案、実際の授業の経過記録、それらに基づく「分析と考察」を記述し、仮説が正しかったことを総括する。ここに至って「仮説」は「結論」となって承認され、広まっていくことになる──という一連の「構想」が理路整然と述べられている。
物事を、科学的、合理的、分析的に考察していく「研究の手続き」としてこれらは妥当かつ正論といえるだろう。これに反論を加えるのはかなり困難である。その故にこそ半世紀以上に亘って教育現場の研究法の王座を占めて揺るがないのであろう。
だが、これらの全ての手続きを漏れ落ちなく、矛盾や飛躍や独断を排しつつ、理路整然と組み立てるのは決して容易ではない。途方もない手間と時間を費すことになる。研究主任を4月に下命され、「研究計画」の完成が9月、10月にもなったという例も少なくないようだ。その筋のさる実力者は「研究計画ができ上がれば研究の半ばは終わったと考えるとよい」と言って研究主任を励ました由である。これは教育の実践の場である「現場」の本務を忘れた「研究者」「研究屋」の「語るに落ちた」失言ではないか。
手段、方法である「研究」が、いつのまにか「目的」に摩(す)り替えられてしまったのだ。そんな「多忙」に心を奪われているから「苛め」一つ解消できない「現場」になってしまったのではないか。以下次回に続けたい。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ