スタンフォード監獄実験を教育現場に応用する「場面リーダー制」とは?

学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。 今回は、学級の中でのリーダーシップの在り方について考えてみましょう。
文/元・埼玉県公立小学校校長・稲垣孝章
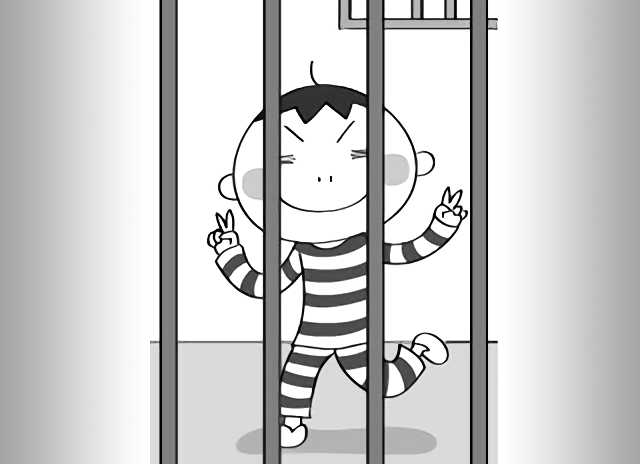
目次
リーダーを固定しない
「どの子も活躍できる学級にしたい」と学級担任であれば誰もが願うことだと思います。しかし、学級内での役割についての考え方、指導の手立てを誤ると、個を生かす望ましい学級づくりをすることは困難になります。
「役割が人間の行動や心理に与える影響」について、フィリップ・ジンバルドーが「スタンフォード監獄実験」を報告しています。一般市民を無作為に募集し、スタンフォード大学の地下に作った監獄で、10人を看守役、10人を囚人役として、2週間その役割を担わせました。その結果、看守役は囚人役に「命令し、暴言をはく」などの非人道的な扱いをするようになり、囚人役は、卑屈にそれを受け入れ、「強い無力感で、人格的な荒廃」が見られたということです。 しかも、看守役の中心として実験に直接かかわったジンバルドー自身が役割にとりつかれて実験を止められず、外部からの働きかけによって、1週間足らずでその実験は中止されたということです。
この実験から明らかなように、人間は役割によって行動が特定される傾向にあり、その役割は心理的にも大きな影響を与えます。したがって、生活班や係活動などのグループ活動を行う際に、リーダーを固定化し、特定の子どもを中心としたリーダー育成をするという考え方は、上記の研究に照らしてみても望ましいとはいえません。特に、初等教育において求められることは、特定のリーダー育成をするという考えではなく、どの子にもリーダーシップを発揮できるような場面を設定していくということです。
「人に従うことを知らない人は、良き指導者になれない」という名言があります。よりよいリーダーシップを発揮するためには、その活動を支えていくメンバーシップとしての経験が重要になります。また、どの子もリーダーシップを発揮できるような組織づくり、活動づくりを行うことにより、子どもたちが互い のよさを認め合う学級風土が醸成されていきます。
集団が個人に優先し、集団に個人が埋没する実践も見受けられます。どの子も活躍できるような、個を生かすよりよい集団活動の展開が、今まさに求められているのです。

