鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」―連載第9回 「授業は子供の素晴らしさに気付く時間です」
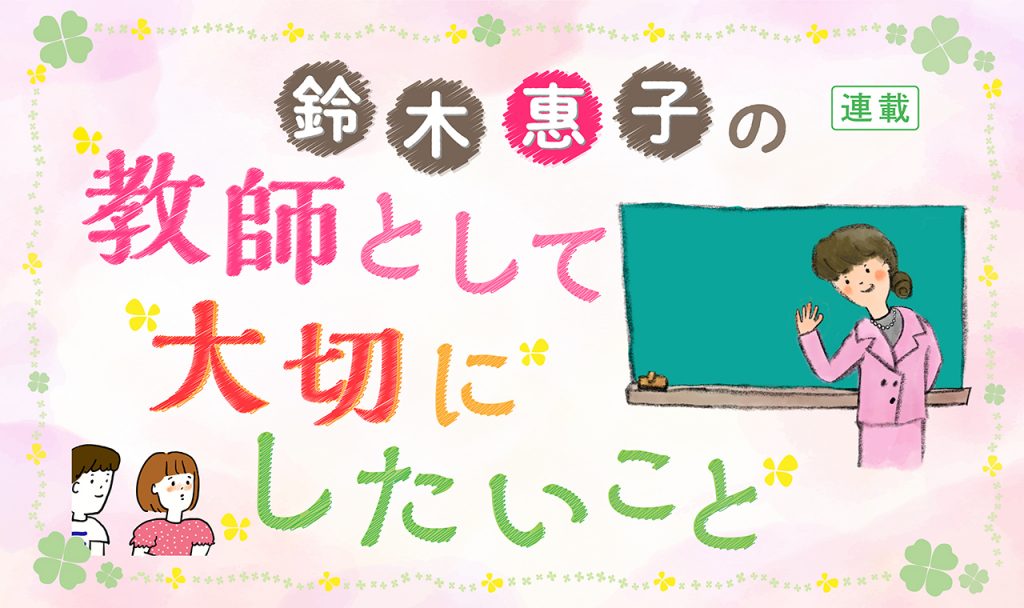
温かい空気の中、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつて全国の多くの先生方がその後姿を追いかけた鈴木惠子先生による書き下ろし連載第9回をお届けします。今回は、「子供それぞれの持ち味や能力が最大限引き出される、子供ファーストの授業」の可能性と魅力について考えていきます。

鈴木惠子(すずき・けいこ) 静岡県藤枝市の元公立小学校教諭。教育委員会指導主事、管理主事、小学校校長等を経て退職。好きなものは花と自然。
「子供ファーストの授業」の可能性
第7回、第8回を通して、「話すこと・聴くことの指導は相手意識を育てることだ」とお伝えしました。相手とは、もちろん共に学ぶ仲間のことです。
「話すこと・聴くこと」の質を高めることによって、「子供が、仲間と共に自ら授業を動かしていく力」も付いていきます。
いつも教師が真ん中にいなくても……、いちいち教師を介さなくても……、第5回でご紹介した富岡学級のように、自分たちで主体的・協同的に学習を進めていく力です。
一人一人の子供から教師へ向いていたベクトルが、教師ではなく、仲間同士へ向くようになるのです。
イラスト/岡本かな子
■ ー 連載 鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」 ー 過去の回はこちら(↓)へ■
■ 第1回「わからなさがわかるかな?」
■ 第2回「し~っ! 先生には聞こえるよ!」
■ 第3回「答えは目の前の子供の中にあります」
■ 第4回「授業観・子供観を見直そう」
■ 第5回「子供ファーストの授業ってどんなもの?」
■ 第6回「授業の主役を明け渡す覚悟を『姿』で見せよう」
■ 第7回「互いに生かし・生かされていることを実感できる話合いを」
■ 第8回「今、全員が耳を傾けたよね! すごく気持ちよくない?」

