鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」―連載第6回「授業の主役を明け渡す覚悟を『姿』で見せよう」
関連タグ
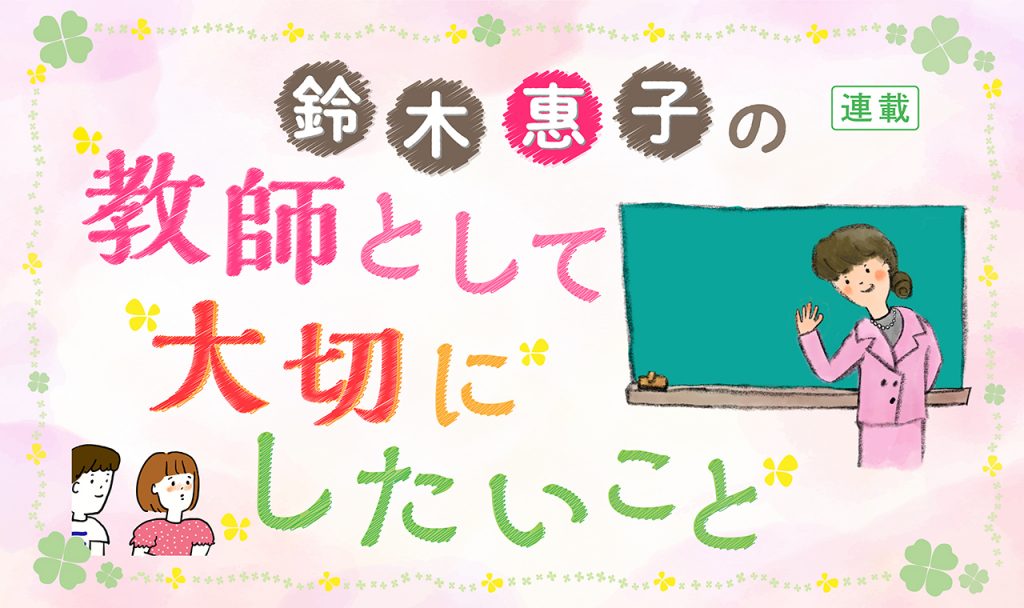
温かく、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつてその後姿を追い求めた先生方が全国にいた鈴木惠子先生。その授業は、授業名人と称された故・有田和正先生から、「日本一の授業」と評されました。連載第6回では、「教師が黙る」「子供たちを信じてとにかく待つ」といったポイントを中心に、子供ファーストの授業づくりについて考えます。

鈴木惠子(すずき・けいこ) 静岡県藤枝市の元公立小学校教諭。教育委員会指導主事、管理主事、小学校校長等を経て退職。好きなものは花と自然。
子供ファーストの授業はどのようにして生まれていくのか
第5回は、校長通信「友垣」から富岡先生の授業の一端をご紹介し、「子供ファーストの授業」を具体的にイメージしてみました。
今回は、富岡学級の子供たちを思い起こしながら、子供ファーストの授業がどのようにして生まれていくのかを考えてみたいと思います。
子どもを主役にするために必要な教師の覚悟
<「困った~!」が学びのスタート>
イラスト/岡本かな子
■ ー 連載 鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」 ー 過去の回はこちら(↓)へ■
■ 第1回「わからなさがわかるかな?」
■ 第2回「し~っ! 先生には聞こえるよ!」
■ 第3回「答えは目の前の子供の中にあります」
■ 第4回「授業観・子供観を見直そう」
■ 第5回「子供ファーストの授業ってどんなもの?」

