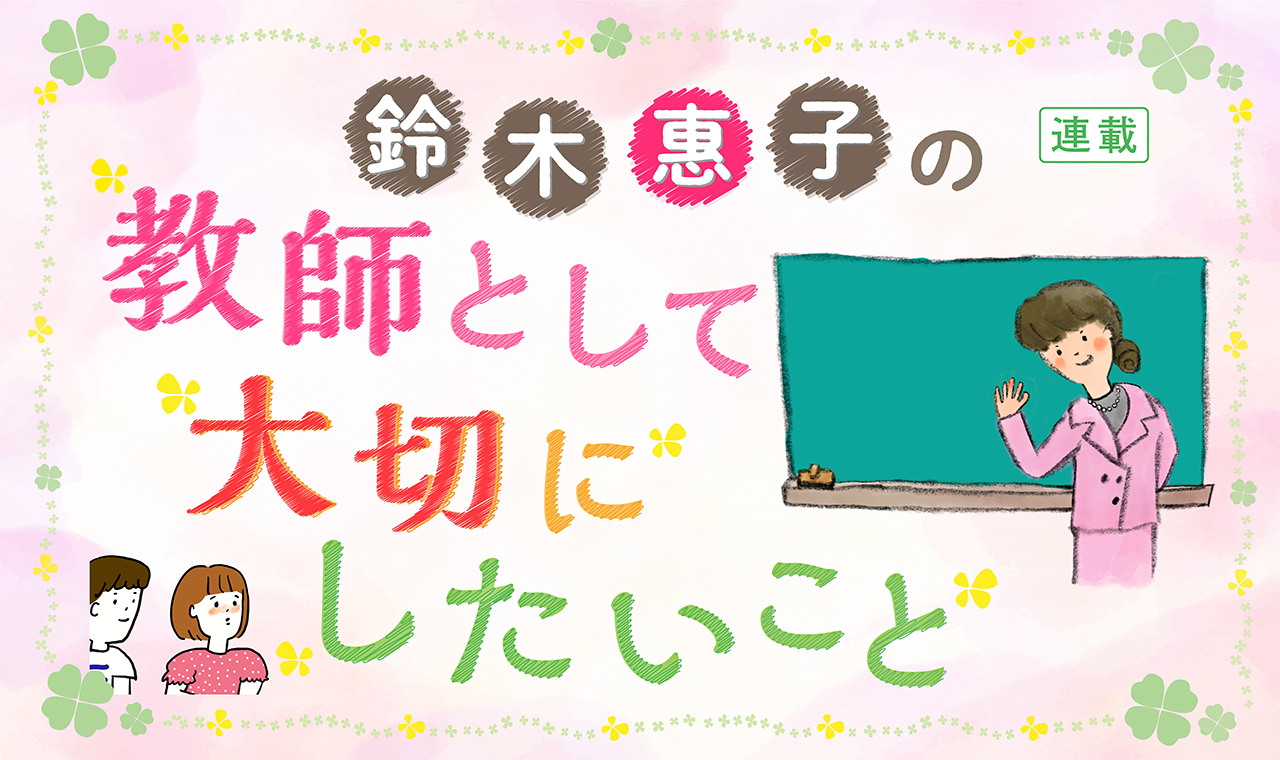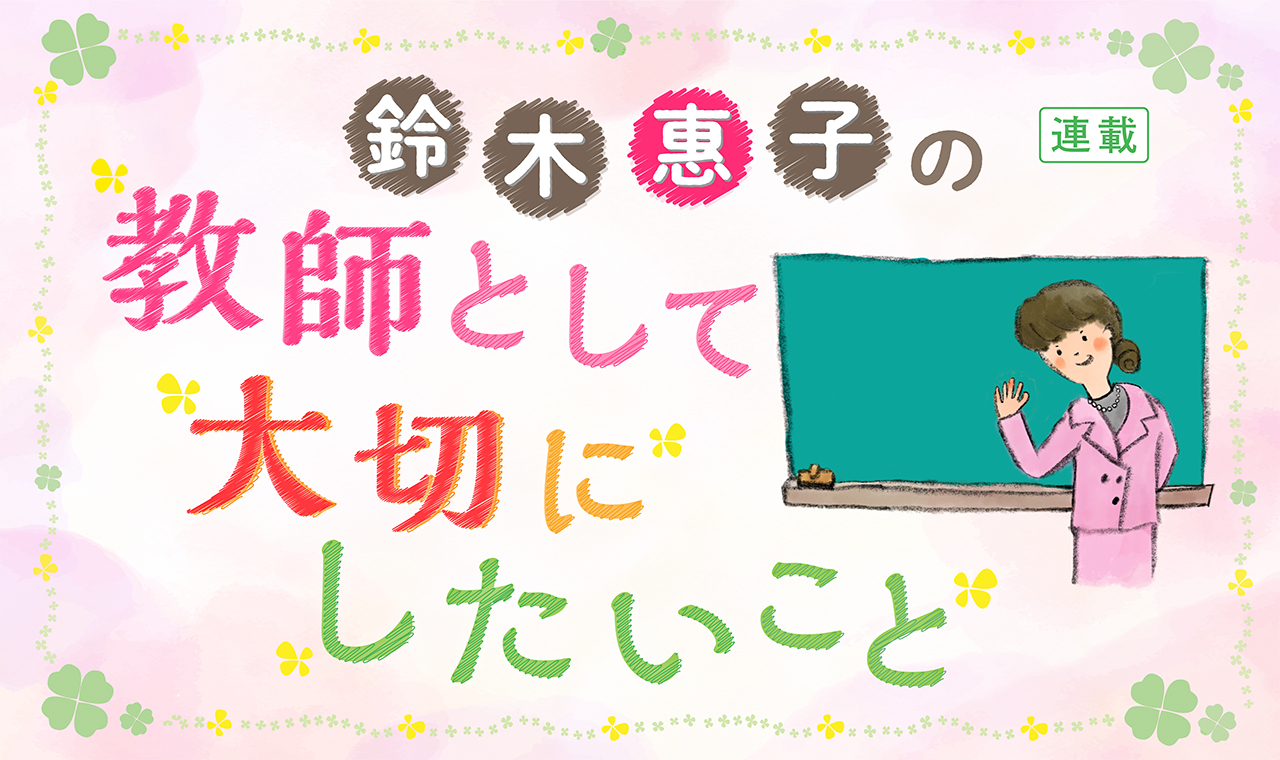鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」―連載第7回「生かし・生かされている喜びを実感し合える話合いを」
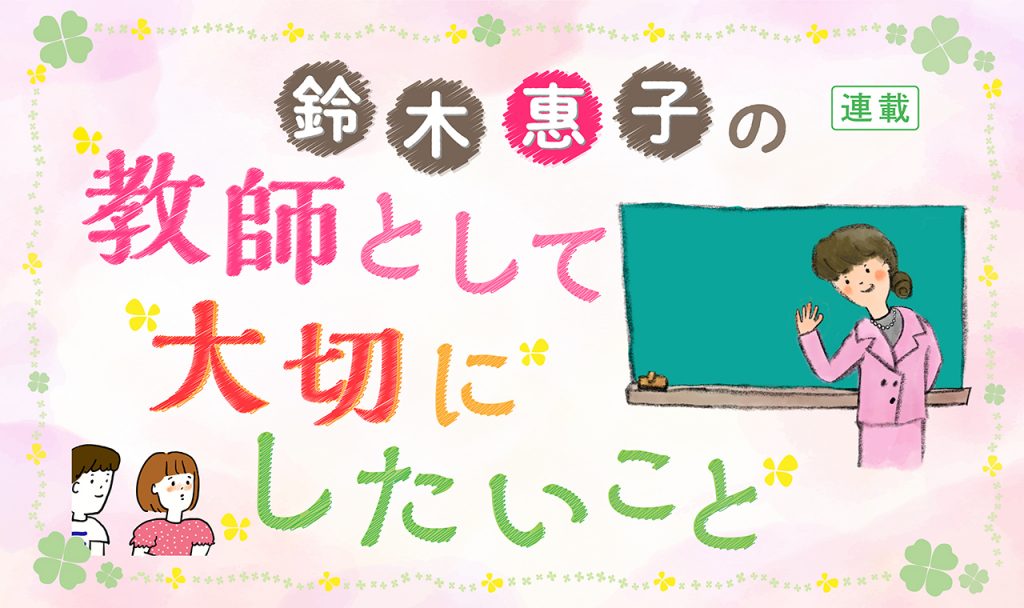
温かく、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつて全国の多くの先生方がその後姿を追いかけた鈴木惠子先生による書き下ろし連載第7回。今回は「話す力」に焦点を当て、対話する喜びに満ちあふれた「ごんぎつね」の授業の様子を覗いてみましょう。

鈴木惠子(すずき・けいこ) 静岡県藤枝市の元公立小学校教諭。教育委員会指導主事、管理主事、小学校校長等を経て退職。好きなものは花と自然。
「喜び」を伴う話合いとは?
第6回は、子供たちに授業の主役の座を明け渡すために必要な「教師の覚悟」についてお話ししました。
「子供の動きを誘発する課題設定」と共に、「しゃべり過ぎない、怖い顔をしない、立ちはだからない」を徹底することは、子供ファーストの授業を実践するに当たって欠かせない教師側の姿勢です。
が、子供ファーストの授業を「主体的・対話的で深い学び」へとつなげるためには、一方で子供たちに積極的な話し手・聴き手としての力を付けなければなりません。
第4回でお話しした「みんなで追究する授業」の牽引力となるのが「話す力・聴く力」です。
心に響く、豊かな対話ができる学習集団を育てるために欠かせない力です。
コミュニケーション能力の育成は、ひと頃、全国の多くの学校の研修テーマになりました。
学校を回らせていただくと、教室に学校全体で取り組んでいる「話し方聴き方」のモデルがよく掲示されていました。
ただ、約束事や型を形式的に指導するだけでは、「喜び」を伴う深い話合いにはつながりません。
イラスト/岡本かな子
■ ー 連載 鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」 ー 過去の回はこちら(↓)へ■
■ 第1回「わからなさがわかるかな?」
■ 第2回「し~っ! 先生には聞こえるよ!」
■ 第3回「答えは目の前の子供の中にあります」
■ 第4回「授業観・子供観を見直そう」
■ 第5回「子供ファーストの授業ってどんなもの?」
■ 第6回「授業の主役を明け渡す覚悟を『姿』で見せよう」