鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」―連載第5回「子供ファーストの授業ってどんなもの?」
関連タグ
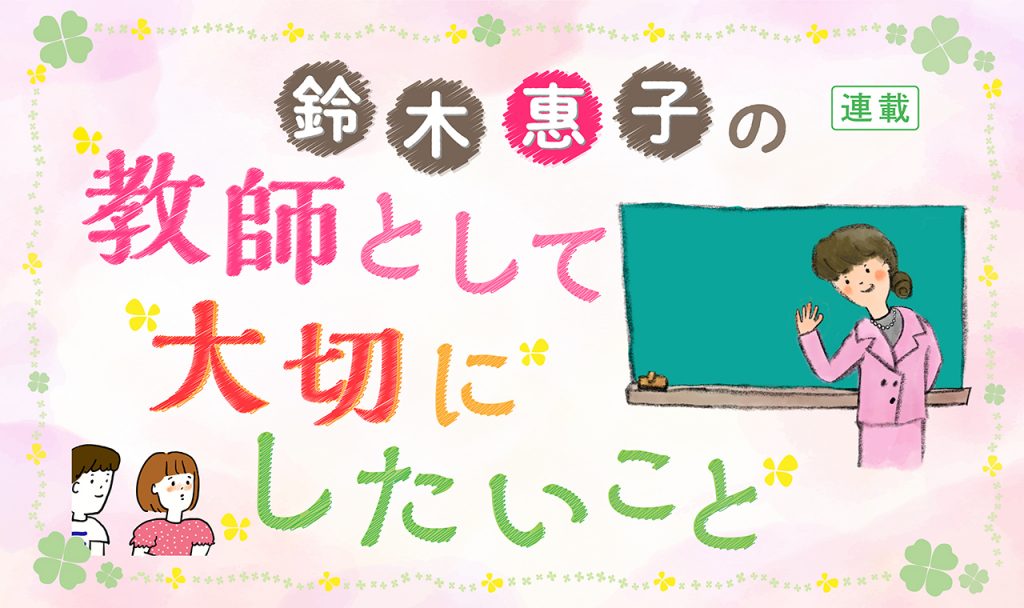
温かく、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつてその後姿を追い求めた先生方が全国にいた鈴木惠子先生。その授業は、授業名人と称された故・有田和正先生から、「日本一の授業」と評されました。連載第5回では、「子供ファーストの授業づくり」の具体について考えていきます。

鈴木惠子(すずき・けいこ) 静岡県藤枝市の元公立小学校教諭。教育委員会指導主事、管理主事、小学校校長等を経て退職。好きなものは花と自然。
10年前の授業を覗いてみましょう
第4回では、「教師として大切にしたいこと」の二つ目、「子供ファースト」の授業づくりについてお伝えするにあたって、授業観・子供観を見直しました。
今回は、かつて私が発行した校長通信「友垣」の一文をご紹介しながら、「子供ファーストの授業」の具体を見ていきたいと思います。
随分昔のものですが、小学校の50代の男性教員、富岡先生が行った2年生算数の授業の様子を書いたものです。
ベテランの先生が授業を公開して下さった時には、その授業実践を、若手に継承したい一心で、よくこんなものを書いて先生方にお配りしていました。
さあ、10年前の教室を覗いてみましょう。
イラスト/岡本かな子
■ ー 連載 鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」 ー 過去の回はこちら(↓)へ■
■ 第1回「わからなさがわかるかな?」
■ 第2回「し~っ! 先生には聞こえるよ!」
■ 第3回「答えは目の前の子供の中にあります」
■ 第4回「授業観・子供観を見直そう」

