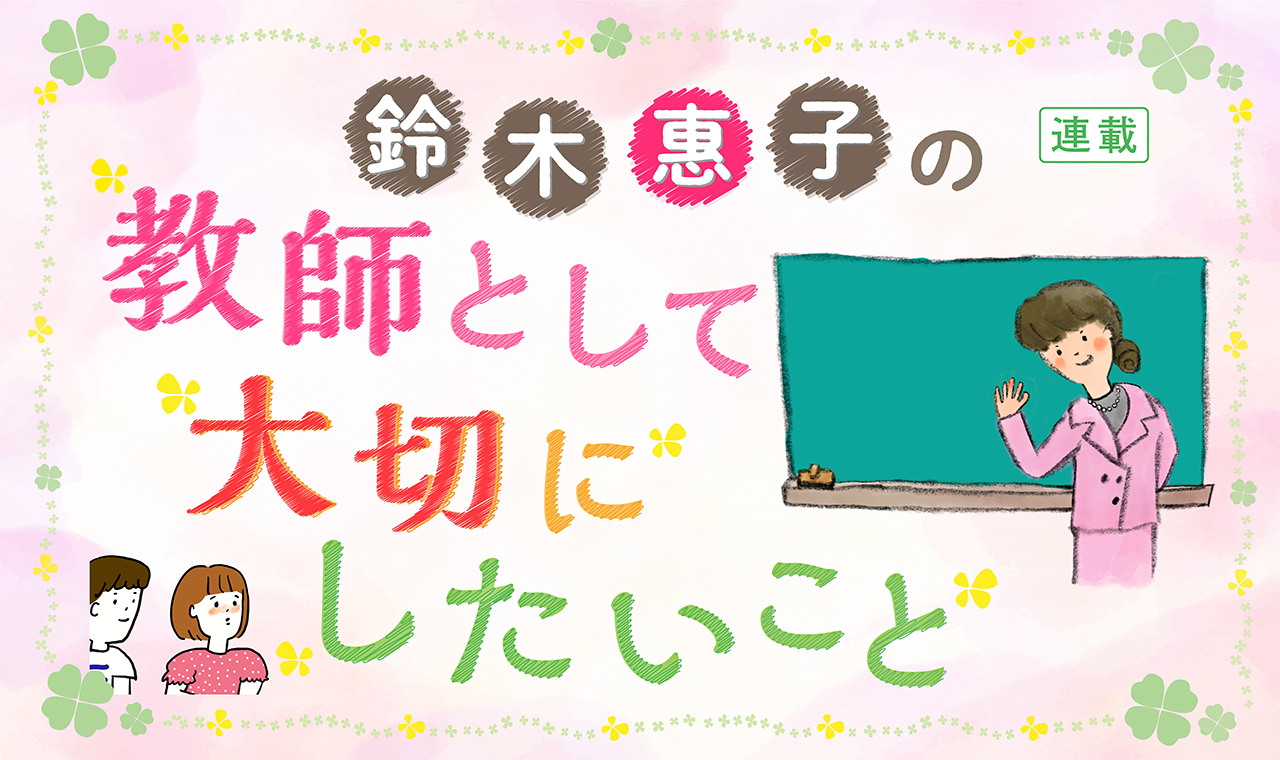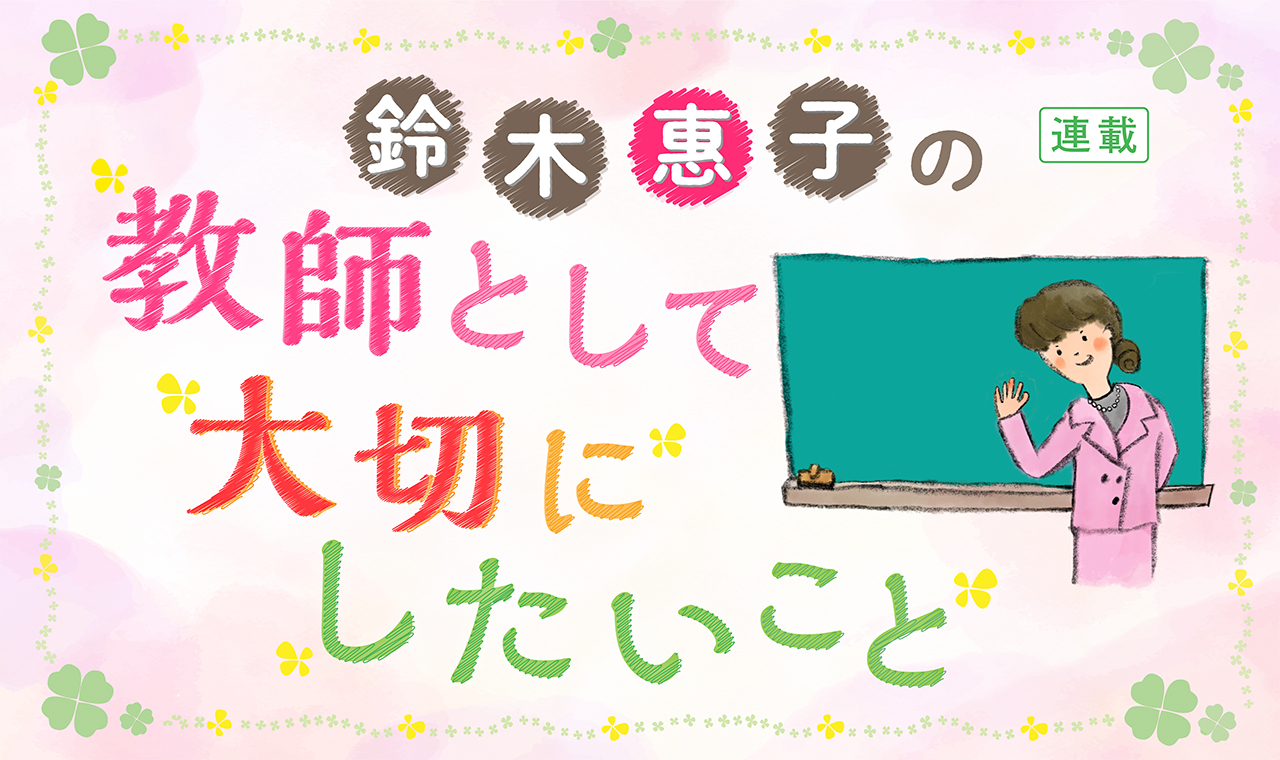鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」―連載最終回「子供と一緒に『今を生きること』を楽しもう」
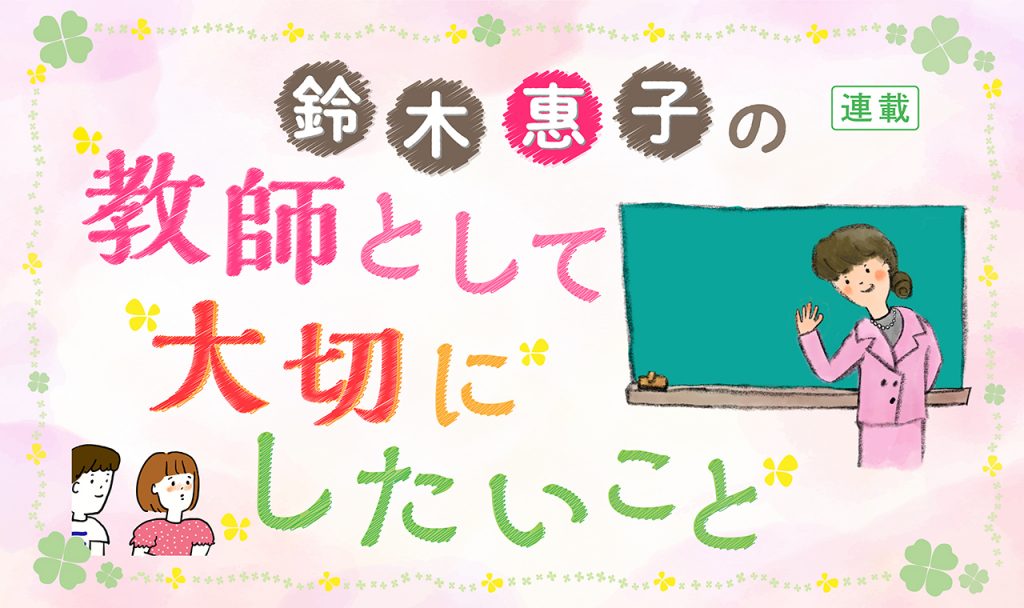
温かい空気の中、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつて全国の多くの先生方がその後姿を追いかけた鈴木惠子先生による書き下ろし連載も、いよいよ最終回。「教師の熱量」や、教室からあふれ出る「空気」について、現場の先生方を勇気づける魂のこもったメッセージをお届けします。

鈴木惠子(すずき・けいこ) 静岡県藤枝市の元公立小学校教諭。教育委員会指導主事、管理主事、小学校校長等を経て退職。好きなものは花と自然。
前回までは、「教師として大切にしたいこと」として、「共感力」「子供ファーストの授業」についてお話ししてきました。
大昔の話に、温かく関心を寄せてくださった皆さんに、心から感謝申し上げます。
最終回は、三つ目の「熱量」についてのお話です。
学校の究極の目標とは?
教師として大切なものの三つ目に、「熱量」を挙げたいと思います。
本当はこれを一つ目にしようかと迷ったくらい大事に思っているキーワードです。
どんな時代にあっても、輝くのは何かに情熱を傾けることのできる人だと思います。
子供の頃、夢中になって何かに取り組んだ経験があるかないかによって、大人になってからの生き方も変わってくるのではないでしょうか?
遊びでも本でもゲームでも、昆虫でもスポーツでも音楽でも……何でもいいのです。
成長過程で何かに熱中した経験がたくさんある人ほど、自分のやりたいことを自分で見つけ、人生を楽しく、創造的に、アクティブに切り拓いていくことができるものと思います。
たとえ上から与えられたり命じられたりした仕事であっても……、たとえそれが雑用と思われるような内容であったとしても……、その中に、自分なりの問題意識ややり甲斐を見つけ、新しい視点を生み出し、新たな地平を切り拓くことができるのは、熱中体験のある人だと思うのです。
ですから、学校の中で、子供たちと熱中できる場を、ぜひ創り出し、共有していただきたいのです。
ワクワクしたりジーンとしたり……、心が熱くなる出来事がいっぱいの教室を、創っていただきたいのです。
イラスト/岡本かな子
■ ー 連載 鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」 ー 過去の回はこちら(↓)へ■
■ 第1回「わからなさがわかるかな?」
■ 第2回「し~っ! 先生には聞こえるよ!」
■ 第3回「答えは目の前の子供の中にあります」
■ 第4回「授業観・子供観を見直そう」
■ 第5回「子供ファーストの授業ってどんなもの?」
■ 第6回「授業の主役を明け渡す覚悟を『姿』で見せよう」
■ 第7回「互いに生かし・生かされていることを実感できる話合いを」
■ 第8回「今、全員が耳を傾けたよね! すごく気持ちよくない?」
■ 第9回 「授業は子供の素晴らしさに気付く時間です」