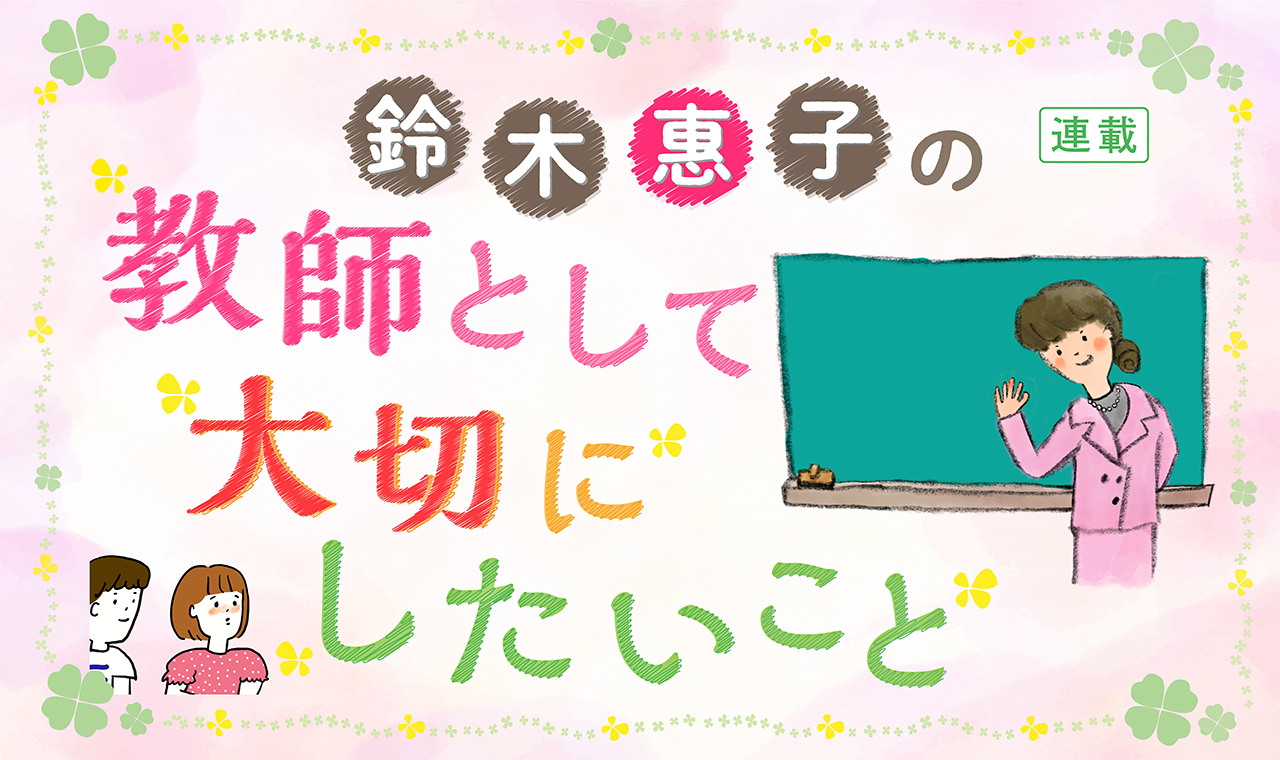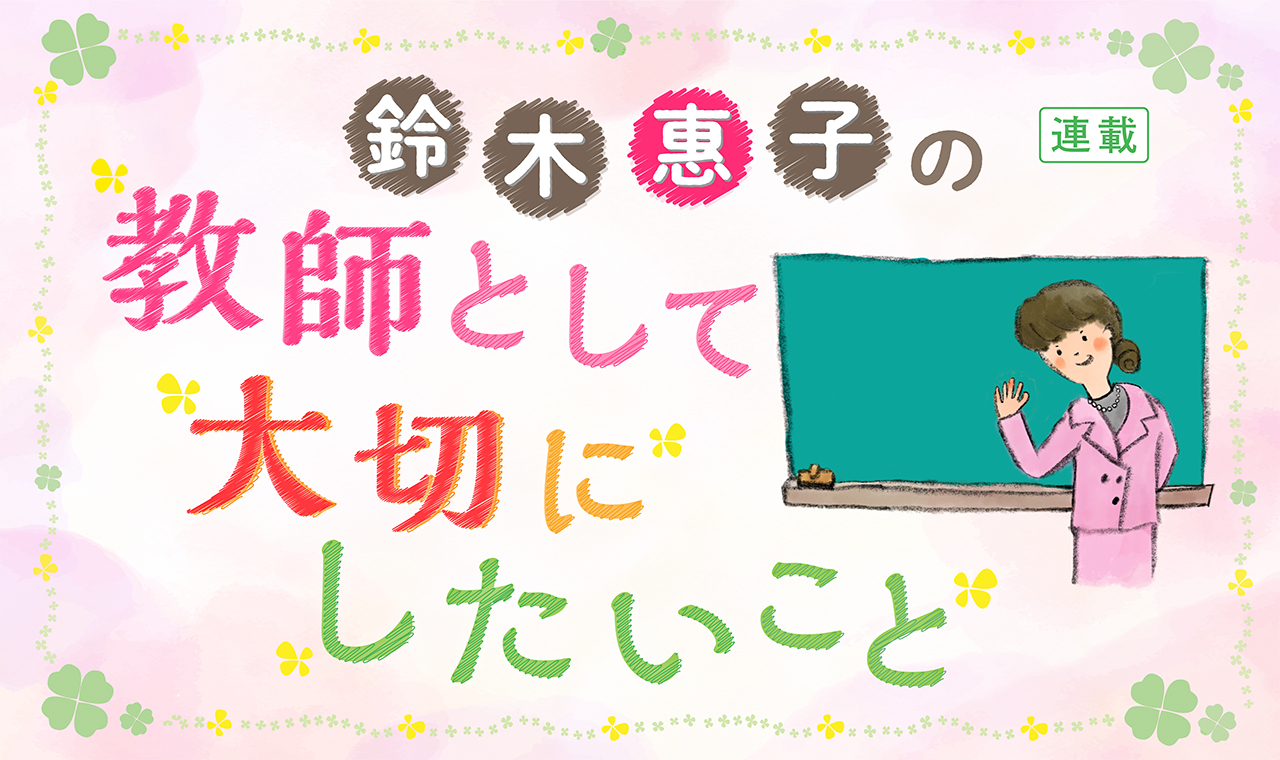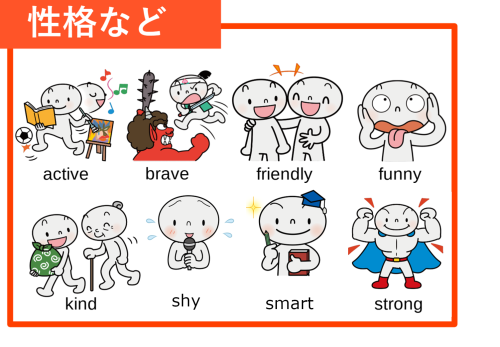鈴木惠子の「教師として大切にしたいこと」―連載第3回「答えは目の前の子供の中にあります」
関連タグ
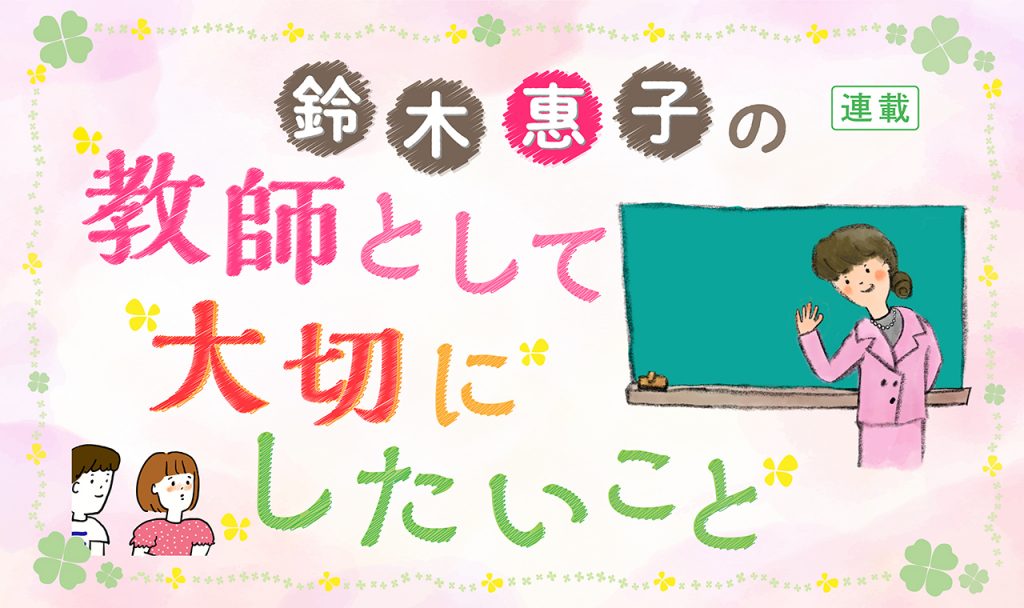
温かく、生き生きと学ぶ子供たちの姿に魅了され、かつてその後姿を追い求めた先生方が全国にいた鈴木惠子先生。子供が伸び伸びと自分を開示、表現していくその授業は、授業名人と称された故・有田和正先生から「日本一の授業」と評されました。変革期の現場で、本当に大切なことについて再確認するための連載、第3回をお届けします。

鈴木惠子(すずき・けいこ) 静岡県藤枝市の元公立小学校教諭。教育委員会指導主事、管理主事、小学校校長等を経て退職。好きなものは花と自然。
第3回 「答えは目の前の子供の中にあります」
前回は、「教師として大切にしたいこと」の一つ目、「共感力」についてお伝えするために、「聞こえませ~ん!」を例にお話ししました。
今回はその続きです。
イラスト/岡本かな子