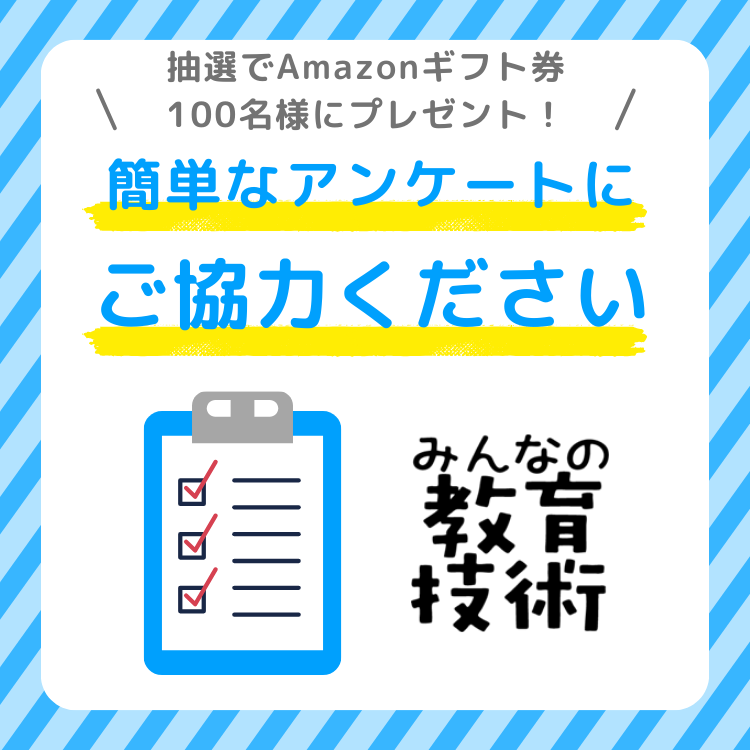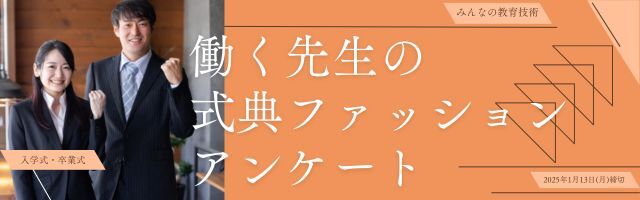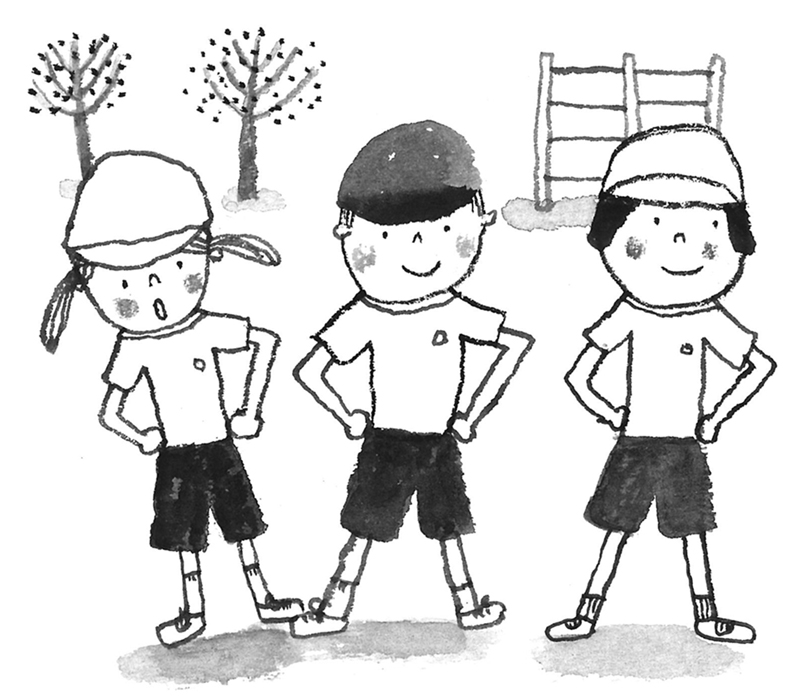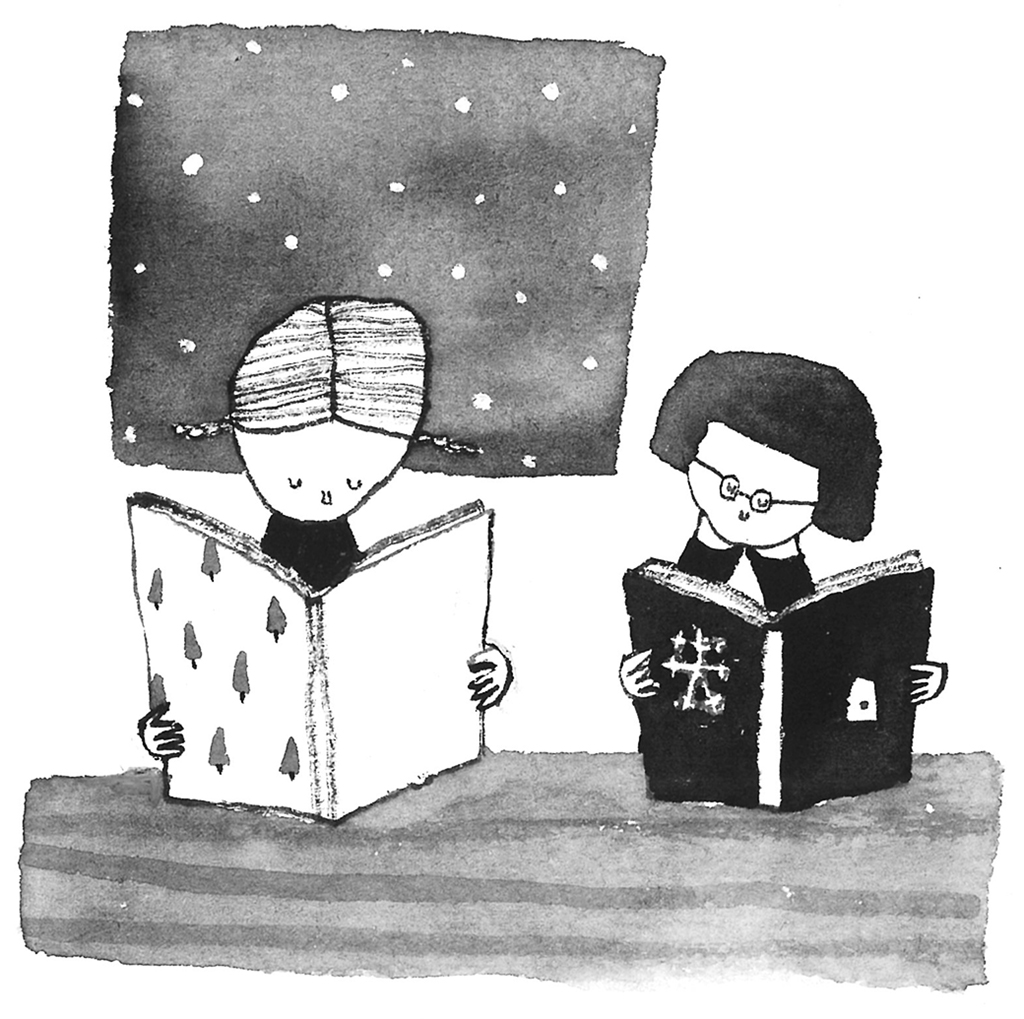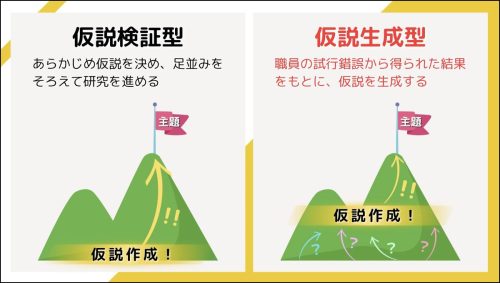「教育勅語」再考、再読のすすめ(下) ー「教育勅語」の真価ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第44回】

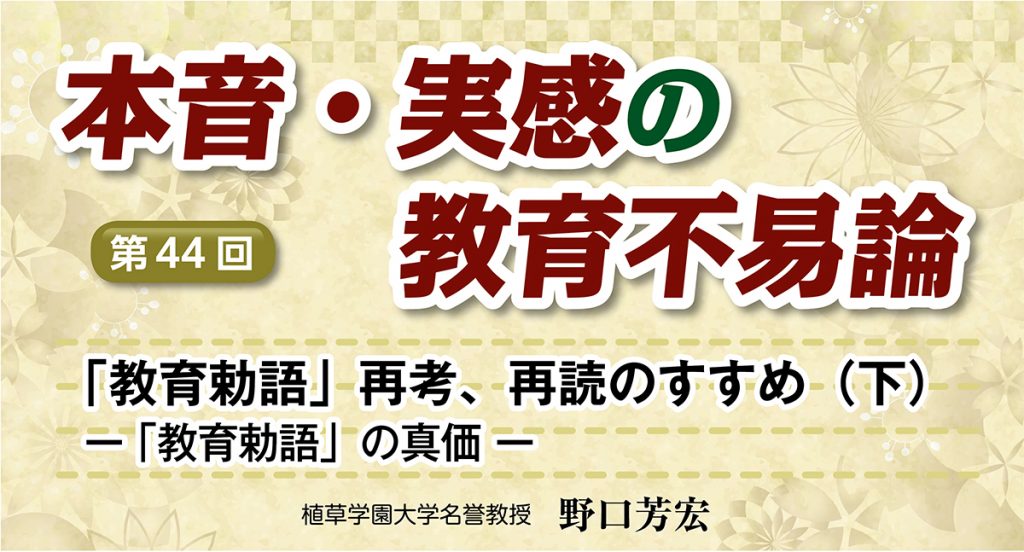
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第44回は、【「教育勅語」再考、再読のすすめ(下) ー「教育勅語」の真価ー】です。
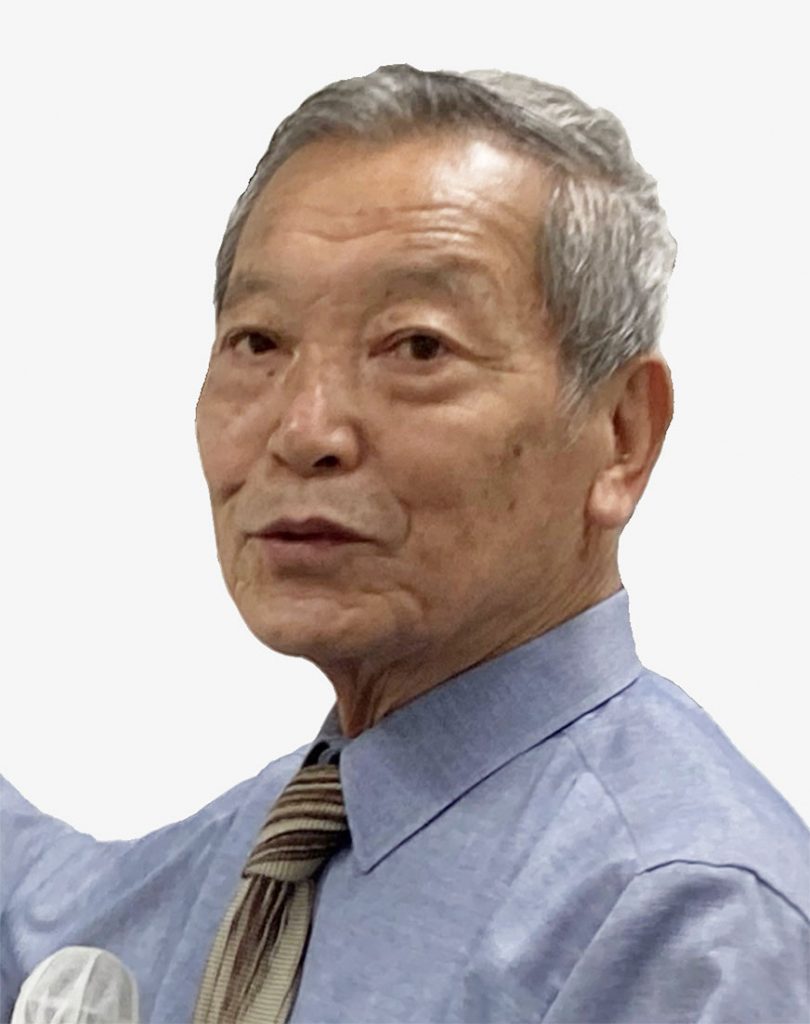
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
6 之ヲ古今ニ通シテ謬ラス(承前)
「教育勅語」の結びの文言を引いて拙訳を示したところで前号を終えた。それに若干の管見、解説を加えておきたい。
「斯(コ)ノ道ハ實ニ……古今ニ通シテ謬(アヤマ)ラス之ヲ中外ニ施シテ悖(モト)ラス」は、現代表記にしないとその意味が分かりにくい。
ちょっと話が外れるが、いわゆる「歴史的仮名遣い」では、現代口語の発音には合わないとして、昭和21年(1946)に内閣訓令で公布されたのが「現代仮名遣い」である。現代口語の発音に合わせた表記で分かり易くなり、便利になった。だが、結果的には歴史的仮名遣いによる文献が読めなくなるというマイナスも生んだ。それまでの大方の日本人は昔の日本の文献を難なく読めていたのである。「現代仮名遣い」への転換という言語政策の功罪は改めてどう評価すべきなのだろうか。
個人的、私的な考えでは「変えるべきではなかった」ということになる。昔の日本人は例外なく学校で旧仮名遣いを教わり、それを身につけていた事実があるからだ。それができなくなったというのは、国民的学力の低下を招いたとも言えるのではないか。
度々引いている格言だが重ねて引きたい。
好きか、嫌いかは自分が決める。
良いか、悪いかは社会が決める。
正しいか、正しくないかは歴史が決める。
子供の学歴よりも親の学歴の方が低いというのが一般的であったというある一時期があった。だが、その頃は、学歴の低い親の方がむしろ多くの漢字の読み書きができたし、古典も自由に読めたという皮肉な現象も見られた。国民的学力の総体は戦前に比べて戦後の方が向上したのだろうか。長い時を経てみないと、事の功罪、その真相は分からないものである。
閑話休題。「教育勅語」は、明治23年に発布され、昭和23年までの60年間日本国民の教育の根本指針として敬され続けて君臨した。
昭和23年6月19日、衆参両院において排除、失効の決議がなされ、現在に及ぶ。この決議はGHQの口頭による指示に基づくものであった。波乱万丈の歴史を辿った教育勅語である。戦後も75年を経た。「良いか、悪いかは社会が決める」というが、現在は排除、失効されたままだから「悪い」、「負の遺産」という受け止め方が広くなされていても不思議はない。
だが、「正しいか、正しくないか」は、「社会」ではなく「歴史が決める」のだと格言では述べている。改めてその正誤、当否を吟味してみることも必要ではないか。
以下は現代表記にして述べていきたい。天皇の名において「之を古今に通じて謬らず」と述べている事実に注目しよう。この真義は、「時代を超えて断じて誤りのない正しい考え方だ」ということである。また「日本だけでなく、世界のどこに示し、及ぼし、実践しても、理に逆らうようなことはない」との胸を張った宣言である。つまり、「教育勅語」の内容は、「真理、真実」を述べた文献である、ということなのだ。「真理、真実」は、「時空を超えて絶対に正しい、不動の理」ということである。ある時、ある日の「決議」によってその価値が消えるというようなことがあってはならないものだろう。敗戦下のあの時代の、あの場におけるあの「決議」は、「それ以外に道のない」避けられない事態、状況、措置であったのだ。その時代の「社会」は、「教育勅語」を「悪い」と言わざるを得ない「状況」下にあった行動なのだ。
改めて、「古今に通じて謬らず、中外に施して悖らず」という「斯の道」の中身を読んでみることにしよう。

7 此レ我カ國體ノ精華ニシテ
「これこそが、我が日本という国家の、最上、最高の真価なのだ」というその内実は何なのか。それが、「億兆心を一にして世々その美を済せる」こと、つまり、「日本国民の全てが心を一つにして代々その美徳を守り、実行してきたことだ」というのだ。では、「その美徳」つまり「精華」とは何か。ここが重要かつ重大な内容である。
それは「我が臣民克く忠に克く孝に」つまり、「我が国民が、困難に耐えつつ立派に忠義、孝行の実行、実践に」努めてきた事実、それが我が国の精華、真価、美徳なのだ、と勅語は説く。
「教育勅語」には、12の徳目が挙げられているが、それらの中核となる主徳、元徳がつまり「忠と孝」の二つなのである。12の徳目はいわばこの元徳「忠、孝」をさらに砕いて具体化したものと考えてよい。日本国民全てがこの二つの根本元徳については正しく理解し、守り、実行せねばならない、というのである。
絞りに絞ってこの二つを主徳、元徳と位置づけたことに私は深い感動を覚える。人によって、愛とか思いやりとか平和とかという言葉を選ぶだろう。そのように考えるのは自由である。だが、国民全ての共有すべき元徳を二つに絞るということは至難の課題である。それを「忠、孝」という二つに精選した判断には全く敬服する。この二つに勝る代案を出せと言われて誰が出せるか。おそらくそれは不可能に近い。
文句やけちをつけることは誰でもできるだろう。だが、よりすぐれて適切な「代案」となるとそれは至難、不可能に近かろう。
「忠」とは、「誠。真心。臣下たる本分を尽すこと」である。忠告、忠誠、忠義などの語がよくその本義を表している。
私は、忠の本質は「真心と秩序」にあると考えている。真心の対語には欺瞞が当たり、秩序の対語には無秩序、無法が当たりそうだ。「欺瞞と無法」では集団、社会、国家は成り立たない。「忠」こそが、団体や集団にとっては不可欠の元徳と言えよう。これに勝る「国家および社会」の徳はあるまい。見事な選択である。
「忠」は公的な徳目、公徳の核であるが「孝」はむしろ私的な徳目、私徳の核である。親のない子はいない。子を産み、育てるのが親である。親なくして子はなく、親なくして子は育たない。「生みの親より育ての親」という諺もある。が、それは例外、特殊な場合であって一般の論理とは別だ。
子にとって親に勝る恩人はなく、親に勝る存在はない。その親もやがて必ず老い、必ず衰えていく。親の有難さを深く理解し、親を尊び、重んじ、その恩に報いるのが「孝」であり、その行為が孝行である。明治になって来日した多くの外国人が日本人や社会を観察して異口同音に述べているのが、子供を慈しむ親、親を大事にする子供の姿の美しさである。「親孝行」は日本の美徳であった。正に「世々その美を済せる」ものであったのだ。敗戦によってこれらの美風は衰えた。その結果、日本は幸せになったとは言えまい。悲しく、残念なことだ。
「我が国体の精華」の美徳、美風をもう一度この国に取り戻したい。それが教育によってできたら、教育は大成功、勲一等だ。
このように考えてくると、我が国に長く根づいてきた「忠、孝」を元徳として「教育勅語」に位置づけ明記したことは本当に立派なこと、凄いことだったと感服する。それを「排除、失効」とした決議こそが「負の遺産」なのではないか。読者諸賢の考えを伺いたいところである。
8 一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ
勅語では「濁音」を用いず、全て「清音」で表記した。上の見出しは「一旦緩急(かんきゅう)あれば義勇公に奉じ」と音読する。また、この一節はしばしば「主権在君」「戦争賛美」「人権軽視」の思想の表れとして引用される文言だが、誤読である。
緩急とは、危急の場合、まさかの場合の意である。この緩は「語調を整える語」と『広辞苑』にある。納得。「国家に重大な危機が発生した場合には」ということで、一国を挙げて国を守らねばならない。その場合「義勇を奮って国家の為に尽さねばならない」のは当然のことだ。世界のどの国にとってもこの考え方は共通であり、共有されている考え方である。
義勇は「正義を愛する心から起きる勇気」「進んで公共に力を尽すこと」とある。義勇兵は、徴兵によらない志願兵であり、義勇軍は「有志の人民が自主的に組織した戦闘部隊」である。義勇は蛮勇とは全く別の大義に基づく勇気であり、正に「公に奉ずる」勇気である。国家の火急、緊急、大事に当たっては国民全てがこの気概を持つべきは当然のことであり、それは万国共通の国民道徳と言えよう。難癖をつける方がおかしいのだ。
これに続く「以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし」も、よく一部の人から指弾されるが、違う。「天壌無窮」というのは、「天にも地にも果てがないように長く、長く続いているところの」というほどの意味で、それは「皇運」「扶翼」にかかる修飾句である。ここで「皇運」といっているのは「皇室の運命」という意味ではない。「帝国」であった当時、「皇国」はそのまま「日本国家」を意味したし、「皇運」はそのまま「国運」つまり「国家の運命」と同意、同義なのだ。「扶翼」は「事が望ましく進むように助けること」であり、国家を危急の場から救うことである。これまた、世界共通の真っ当な考え方であって、疾(やま)しいことなど一点もない。
ここを「皇室の運命を助ける為に、勇気を出して命を捨てよ」ということだ、などと解するのは全くの的外れである。
9 「教育勅語」の再読、再考を
ある幼稚園で「教育勅語」を暗記させていたということが大げさに報道されたことがあった。「意味も分からないのに暗記させるなど無意味だ」という論調が多かったようだ。それへの論評は控えるが、子供への与え方の前に、教師自身の「再読、再考」をこそ重視したい。そもそも「教育勅語」は子供に与える為に作られたものではない。
国民に対して、日本の教育の根本的な在り方を訓し、その共有と実践を求めたものである。しかも、高い所から一方的に示した「命令、指示」などではない。
このことは、「教育勅語」最終の次の一文によって明らかである。
朕、汝臣民と共に拳拳服膺(ふくよう)して、皆其の徳を一にせんことを請い願う。
(現代的表記にした)
拙訳を示せば次のようである。
天皇は、国民諸賢と共にこれらの教えを慎んで胸底に深く刻み、その美徳を国民と一つになって実践していくことを心の底から切に願っている。
「朕、汝臣民と共に」とは、このような意味で示されたものに違いない。
子供に教えることを急ぐのではなく、まずは教師自身の「教育」に対する考え方をこの勅語から学びとることが先決なのだ。
十二徳のいちいちについて述べることはできなかったが、拙稿に記すことよりも、杉浦重剛先生の『教育勅語 昭和天皇の教科書』(勉誠出版)を拝読することの方がはるかに有益である。ぜひこの機会に一読をと切望して筆を置く。
執筆/野口芳宏 イラスト/すがわらけいこ
『総合教育技術』2020年12月号より