6月の学級通信文例:係活動への取り組みが学級の荒れを防ぐ

学級にも慣れ、子供たちの緊張が緩むとともに訪れるのが「6月危機」。「ギャングエイジ」と呼ばれる中学年の子供たちには、仲間の不適切な行動に流されてしまうような姿が多くみられるのではないでしょうか。
そこで今回は荒れがちな6月危機を乗り切る一例として、学級通信を使った取り組みを紹介したいと思います。
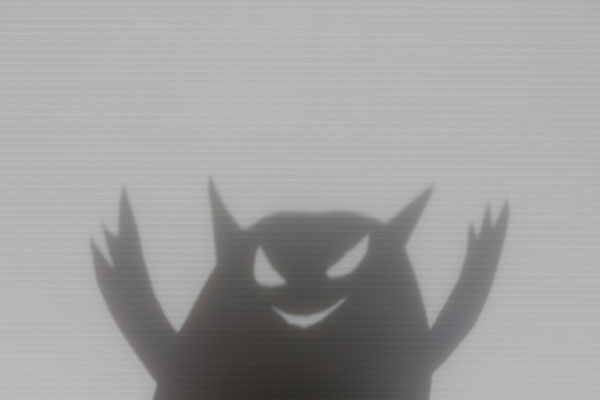
目次
「ギャングエイジ」の中学年児童
「6月危機」と称されるこの時期の教室では、子供たちの不適切な行動が増加する傾向にあります。特に「ギャングエイジ」と呼ばれる中学年の子供たちには、仲間の不適切な行動に流されてしまうような姿が多くみられるのではないでしょうか。
実際に、文部科学省のホームページに掲載されている「子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」には、このように明記されています。
集団の規則を理解して、集団活動に主体的に関与したり、遊びなどでは自分たちで決まりを作り、ルールを守るようになる。その一方、この時期は、ギャングエイジとも言われ、閉鎖的な子どもの仲間集団が発生し、付和雷同的な行動が見られる場合もある。
文部科学省「3.子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」 より抜粋
自我の芽生えにより「主体的」に行動することが増える一方で、人の意見をそのまま受け止めたくない、自分の意見を言いたいという思いも強くなります。親や教師の言うことが本当に正しいのかと疑問を持つようになったり、干渉されることに反発したりすることも増加します。
また子供の社会性にも変化が見られます。仲間を作り集団で行動をすることで、集団の中での役割や責任、ルールを守ることの大切さ、対人関係の築き方などを身に付けていきます。
集団を優先するあまり子供だけの集団で自分たちのルールに従って行動するものの、仲間たちの意見や行動に流されやすい「付和雷同的」な一面も見られるようです。
つまり、反発したり、仲間に流されてしまったりといった行動は、主体性や社会性が発達していく中で起こる成長過程の一つということができるでしょう。子供たちが成長していくエネルギーはとても大きく、この発達を無理に抑え込むことはできません。

