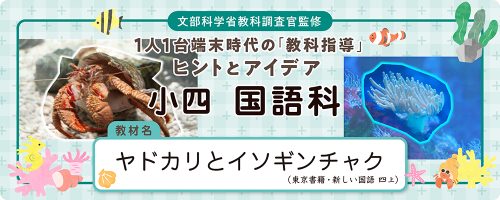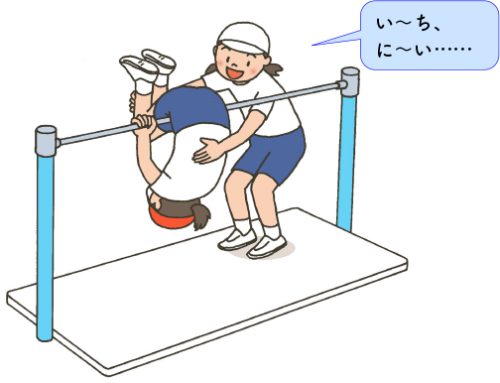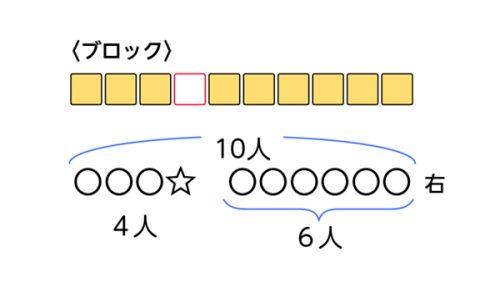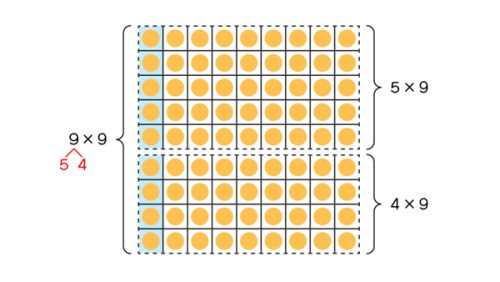小2生活「おいしくなあれ! ぼく・わたしの野菜」指導アイデア
執筆/愛知県公立小学校教諭・朝倉有利子
編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤 智、愛知県公立小学校校長・稲田あけみ
目次
期待する子供の姿
知識及び技能の基礎
野菜を栽培する活動を通して、野菜が生命をもっていることや成長していることに気付く。
思考力、判断力、表現力等の基礎
野菜を栽培する活動を通して、それぞれの野菜の成長の様子や世話の方法に関心をもって働きかけることができる。
学びに向かう力、人間性等
野菜を栽培する活動を通して、野菜への親しみをもち、大切に育てようとする。

単元の流れ(16時間)
単元に入る前に、野菜を料理したり食べたりした絵日記や作文を取り上げ、栽培への意欲を高めておきます。
一年生では、どんな植物を育てましたか。
アサガオを育てました。毎日、お世話をして、花が咲いたときうれしかったな。
二年生では、野菜を育ててみたいな。
学習の流れ
どんな野菜を育てようかな(2時間)
ナスが育てやすいって、おばあちゃんが言ってたよ。
甘いミニトマトを育てて、トマトが好きなお母さんに食べてもらいたいな。
【評価規準等】
思 野菜の特徴を本で調べたり、親しい人に聞いたりして、育ててみたい野菜を選んだり決めたりしている。
※評価規準等:知=知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点、を示しています。
こんにちは、私の苗ちゃん(2時間)

野菜名人「上手に植えたね」
【評価規準等】
態 大切に育てたいという思いをもって、植木鉢に土を入れたり、苗を植えたりしている。
苗ちゃんの世話をしよう(6時間)
葉っぱは、トマトのにおいがするよ。
これで安心。ぐんぐん伸びるかな。
【評価規準等】
知 野菜にも自分と同じ生命があり、成長していることに気付いている。
大変だ!苗ちゃんを助けよう(2時間)
私の葉っぱは、虫がいっぱい。どうしよう。
僕の葉っぱは穴が開いちゃった。野菜名人に聞いてみようよ。

【評価規準等】
思 困ったことを友達と相談したり、野菜名人に聞いたりして、野菜の立場に立って世話の方法を見直している。
野菜を収穫しよう(2時間)
このキュウリは、お母さんにプレゼントしよう。
たくさん採れたから、みんなで食べたいね。
どの野菜も、とっても大きく育ったね。
【評価規準等】
態 自分が育てた野菜に親しみや愛着をもったり、収穫の喜びを味わったりしている。
野菜アルバムを作ろう(2時間)
トマトがいっぱいできて、うれしかったな。
収穫できたのは、がんばって育てたからだね。
【評価規準等】
知 野菜の世話が上手にできるようになった自分自身の成長に気付いている。
活動のポイント1 栽培活動への意欲が継続する工夫をしましょう。
繰り返し関われる場所
栽培場所は、身近な場所にしましょう。例えば、登校時に通る通路沿いに植木鉢を置いたり、教室から見える花壇に植えたりすれば、ちょっとした変化に気付きやすく、自然と関わりも増えます。

観察カードなどの掲示
観察は、成長の様子を絵に描いたり、写真に撮ったりする方法以外にも、茎やつるの長さを記録することもおすすめです。観察時に紙テープを何本か用意しておき、茎やつると同じ長さに切って観察カードと一緒に掲示します。毎回伸びていく記録を見て、子供たちは観察が楽しみになります。
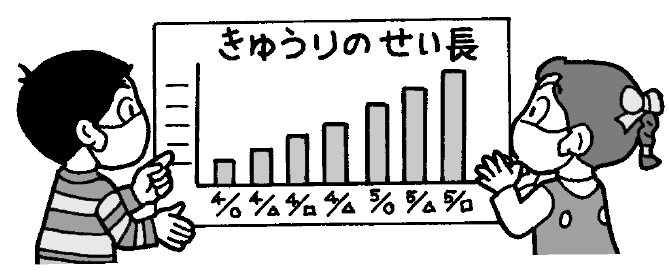
活動のポイント2 さまざまな人との関わりがもてる活動にしましょう。
イラスト/高橋正輝、横井智美
『教育技術 小一小二』2021年4/5月号より