学年通信・学級通信の書き方は適切ですか?

学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。
文/稲垣孝章(元・埼玉県公立小学校校長)
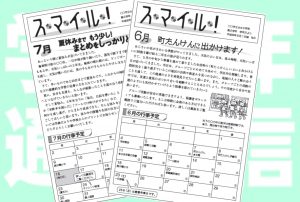
目次
文章表現に気をつけていますか
教職3年目の教師が作成した学年だよりが、起案形式の閲覧で回ってきました。
「新年に向けて、各御家庭でお子さんと一緒に、絵の具や習字の墨汁等で不足している学用品があれば補充しておきましょう。」
この表現に問題はないように感じるかもしれません。意外にこのような表現が多く見られるのが現状です。
しかし、文末に不自然さはないでしょうか。
学年だよりは、保護者向けに作成するものです。したがって「~しておきましょう。」ではなく「~しておいてください。」という依頼の文章表現となります。この場合は、子ども向けに書く文章と保護者向けに書く文章が混在してしまっているのです。もし、子ども向けの文章も入れるのであれば、枠囲み等を活用して地の文と異なるように工夫したいものです。
学級通信の掲載事項は配慮しているか
中堅の情熱あふれる先生の学級通信に次のような記載がありました。
「今回の全校児童集会での学級自慢発表会を大成功に導いてくれた代表委員のAさんの活躍は見事でした。全校児童からも大きな拍手が送られました。」
この文面だけでは何の問題も見つかりません。しかし、この学級通信を発行後に、ある保護者から次のような手紙が届けられたそうです。
「先生は、熱心で、毎週学級通信を出してくださり、感謝しています。しかし、頑張っている子を掲載するのはよいのですが、残念なことにそれは、いつも一部の子になっているように感じます。」
この手紙をもらった先生は、どの子も偏ることなく学級通信に掲載することの大切さを痛感したと語っていました。学級内では、どの子も大切な集団の一員であり、どの子も大切な役割を担って活躍していることを、教師は常に念頭に置いておくことが基盤となります。

