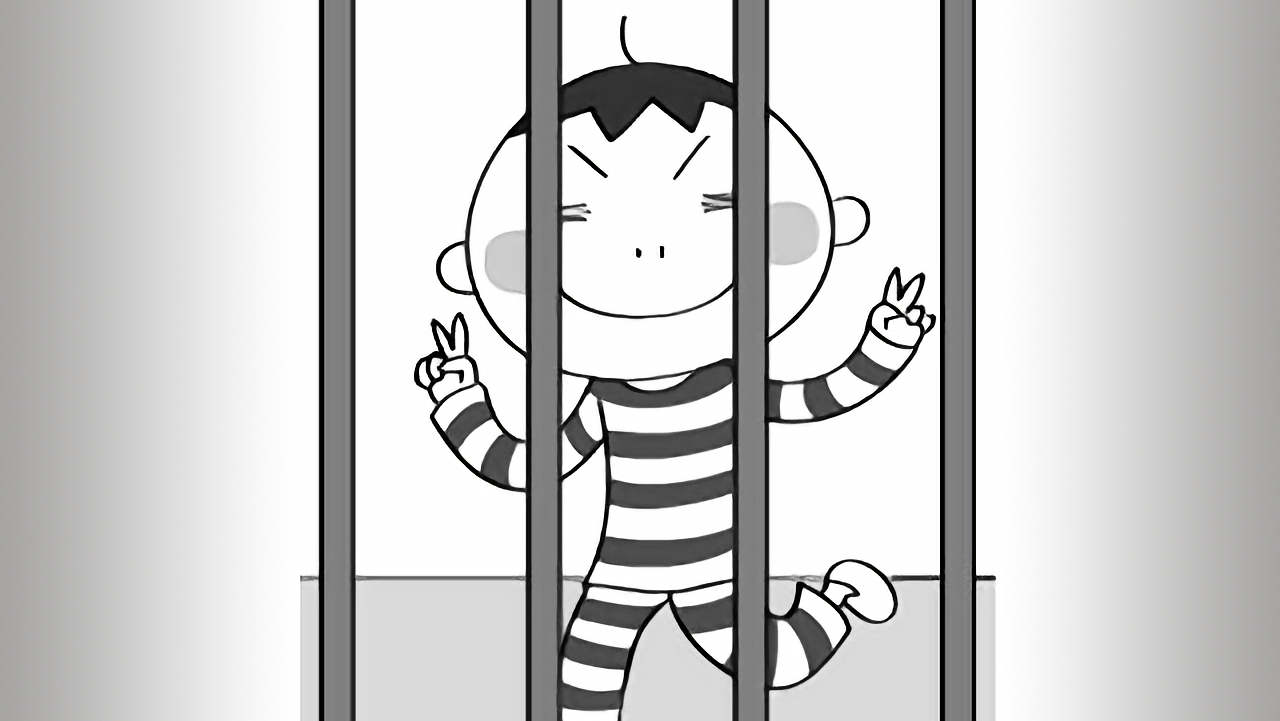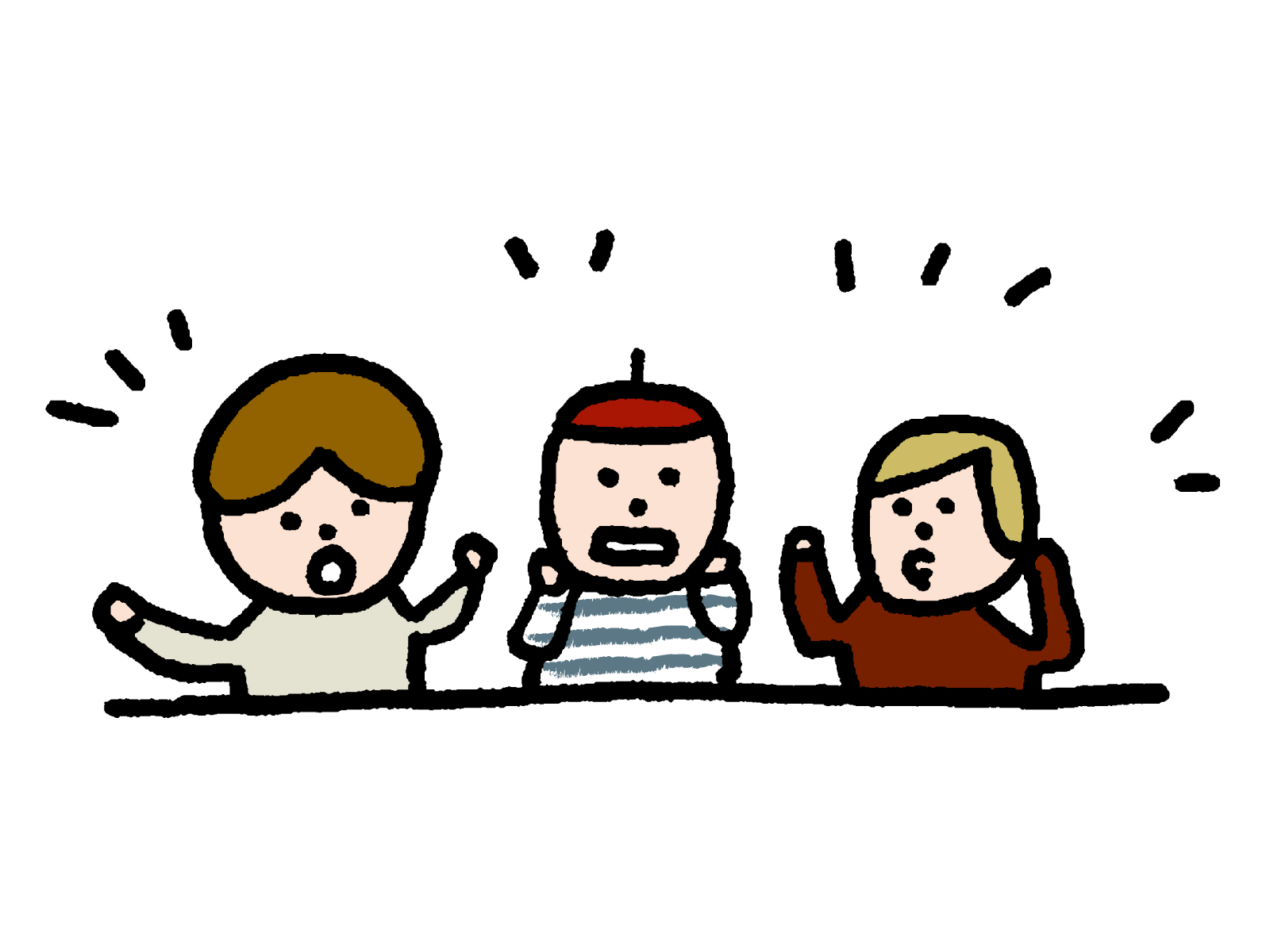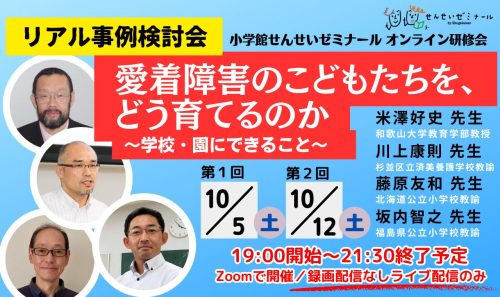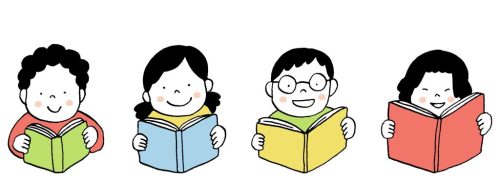通信簿を渡すときの言葉がけ、ちょっとした気遣いで変わります

学級経営・特別活動を長年、研究・実践してきた稲垣孝章先生が、教育現場で見て気になったことについて、ズバリと切り込みます。
文・稲垣孝章(元・埼玉県公立小学校校長)
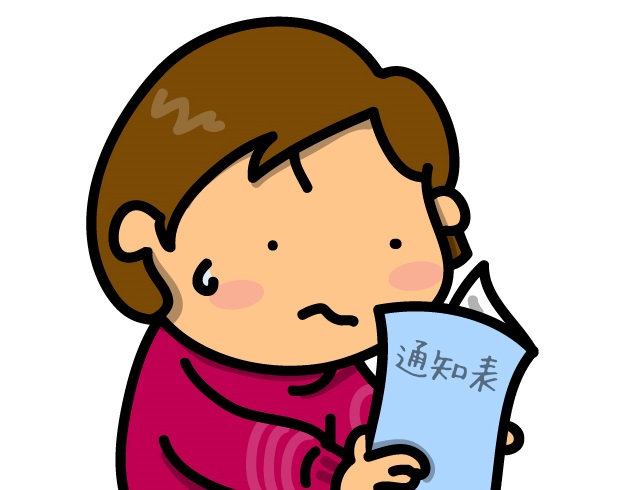
目次
どちらの方が印象に残る?
次の二つは、同じ内容のことを伝えています。しかし、その伝わり方はどうでしょうか。
①「この問題は難しいけれど、あなたなら大丈夫」
②「あなたなら大丈夫だけど、この問題は難しい」
①②ともに同じ内容のことを伝えていますが、言葉の遣い方の順序を入れ替えると、聞いている人には同じようには受け取れないようです。実は、後で言われた言葉の方が心に残りやすい(残存効果)ということがあるのです。
通信簿を渡す時の教師の言葉がけ、また保護者が家で通信簿を見た時に子どもに語りかける言葉がけ等、ちょっとした言葉の遣い方の順序を入れ替えてみると、子どもの受け止め方も変わってくるのです
通信簿を手渡す時は?
初任者研修中の新採用教員が学期末に通信簿を手渡している場面をみました。
子ども一人ひとりを順番に教卓に呼び、「○○さん、よくがんばったね」とひとこと言葉を添えて通信簿を手渡しています。さて、このことについて、どのように考えますか。
決して間違っているということではありません。しかし、望まれる手渡し方は、少し違います。
「通信簿の仕上げは言葉がけ」という名言があります。可能なら、教師のそばに一人ひとりの子どもを呼び、脇に座らせて、「今学期、どこをどのように頑張ったことがよかったのか、そして来学期には何を期待しているのか」等について具体的に言葉をかけることが求められます。その時間、他の子どもへの指示としては、読書や作文等が考えられますが、子どもから「担任 への通信簿」と題して手紙を書かせることも効果的です。

課題のある子の所見は?
「集中して授業に臨むことが課題です」「忘れ物が多く、…」と所見欄に書きたくなる子が存在するのが現状だと思います。
しかし、その子なりのよさを見取るという観点から、現実的には通信簿にこのような所見を書くことは望ましくありません。
例えば「集中して授業に臨む態度がみられるようになり、本来の力が…」「忘れ物を解消しようとする姿勢がみられるようになり、学習意欲も…」などと、課題を踏まえつつも成長の様子を記載していくようにすると、肯定的な所見になります。
『小一~小六教育技術』2014年4月号~2016年2/3月号連載「正襟危座--伝えたい--耳に痛いかもしれないけれど、教室で大切な基礎基本」より