研究紀要は廃止も含め検討を!改善チェックリスト

「研究授業が終われば、学校研究が終わるかというと、そうではありません。研究授業以上に大変なのが、研究冊子づくり。でも、それは教職員の本来業務かどうか、今一度立ち止まって考えてほしい」と鈴木夏來先生は言います。
廃止、あるいは電子化などの改善をすることで働き方改革に大きく寄与すると言われる「研究紀要」についての提案です。
執筆/神奈川県立総合教育センター主幹兼指導主事・鈴木夏來
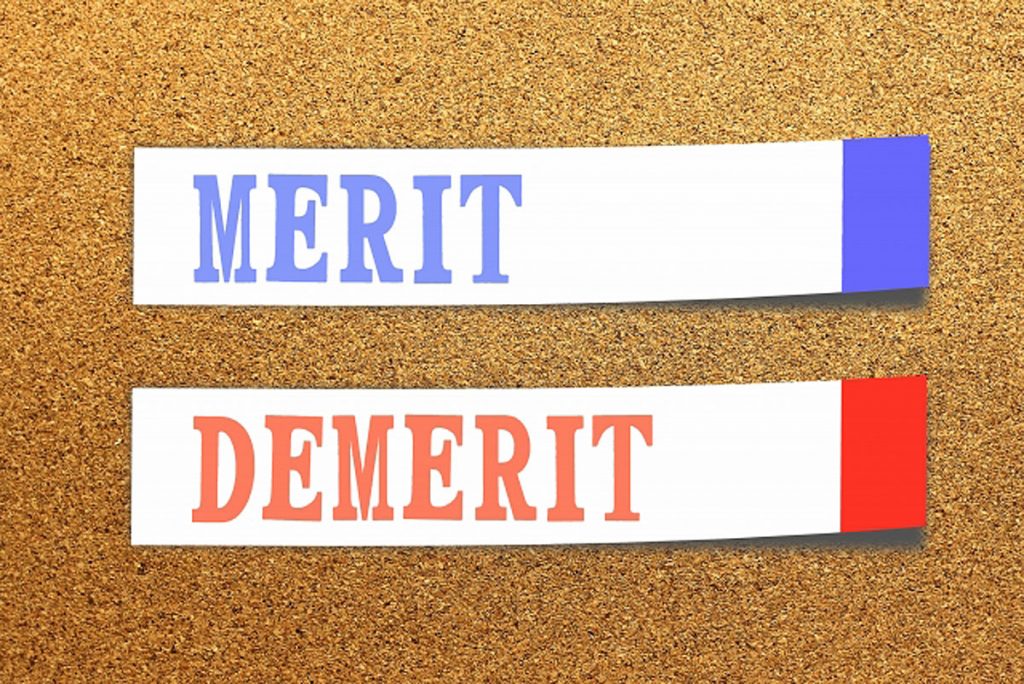
目次
長期休みの間も学校にいる現実
研究チームの一員になると、それはもう、たくさんの業務が待っています。
「通知表の所見が終わったからラクになった? いやいや。この時期から研究紀要を作り始めないと、もう間に合わないんです・・・」
「冬休み中も、ほとんど学校ですよ。指導案の直しとチェック、それに研究成果を書かねばなりません。ほかの先生方が来る仕事始めまでに、ある程度、仕上げないと」
という声が聞こえて来ます。しかし、それは教職員の本来の業務でしょうか。
研究紀要の発行は義務ではない
各学校が1年間の校内研究の成果をまとめた冊子を「研究紀要」と言います。 ほかにも、「研究集録」「研修収録」「研究のまとめ」「○小の研究」など様々な呼称があります。ここではいずれも「研究紀要」と呼ぶことにします。
研究紀要は本来、大学や教育研究所などの専門機関の研究施設が作成するものです。
大学や研究所が研究を行い、その成果を「研究紀要」という形でまとめるのは当然のことでしょう。大学の附属小学校等であれば、それは本業ですからやむを得ないことなのかもしれません。
しかし、通常の学校が同じことをする必要があるのでしょうか。
私たち教職員は、大学や研究所の研究員でもなければ、出版社の編集スタッフでもないのです。
「そうは言っても、うちの学校は研究委託を受けている。だから研究成果を冊子という形に残さねばならない」
そう考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、実際の委託元は、そう考えているのでしょうか。
もちろん、報告書等が必要であれば、最低限は書かなければならないかもしれませんが、研究冊子の作成そのものに予算を付けていなければ、そもそも作成する必要はないのです。
冊子を作成するとなると、原稿のチェックや丁合等に甚大な時間がかかります。それは学校の教職員の本来の業務ではありません。そのことを国や教育委員会もよく知っています。
働き方改革を進め、学校現場の負担を軽減しなければならないと考えていますから、「研究紀要を冊子で作って出してくれ」などとは言えません。
ところが、私の経験上、学校現場は次のように考えることがあります。
実際には不要なのに、つい学校が考えてしまうこと(例)
- 委託を受けた以上、形に残さねばならない
- 研究紀要は、電子媒体ではなく、紙媒体の冊子にして出さないと失礼だ
- 教育長、教育委員、指導をしてくださった指導主事をはじめ関係諸機関に渡すべき
- 渡す場合は、美しく製本されたものを選んでお渡しすべき
- 万が一、乱丁落丁や誤字脱字が見つかったら、差し替えたものをお渡しすべき
- 学校逓送よりも郵送、郵送よりも手渡しのほうがよい
- 手渡しならば、できれば研究主任、いや管理職、できれば学校長が直接渡すべき
- 研究紀要には、学校長の決裁が必要な、丁寧な挨拶文を添えるべき
しかし、私の知る限り、県や市町村の教育委員会は、そうしたことを求めていません。
学校研究が学校教育目標の具現化につながること、子どもたちのためになること、先生方の力量向上につながることを、県や市町村の教育委員会は、心から願っているはずです。
研究紀要の作成が目的化し、学校現場の教職員が疲弊するようなことは、あってはならないと考えています。

