新型コロナの教え方:休校明けの子供の不安はこう取り除く
世界的な疾病禍により、かつてない長期休業に入らざるを得なかった学校が少なくありません。特殊な状況下で新年度を迎えた学級が、落ち着いて学習に入っていくためには、どのような配慮が必要でしょうか。日本学校心理学会常任理事で子育て支援・リソースポート代表の半田一郎さんに話を聞きました。
半田一郎(はんだ・いちろう)1969年、高知県生まれ。日本学校心理学会常任理事、公認心理師、臨床心理士。茨城県公認心理師協会副会長であり、同県内の小・中・高等学校でスクールカウンセラーとして活動。子育て支援・リソースポート代表として保護者や子供の支援にも当たる。

目次
学校再開によって子供たちの日常が回復する
子供たちへの配慮を考えるためには、まず、この災害の特性を知ることが重要です。
例えば、震災や台風などの災害は、ある時点で災害が起きて、その後も大変な状況があるにせよ、支援が入り、日常が戻ってくる回復のプロセスが目に見えます。
それに対し、今回のコロナウイルス禍は、長期間の災害が継続している状況です。先の災害例とは異なり、現在進行形の不安に直面しているという、今までにないタイプの災害なのです。
しかも、地震や台風などは災害の影響が具体的に目に見えるのですが、ウイルスは正体が見えず、被害の状況も見えにくいため、余計に不安が大きくなってしまいます。
加えて休校中、ずっと家で過ごしたことや学童などで学校に来ていたとしても、普段と違う状況になっていたことなどが子供たちのストレスにつながっています。
とはいえ、現実にこの問題がどの程度続くかは置いたうえで、まずは学校再開によって子供たちの日常が回復するということが、安心につながっていくのです。
コロナウイルスについて分かりやすく話す
学校、学級の再開に当たっては、まず子供たちにとって身近な担任の先生が、今の状況やこのウイルスについて、子供たちに分かる言葉で話していくことがとても大事です。それが子供たちの安心につながります。
こう言うと、「医学関係のことは分からないので…」と考える先生もいると思います。
もちろん、知らないことを無理に語る必要はなく、分からないことは「分からない」と伝えるのでよいのです。
それにネット上には、公的医療機関や心理学の専門家などが、子供たちに向けて多様な資料を公開しています(資料参照)。
資料「新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!」(日本赤十字社)より抜粋
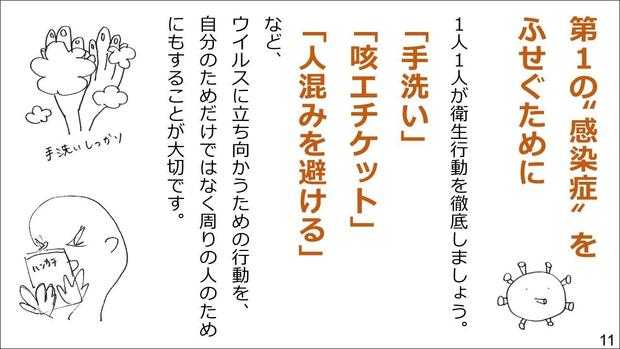
日本赤十字社「新型コロナウイルスの 3つの顔を知ろう!」
そうしたものも活用しながら、保健の先生を中心にして、学校全体でスクールカウンセラーなどとも打ち合わせ、分かりやすく話をしてあげることが大事です。
ただし、話をするときに気を付けたいのは、命令や否定口調で話さないということです。
例えば手洗いについて、「手洗いをしないとダメだよ。コロナウイルスにかかっちゃうよ」と、つい言ってしまうかもしれません。もしそんな口調で叱られた子がいると、「あいつはコロナだ」といじめの対象になる危険が出てきます。
そうではなく、「手洗いをするとコロナをやっつけられるよ」と、プラスの方向性で話をしてあげることが大切です。


