昭和100年…覚悟の年 ~「二項対立」と「とはいえ…」を乗り越えて~【連載|管理職を楽しもう #12】
- 連載
- 管理職を楽しもう

前例踏襲や同調圧力が大嫌いな個性派パイセン、元小樽市立朝里中学校校長の森万喜子先生に管理職の楽しみ方を教えていただくこの連載。いま管理職の先生も、今後目指すかもしれない先生も、自分だったらどんなふうに「理想の学校」をつくるのか、想像しながら読んでみてくださいね。 第12回は、<昭和100年…覚悟の年~「二項対立」と「とはいえ…」を乗り越えて~>です。
執筆/元小樽市立朝里中学校校長・森 万喜子
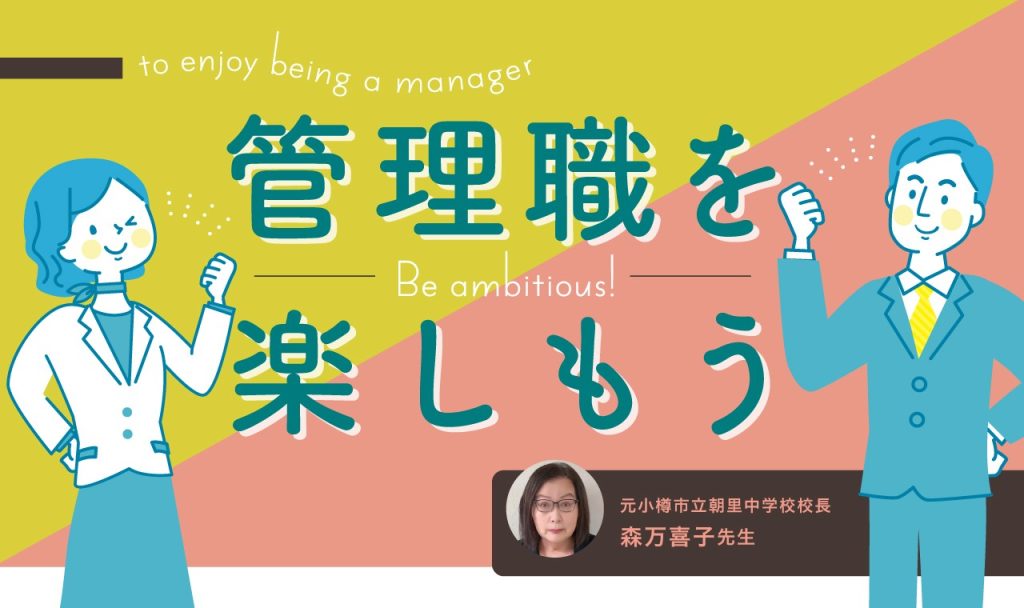
目次
新年が明けました。
皆さん、穏やかに新年を迎えられたでしょうか。昨年、2024年は、元日から能登半島を中心とした震災が起き、翌日は羽田での航空機事故、世界でも戦争や紛争、自然災害が起き、特に子どもや若い人が被害に遭う事件や事故など、心が痛む思いが多くありました。
令和7年は十干十二支(じっかんじゅうにし)という古来の暦法で「乙巳(きのとみ)」とされ、これまでの努力や準備が実を結び始める時期を示しているそうです。巳(み)は蛇ですが、神聖な生き物。たくましい生命力をもち、脱皮で再生を繰り返し金運上昇の縁起物とされています。新しい時代に、それぞれのペースで前進していく変化の年と期待されているようです。歴史上でも、大化の改新、壇ノ浦の戦い、東京オリンピック翌年の経済成長など、大きな変化の年であることが多かったようです。そう考えると、今年1年をどうするか、ぼんやりしてはいられませんね。
教育の振り子はなぜ大きく振れるの?
また、今年2025年は昭和でいうとちょうど100年。自分が生まれ育った時代が、若い人たちからすると大昔になっていることに驚きつつ、世の中が変わったことは肌感覚で、実によく分かるのです。自分が小学生のときはSFの世界だったものが、実生活に当たり前のように存在しています。でも、生活は便利になったけど、生きやすくなったとは言えないみたいで、不登校児童生徒数が34万人を突破しました。もう、過去の価値観の学校のままでは、もたない。だけど、学校というところは、なかなか変われないのが悩ましい。変えることがこれまで積み上げてきた学校文化を否定することになるから不安だという人がいます。変えて失敗したらどうしよう、という恐れもある。だけど、魔法の杖も特効薬もないのなら、丁寧に議論し、仕組みを考え、やってみるしかないんです。
一歩踏み出すと新しい学びの世界と可能性が広がるはずなのに、なぜか変えてみて課題が見えると、その課題を解決するために試行錯誤するよりは、以前のやり方や考え方に戻そうとする力が働きやすくなっているように感じます。
デジタルかアナログか、子どもたちに委ねるのか、教師主導で教えるのか、個別か集団か、とかくAかBかの二項対立に議論が落とし込まれることが多くなりがちですが、もうそんなことに解決策を見いだすことは難しいということに、誰もが気づいているはずです。大きく振れる振り子の下で、戸惑うのは子どもたち。どちらかしか選べない時代じゃない。子どもたちの前にはたくさんの選択肢と、自己決定と失敗が許される寛容さを用意したいのです。

