提言|住田昌治 校長がすべきこと、すべきでないことは? 【緊急検証! 教員のなり手不足問題、私はこう考える! #6】
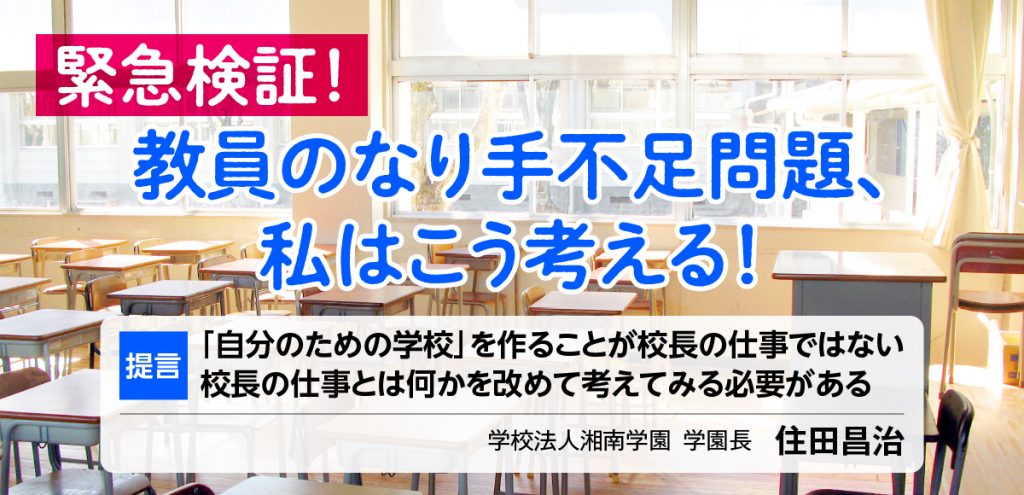
教員のなり手不足問題は深刻であり、日本の学校にとってその解決が目下の急務です。現在、文部科学省が進めている働き方改革や給特法に関する議論は確かに重要ではありますが、果たしてそれだけで解決となるでしょうか。教育関係者がその他にできること、するべきことは何かを考える7回シリーズの第6回目です。今回は、校長がすべきこと、すべきでないことに注目します。横浜市での副校長、校長時代に、元気な学校づくりを行ってきたことで知られる住田昌治さんに話を聞きました。

住田昌治(すみた・まさはる)
1958年京都生まれ、島根育ち。玉川大学卒業後、横浜市の小学校に7校42年勤務し、その間、副校長を3年、校長を12年勤める。2022年度より現職。副校長、校長時代にユネスコスクール、ESDに取り組み、元気な学校づくりで注目されるようになり、「カラフルな学校づくり」(学文社、2019)出版後は、全国から講演依頼や原稿執筆依頼が相次ぎ、型破りな校長として全国を飛び回る日々を送る。著書に「『任せる』マネジメント」(学陽書房、2021)、「若手が育つ指示ゼロ学校づくり」(明治図書出版、2022)、「できるミドルリーダーの育て方」(学陽書房、2022)、「校長先生、幸せですか?」(教育開発研究所、2023)などがある。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|玉置崇 大学、教育委員会、学校が今、すべきことは?
●提言|川上康則 学校や教員が、今すぐ考えたい5つのこと
●提言|赤坂真二 大学と学校は今、何を変える必要があるのか
●提言|田中博之 授業に関する業務をスリム化するには?
●提言|専門家が指摘! 学校の同調圧力を弱くすることが重要
●提言|住田昌治 校長がすべきこと、すべきでないことは?(本記事)
目次
残念な校長にありがちなことは?
教員のなり手不足問題の原因の一つとして、校長の存在があります。多くの校長先生はやるべきことをやっておられますが、一部の残念な校長先生がブラックな学校をつくり、ブラックを広めているからです。
先日、管理職向けのセミナーで参加者から質問を募ったところ、「私にはやりたいことがあるのに、教職員が動いてくれないのです。どうすればいいでしょう?」という質問が来ました。
この校長先生のやりたいことが何かはわかりませんが、少なくとも教職員から賛同を得られないことを進めようとしているわけです。
校長がやりたいことを始めると、教職員はそれに巻き込まれます。ただでさえ忙しいのに、やりたくなくてもやらざるを得ない状況になるのです。口では「働き方改革を進める」といいながら、その一方で、「やらされ感」のある仕事を増やしている校長もいます。
例えば、教科等で活躍した校長で、その教科等の研究会の会長になったような人は、自分の学校を、その教科等の研究校にしてしまうのです。そうすると、その教科等の授業がしっかりできない教員は許せないわけです。「○○科の授業はそんなもんじゃない。もっと教材研究をしてこい」と徹底的に鍛えます。それにより、確かに○○科の指導技術は身に付くかもしれませんが、その学校のすべての教員が、○○科の専門家になりたいわけではありません。しかし、○○科の授業がうまくできる教員が高く評価され、○○科の授業に一生懸命取り組む教員が可愛がられますから、教員たちも忖度して取り組みます。そうやって、○○科の研究発表会をするために1年間を過ごし、研究発表会の参加者が何人だったかがその校長の評価になります。要するに、○○科の授業がよくできる教員、○○科がよくできる子どもが育つ学校になっていれば、その校長は満足なのです。
ここで考えてみてほしいのは、校長は何をする人なのか、ということです。少なくとも、自分のやりたいことをやるのが校長の仕事ではありません。学校には学校教育目標があります。その目標を達成するために、教職員みんなで力を合わせて教育活動を行えるように、マネジメントをするのが校長の役目です。その際に、学校に教職員が何十人かいたら、その一人一人に自分のやりたいことがあるはずですから、それらを引き出し、やりたいことが実現できるように後押ししていく必要があります。
それから、教職員が育つようにすることも校長の役目です。何かあるたびに「どうすればいいんですか」と、いちいち校長に聞きにくる教職員ではなく、自分で考えて、動けるような教職員に育つような環境を作らなければなりません。
厳しいことをいうようですが、校長になったら、自分が研究してきたことは手放さなければいけないと思います。そういう心構えや覚悟を持って校長にならないと、教職員を疲弊させ、「校長自身のための学校」をつくってしまう可能性があるからです。
では、校長の幸せは何かといったら、子どもが育つことです。それと同時に、教職員が育ち、校長がいなくても教職員たちだけで学校づくりができるようになることが、校長としての自分の成果なのだと、発想の転換を図る必要があります。
校長がすべきことは、心理的安全性のある組織づくり
教員のなり手不足の原因として、「学校はブラックな職場」というイメージもあります。そのイメージを変えるために、校長がすべきことは、心理的安全性のある組織づくりです。みんなが安心してものが言えて、自分のやりたいことができ、自分らしさを発揮できる、そういう学校づくりを進めていくのです。
そのためには、教職員が話しやすくなるように、校長はファシリテーション能力を身に付ける必要があります。教職員の意見を丁寧に聞き、拾い上げていくことを通して、教職員が自分たちの学校を自分たちで作っていく、そういう当事者意識を持って学校づくりに参画していくことが重要なのです。それにより、風通しがいい学校、自分たちの働きやすい学校になっていきます。教職員自身が自走して、自分たちでどんどん動くことによって学校が活性化していきますから、ブラックではなくて、お互いの個性を認め合うカラフルな学校になっていくわけです。
国が今まで求めてきたのは、働き方改革などを「校長の強いリーダーシップで実現する」ことでした。そうやって校長の権限を強めていった結果、教職員の意見を全然聞かないで強引に学校改革を進めたり、怒鳴ったり、機嫌を悪くしたり、パワハラをしたりする校長が出てきたわけです。
なぜこうなったのかというと、国はリーダーシップを学んでいない人たちに、「 リーダーシップを発揮しろ」と言ってしまったからではないでしょうか。「やらなければならない」と強く感じた校長の中には、権限が強くなったことで、単純に命令して「やらせる」方向へと進んでしまった人もいるのだと思います。例えば、先述の自分のやりたいことをやる校長たちは、教科の指導力はありますが、リーダーシップやマネジメント力、ファシリテーション能力には関心が薄いのかもしれません。
国も「強いリーダーシップで」と言っているだけでは、学校経営や「働き方改革」などがうまくいかないことに気づき、管理職にはマネジメントや、ファシリテーション能力・アセスメント能力などが必要だと、2022年あたりから言い始めています。いまさらという気もしますが、これから幸せな校長を量産していくためには、校長がリーダーシップのあり方や、マネジメントやファシリテーション能力・アセスメント能力などを学べる機会をつくる必要があると思います。

