公立小学校における「自由進度学習」への挑戦【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画 #03】
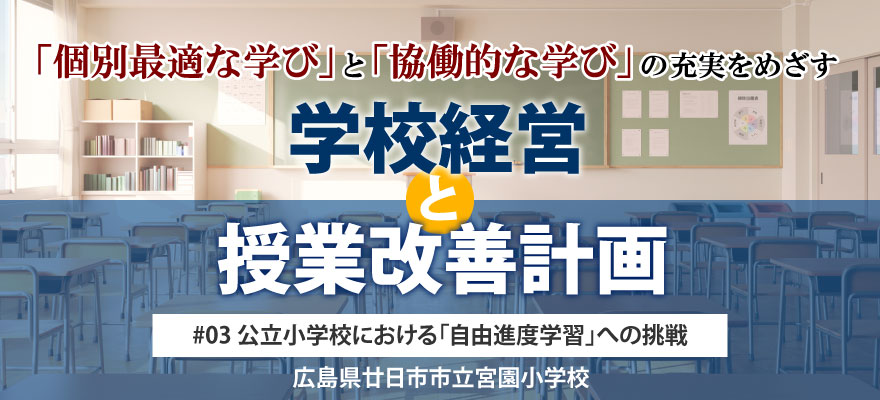
2020年度から広島県の「個別最適な学びに関する実証研究事業」として「自由進度学習」に取り組んできた廿日市市立宮園小学校(児童数198人/2023年3月現在)。その導入の経緯やこれまでの実践の内容と成果について、中谷一志校長、二野宮加代子研究主任に伺った。

広島県廿日市市立宮園小学校
「自分を育て みんなで伸びる」を学校教育目標に、「自立した学び手」の育成を目指している。
この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の3回目です。記事一覧はこちら
目次
きっかけは広島県の「個別最適な学びに関する実証研究事業」から
2020年度から広島県で「個別最適な学びに関する実証研究事業」が開始された。その目的は、「ICTを活用しながら、子どもたちがより主体的に学べる学習について研究する」こと。宮園小学校では、この研究事業の指定校となったことをきっかけに、自分から進んで学び続けようとする意欲や力をもった「自立した学び手」を育成するために「自由進度学習」を導入し、2022年度まで継続して取り組んできた。
研究にあたっては、まずは教職員の意識改革や対話が重要だと考え、広島県教育委員会義務教育指導課指導主事の力も借りつつ、「主体的な学びとは何か」「個別最適な学びとは何か」などについて対話を繰り返した。その中で、多くの教職員から「宮園小学校の子どもたちは自分から考えて行動することが苦手」という声が聞かれ、そうした実態を踏まえて「自立した学び手」の育成を目指した取組を進めていくことを全教職員で共有した。しかし、具体的に「何から始めればいいのか」「どう取り組めばいいのか」もわからない状況だったため、ひとつの提案授業として、中谷一志校長自ら「自由進度学習」の授業を行い、教員に参観を呼びかけた。
その当時はまだ1人1台のタブレット端末がなかったため、授業は教科書とノート・プリントが中心。授業を見た教員からは、「教師の指導がなくていいのですか」という疑問と同時に、「子どもたちが45分の授業時間を一生懸命自分たちで学ぶ姿に驚きました」という反応があったという。
「あの授業はお世辞にもよい実践とは言えないものでしたが、自由進度学習のイメージを教員間で共有することはできたと思います」
2020年9月に1人1台のタブレットが届くと、本格的にICTを使った自由進度学習がスタート。1年目は「失敗してもいいからやってみよう」という中谷校長の声かけのもと、実践しては改良するといった試行錯誤を繰り返しながら学校全体での挑戦が続けられた。授業の内容は結果的に知識・技能の獲得が中心で、子どもたちの自己選択・自己決定の場面では、習熟に応じたコースを選択させたり、練習問題として通常のドリルに加え、AIドリルやプリントを用意したりと取り組み方を工夫。教員から多くの改善案が生まれ、中谷校長もそれを後押しした。

1年目を振り返って新たに生まれた課題意識
1年目のまとめをしている際に、一部の教員から「知識・技能は伸びたけれど、思考力、判断力、表現力で伸び悩んでいる」という声が上がった。中谷校長は、「これは重要な課題意識であり、何より教員から出されたことに意味がある。教員はステップアップを求めている」と捉えた。そこで、その課題の解決に向け、2年目からは「自由進度学習」に精通する上智大学の奈須正裕教授を講師として招聘。2021年3月からオンラインでのやりとりが始まり、6月には実際に学校に招いて指導助言を受けた。奈須教授から「環境を整えれば子どもたちは自立して学ぶ」と指導を受けたことで、宮園小学校の自由進度学習の方向性が定まったという。その後も何度かオンラインなどによる相談を重ね、取り組み2年目にして「自由進度学習」の土台が固まった。3年目以降も引き続き奈須教授の指導助言を受けながら、さらなる充実を図っている。
「著名な講師の方に直接指導していただくことは、内容面の充実だけではなく、教員のモチベーション向上の面でも非常に意義があると考え、思い切って講師をお願いしました」

