リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #39 どんな言葉をかけますか|有我良介 先生(北海道公立小学校)

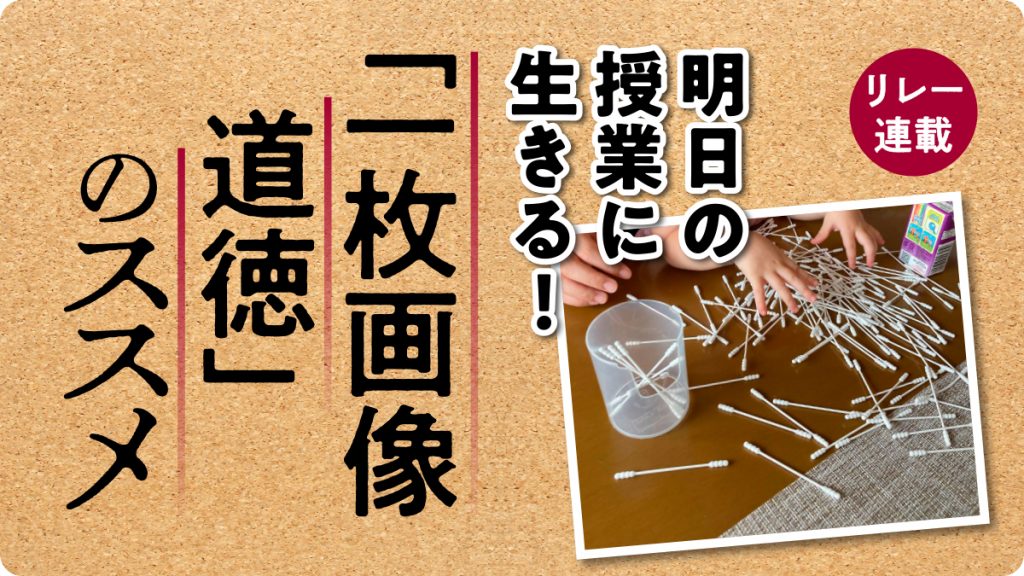
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットを機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今週は有我良介先生のご執筆でお届けします。
執筆/北海道函館市立桔梗小学校教諭・有我良介
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
ごあいさつ
みなさんこんにちは。北海道・函館市で小学校教員をしています。有我良介です。
私には3歳と1歳の子供がいます。妻の方が何千倍も大変な思いをしているので、声を大にしては言えませんが……子育ては大変ですね。
私:『ごはんとパンどっちが食べたい?』
息子:「ラーメン!」
私:『動物園と水族館どっちに行きたい?』
息子:「ウルトラマンに会いたい!」
今まで磨いてきた発問の無意味さを痛感する日々です。
そんな私が、子育てを通して最も価値観を揺さぶられたものは、「子供への声のかけ方」です。
きっかけは、ある子育て番組を観ていたときのことです。大人から見れば明らかに不適切な行動に対して、「すごく楽しそうなことしてるね!」と肯定的に受け止めてから新たな選択肢を与え、適切な行動に導く姿に、「自分はこのように子供の思いを温かく受け止めているのだろうか。」と改めて考えさせられました。
そして、子供たちがよりよく生きるために大切なことを伝えたいと思い、今回の授業を考えました。
1 授業の構想〜ありのままの自分を温かく受け止める存在〜
対象:小学4年
主題名:相手のことを考えて
内容項目:B-10 相互理解、寛容
以下の写真を提示します。写真の子供は1歳であることと、目を離した隙に箱の綿棒を机に出してしまったことを伝えます。

発問1 あなたなら、この子にどんな声をかけますか。
●ぐちゃぐちゃにしちゃダメでしょ。
●ちゃんと自分で片付けなさい。
●どうして散らかしちゃったの?
●一緒に片付けようか。
児童は、自分がよくない行動をとったときに、どんな言葉をかけられたのかを思い出して考えることでしょう。
児童の発言を二種類に分けながら板書をします。一つは、一言目がポジティブなもの。もう一つは、一言目がネガティブなものです。
説明
ここで、次のように説明します。
●写真のお母さんは、一言目に「ありがとう。ママうれしいよ!」と伝えました。
●その後、この子はお母さんに綿棒を渡します。綿棒を使って耳掃除をしていたからです。
●それを見たこの子は、お母さんが喜ぶと思って、綿棒を渡すために箱から全部出してから渡しました。
●周りから見ればよくない行動であっても、その行動の背景を考えることで、その人の思いが見えることがあります。
●子供はありのままの自分を温かく受け止めてくれる大人がいることで、自分の気持ちをコントロールして、自発的に物事に取り組めるようになります(自己抑制)。※1
この説明を聞いた児童たちは、自分が見えていなかった背景に気付き、考え直すことができます。
●この写真を見た瞬間に悪いことをしていると思ってしまった。
●私も、親切のつもりでやったことを怒られてしまった経験がある。
●でも、綿棒をぐちゃぐちゃにしたのはよくない行動だから、教えてあげなければいけないと思う。
ただ受け入れるだけではその人のためにならないと考えるような発言が児童から出てきたら、次の発問に進んでいきます。
もし児童から出てこなければ、教師側から問い返してみるとよいかもしれません。
『確かに、悪いことをしたら教えなければいけないよね。じゃあ自分だったら一言目にどんな声をかけられたら、受け止めてもらえたと思えるだろうか。』
発問2 もしあなたが、よくないと見られる行動をとっていた場合、どんな言葉をかけてもらいたいですか。
(例1:黙食中に友達と話している場面)
●話しているけど、どうしても話さなければいけないことがあった?
●どうしました? 困っていることがあって話しているなら手助けするよ。
(例2:机の上が散らかっている場面)
●一緒に片付ける? 一人で片付ける?
●(違う話題について話しかけてから)ところで、何が起きてこういう状態になったの?
例示する場面は児童の実態によって変えます。
一人の状況や複数人での状況、自分が明らかに悪い状況や巻き込まれてしまった状況など、その時々によって声のかけ方は変わります。児童たちは、想像をめぐらせながら、自分に置き換えて考えることでしょう。
不適切な行動を見た瞬間に否定的な見方をしていた児童は、どのように声をかければよいかを考えられない可能性もありますが、そのような自分に気付くことも大切だと考えます。
考えがもてない子が多ければ、児童に発表してもらったり、役割演技を行ったりするのもよいかもしれません。

