「理解→表現」か「表現→理解」か【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第24回】

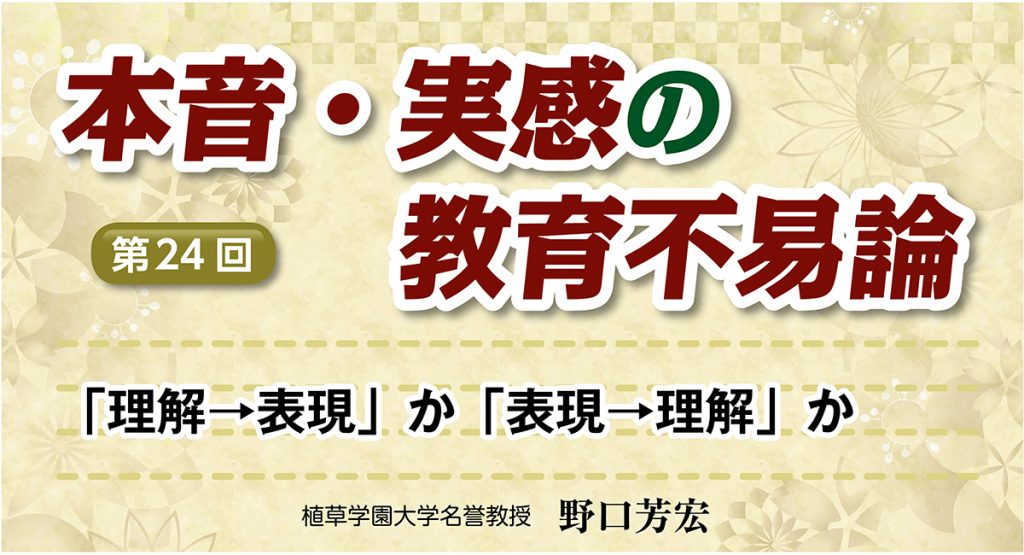
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第24回目は、【「理解→表現」か「表現→理解」か】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 不易と流行の本来
「不易流行」という四字熟語について、『大修館四字熟語辞典』では次のように説いている。
変化することのないものと、変化してやまないもの。松尾芭蕉は、俳諧は、永遠に変わらないものと時に応じて変化するものとの両面に立脚しており、風雅の誠を求めて変化し続けていくことこそが俳諧の不変の価値を実現する、という不易流行論を説いた。
初文は文字どおりの解説である。第二文は芭蕉の俳諧論の根本を端的に解説している。「風雅の誠を求めて」が、時空を超えた俳諧論の不易なる前提、本質である。続く「変化し続けていくこと」が流行の部分である。求めるべき目的は「風雅の誠」であり、それが「永遠に変わらないもの」と芭蕉は説いたのである。続けて「時に応じて変化するもの」にも注目しつつ詠むべきだと説いたのだ。揺るぎなき正論、真実と言えよう。
芭蕉は「俳諧」について述べているが、「俳諧」をそっくり「学校教育」と置き換えてみても何らの科は生じまいと思う。教育の世界でも「不易と流行」の「両面に立脚して」いることに変わりはないだろう。
俳諧を学校教育と置き換えてもよい、と述べたのだが、私はむしろ「不易」の部分を重視し、「流行」についてはもう少し軽くみてもよいのではないか、と考えている。流行が全く不要などと言っているのではない。
義務教育期間の9年間と、高校3年間の計12年間の教育内容、教育課程は、およそ10年間のサイクルで改訂されている「学習指導要領」によって規定される。
その改訂については、文部科学大臣が中央教育審議会に諮問し、その答申に基づいて新しい「学習指導要領」が作られ、それに基づく教科書が誕生し、現場の教育実践のありようを規定していくことになる。
このような手続きによってなされる改訂は合理的と言えるだろう。だが、学校現場にその理念が下ろされる頃には次のような傾向が生じてくるのが通例である。
ア、「変わった部分」への過剰反応
イ、「不易」の部分の軽視
改訂されると、「変わった部分」「新しくなった部分」ばかりが強調されがちだ。現場では、それまでの実践のどこをどう変えるべきかというところにのみ意識、関心が向いてしまい、授業の本質、教育の本来像などがぼやけてしまうのである。
小、中学校の教育の根本価値をずばりと一言で言うならば、「基礎教育」という一点になろう。「基礎教育」の、その本質は、「不変、不動」という一点にある。この考えには大方異論はなかろうと思われる。
このことは、中央教育審議会も文部科学省の当局もよく理解しているので、どの改訂にあっても「基礎・基本が大事」という文言は必ず書かれている。
ところが、現場の指導者層が説く段になると、多くは「何が変わったか」「これからの授業はどう変えていくべきか」という点が強調され、指導され、授業に偏りが生じてくるのである。つまり、「流行」の部分への過剰な傾斜を強めることになり、相対的には「不易」の部分が軽視されることになりがちだ。これは本末の転倒である。

2 流行の定着は不易になり得るか
これまでになかった考え方が発表された時には、その新鮮さが大きな話題になる。大きな関心を集める。新しいことの価値や意義が強調されることになる。当然である。
それが10年も続くと、もはや「定着」の感が生まれ、せっかく定着してきたものをまた改める、ということはできにくくなる。そして、疑問を抱きながらも、「これまで続けてきたのだからー」、「続いてきたのだからー」ということで変えにくくなってくる。かくて、まるでその考え方が正しいことのように思われて居座り続けるという事態になってくる。
昭和52年の学習指導要領によって国語教育は大きな二つの変化を生み出した。
その第一は、それまでの「経験主義的な活動中心」の内容区分「聞く・話す」「読む」「書く」から、「表現」「理解」「言語事項」という「言語能力中心」の内容区分に改められたことである。
そして、その第二は、「表現」「理解」という「表現重視」、つまり「理解」を「表現」の後に置くようになったことである。
ここで、特に問題としてみたいのは、第二の「表現重視」という「新しい」考え方である。
それまでの戦後30年ほどの国語の学力構造、あるいは内容構造は、大きくは、
「聞く・話す」
「読む」
「書く」
「言葉に関する事項」
という順序で把握されていた。
「聞く・話す」というのは「音声言語」の活動であるが、「聞く」が、「話す」に先立っている。つまり、この配列は「理解→表現」という順序になっている。
次の「読む」「書く」は、「文字言語」に関する活動であるが、その順序は「読む」「書く」であり、これも「理解→表現」という順序になっている。いわば「理解第一」「表現第二」である。
昭和52年の学習指導要領「国語」では、この伝統的な「理解→表現」という順序を逆にして「表現→理解」としたところに大きな転換があったと言える。
その後、「表現」「理解」という内容区分は、「A・ 話すこと・聞くこと」「B・ 書くこと」「C・ 読むこと」と改められたが、その配列の順序は依然として「表現→理解」という原理の踏襲である。この考え方は妥当かつ適切と言えるのだろうか。平成29年の改訂でも、この基本的な考え方、即ち「表現優先」が踏襲されて後の10年に継承されることになった。「表現優先」という考え方は、昭和52年以来ざっと40年、半世紀近くに亘って国語教育の「常識」となりつつある。つまり、かつての「流行」は、長年の「定着」によって、もはや「不易の真理」とも見做されそうなのだ。これでよいのだろうか。改めて考えてみたい。

