何のためにを考える〈前編〉【伸びる教師 伸びない教師 第19回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

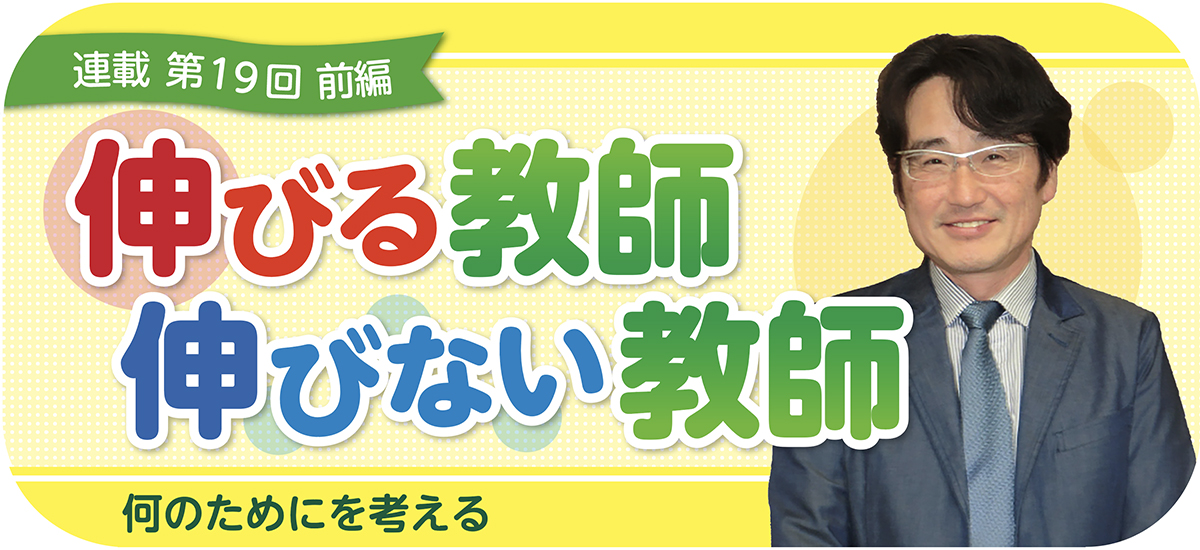
今回は、「物事に取り組むときに目的を考えること」を前後編に分けて紹介します。前編は、家庭訪問の目的を考えた出来事の話です。豊富な経験で培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする平塚先生の人気連載です。
※本記事は、第19回の前編です。
プロフィール
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県上三川町立明治小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を歴任。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
伸びる教師は、物事に取り組むとき「何のために」と考え、伸びない教師は疑いなく取り組む。
目次
10秒を短縮する理由とは
先日、避難訓練で全校児童にこんな話をしました。
「今日の避難にかかった時間は〇分〇秒です。あと10秒減らせます。避難した時に『まっすぐ並んでー』って担任の先生に言われていたでしょ。あの時間を減らせると思います。体育の時にきちんと整列する練習をしているのは、こうした緊急時に素早く並べるようにするためでもあるんです」
避難の集合時に人数確認を10秒早く行えれば、万が一逃げ遅れた子供がいたとしても10秒早く助けに行くことができます。特に火災の場合はその10秒が命取りになることもあります。
体育ではこうした非常時も想定して、集団行動の中で素早く整列できることや的確に行動できることを指導しています。「運動会で集団行動するからいいや」とか「戦時中みたいであまり好きじゃない」等の理由で積極的に指導しない先生を見かけることがありますが、こうした「何のために」という視点をもつことが大切です。


