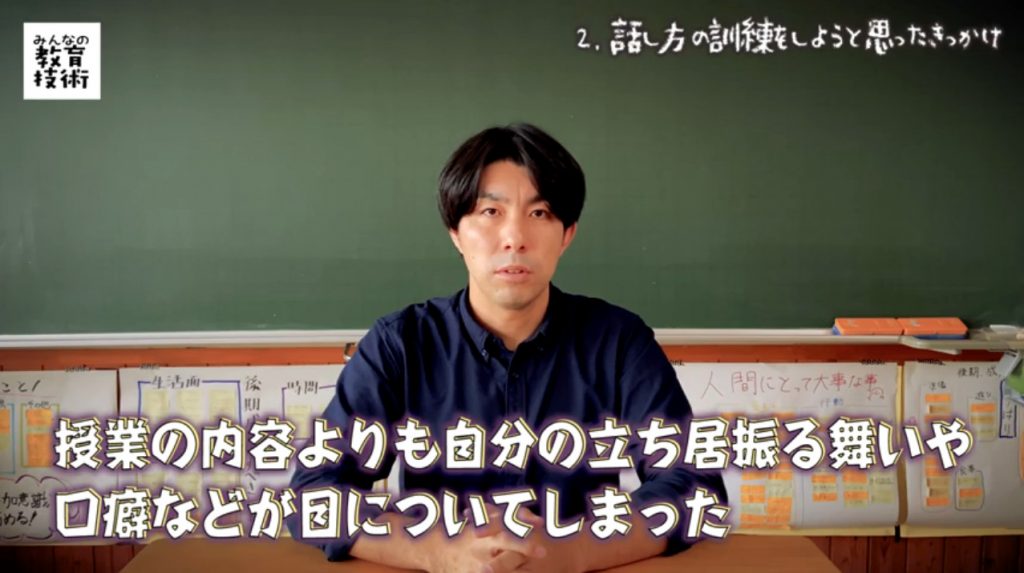教師の「話す技術」をアップする古舘式トレーニング法【動画】

自分の「口癖」、知っていますか? 授業や学校生活の中での説明や指示は、子供たちにとって聞きやすく伝わる力を持っているでしょうか? 自らの体験に裏打ちされた教育哲学と再現性の高いスキルをTwitter(@YoshiJunF)で発信し、若手教師を励まし続ける古舘良純先生からの今回の提案は、言葉の力を最大限に活かして授業に役立てる「話し方」の訓練です。
目次
1. 話し始めるときに言いがちな4つの言葉
「はい」
「じゃあ」
「えーと」
「それでは」
今回ピックアップしたツイートは、私たちがつい多用してしまう「この4つの言葉を使わずに教師からの指示、発問、説明などをしてみませんか?」という内容です。
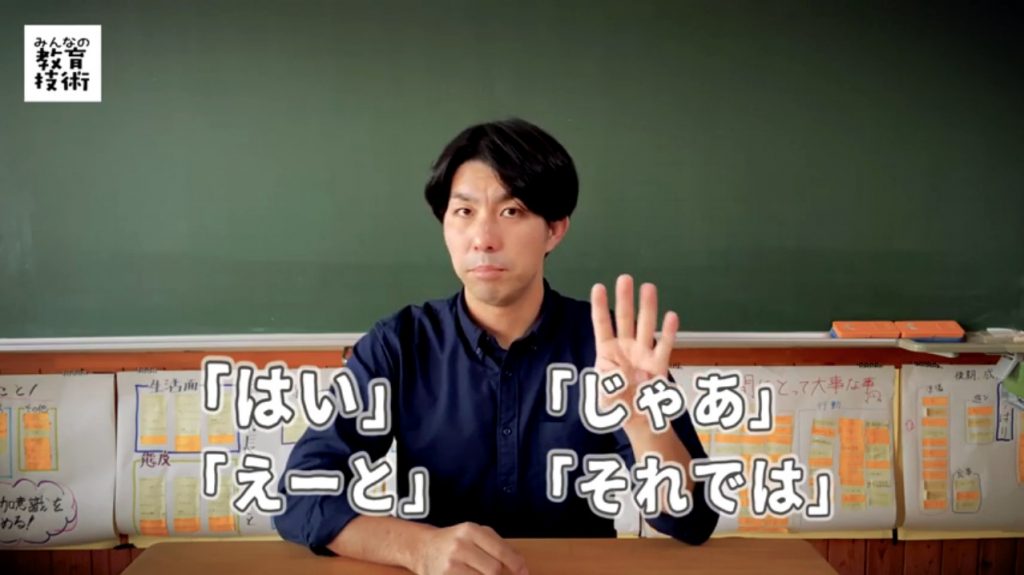
2. 話し方の訓練をしようと思ったきっかけ
これらの言葉を使わない話し方を訓練してみようと思ったのは、この4つが私自身の口癖だったからです。
数年前に自分の授業研究会のビデオを録画して見ていたときのこと。授業の内容よりも、自分の立ち位置や立ち方、しぐさ、振る舞い、それに加えて「はい」「じゃあ」「えーと」「それでは」というような口癖が気になりました。