【シリーズ】高田保則 先生presents 通級指導教室の凸凹な日々。♯20 外国にルーツをもつ子どもたちへの支援 ―適応するのは、子どもか、学校か

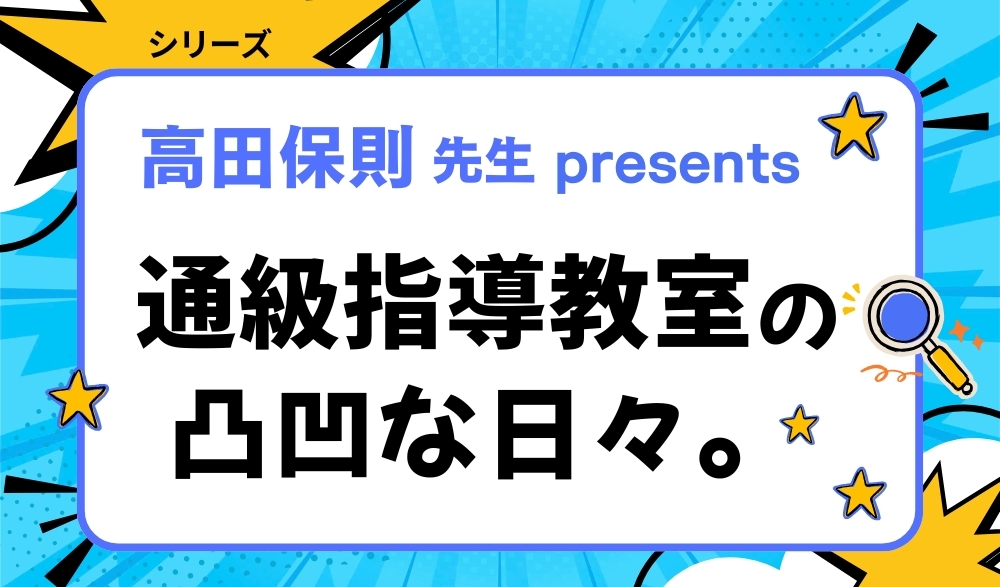
通級指導教室担当・高田保則先生が、多様な個性をもつ子どもたちの凸凹と自らの凸凹が織りなす山あり谷ありの日常をレポート。情熱とアイデアに満ちた実践例の数々は、特別支援教育に関わる全ての方々に勇気と元気を与えるはずです。
執筆/北海道公立小学校通級指導教室担当・高田保則
目次
はじめに
北海道オホーツク地方の小学校で、通級指導教室を担当している高田保則(たかだやすのり)です。日々、子どもたちと向き合う中で感じたことや考えたことを綴っています。ここに記す事例は、これまでに出会った子どもたちのエピソードを組み合わせて作った架空のお話ですが、実際に過ごした時間の空気感を込めています。
学校で「当たり前」とされている行動やルールは、誰にとっての常識なのでしょうか。授業中に席に座ること、身だしなみの決まり、言葉にされない生活上の約束事。外国にルーツをもつ子どもたちとの関わりを通して見えてきたのは、子どもの適応力だけに期待する支援の限界と、学校側が前提としている文化の存在でした。
学校ではしばしば、「適応できない子ども」が課題として語られます。しかし、そのとき学校自身の前提や文化が問い直されることは、ほとんどありません。適応するのは子どもなのでしょうか。それとも学校なのでしょうか。通級指導の事例から、その問いについて考えてみたいと思います。
1.授業中に立ち歩くEさん
Eさんが生まれたのは、南の国でした。父親の転勤に伴い、この町にやってきました。母親は南の国の出身で、宗教上の理由から家庭では肉食が厳しく制限されていました。そのため、Eさんは学校給食を食べることができず、毎日弁当を持参していました。
小学校入学後、Eさんについての相談が寄せられました。主訴は、授業中の落ち着きのなさでした。立ち歩きが収まらないというのです。父親は日本人で、Eさんの話し言葉は日本語でした。学級担任の指示も理解できているように見えましたが、行動には結びついていませんでした。
知能検査の結果は平均域で、認知面に大きな弱さは見られませんでした。一方で、Eさんと会話を重ねる中で、細かな言い回しや抽象的な表現が十分に伝わっていないという感触を持ちました。母親は日本語でのやりとりに不自由があり、家庭内の会話は母国語が中心でした。Eさんは、日本語の抽象的な表現や含みをもった指示の理解に苦戦しているのではないか、という仮説を立てました。
それでも、Eさんの落ち着きのなさは際立っていました。席に座っていられず、やがて床に寝そべる姿も見られました。Eさんは南の国の幼稚園に通っていたと言います。そこで、もう一つの視点が浮かびました。そもそも、その国の幼児教育では、「席に座って学ぶ」ことが前提になっていたのでしょうか。
私たちは、自分たちの国の教育文化を基準に「当たり前」を考えがちです。しかし、幼児教育の形態や集団の約束事は、国や地域によって大きく異なります。Eさんの行動は、能力や態度の問題ではなく、前提となる文化の違いによって生じていた可能性があると考えました。
文化の違いを指導仮説に加えたEさんの通級指導が始まりました。環境や関わり方を少しずつ調整する中で、Eさんは日本の学校生活に徐々に慣れていきました。子どもには確かに高い適応力があります。しかしそれは、大人が子どもの困りを言語化し、環境を整えたときにこそ発揮される力でもあるのだと思います。
Eさんにとっての通級指導は、「正す」場ではなく、文化の違いを言葉にし、翻訳する役割を担っていたのだと振り返っています。

2.イライラが溜まっていたFさん
Fさんは日本で生まれ、幼い頃にヨーロッパへ移り住みました。両親は日本人で、家庭の事情から帰国し、この町にやってきました。ある日、Fさんがピアスをつけて登校したことで、職員室がざわつきました。現地では珍しいことではないとのことでした。意志のはっきりしていたFさんは、文化の違いを理由に、ピアスを外すことを拒みました。
その後、Fさんが家庭でイライラを募らせているという話が伝わり、通級指導につながりました。Fさんは、友だち関係、学校の決まり、生活習慣、暗黙のルールなど、さまざまな違いに戸惑っていました。異なる文化に適応してきたFさんにとって、日本の学校文化は新たなストレス要因になっていたと見立てました。
通級指導では、Fさんとの対話を大切にしました。ヨーロッパの歴史に興味があると聞き、日本の歴史漫画を紹介したことをきっかけに、住んでいた国のことや学校生活、その国の言葉について、少しずつ話してくれるようになりました。Fさんにとっての「常識」は、私にとって新鮮で、学ぶことの多いものでした。
やがてFさんは、自らピアスを外し、日本の学校生活に馴染んでいきました。これもまた、単なる「適応」ではありません。理解され、語ることのできる場を得たことで、自分なりの折り合いをつけた結果だったのだと思います。
Fさんにとって、通級指導教室は、自分の立場や評価から一時的に距離を置ける場でした。だから、Fさんは、日本の文化に「従うか、拒むか」という二択ではない選択肢を見つけることができたのではないでしょうか。

3.適応できた、という安心の陰で
心理学の知見によると、バイリンガルの子どもたちは、認知や思考の柔軟性が高いと言われています。事例のEさんやFさんにも、そうした傾向は感じられました。2人とも、周囲の子どもたちに溶け込むのが早く、入学や転校からほどなくして友達ができていきました。当然、2人に関わる職員も、友達づくりが円滑に進むよう、さまざまな配慮をしていたのだと思います。
一方で、私は次第に引っかかりを覚えるようになりました。
子どもたちが示したその柔軟な適応力に、私たちはどこまで依存してよいのでしょうか。環境や文化の違いを乗り越える負担を、知らず知らずのうちに子ども自身に引き受けさせてはいなかっただろうか。子どもが「慣れていく」ことを前提にすることで、学校の側が立ち止まらずに済んでしまう構図が、そこにあったようにも感じられました。
4.マナー違反の誤解
文化の違いは、教室の中よりも、むしろ日常の場面で誤解として表れやすいのかもしれません。
田舎町にも外国籍の労働者が暮らすようになりました。ある時期、スーパーで購入された食材の容器が店内に捨てられていくことが話題になりました。異国では、市場で量り売りの食材を購入するのが一般的な地域も多くあります。すべてが容器とラップで包装されている日本の販売形態は、決して世界の標準ではありません。
「容器は持ち帰ってください」
その内容を多言語とイラストで示したポスターが掲示されると、問題は自然と解消されました。
相手を正す前に、情報を共有すること。その大切さを示す出来事だったと思います。

5.前提を疑うことから始まる共生
どの地域の学校にも、外国にルーツをもつ子どもがいることが当たり前の時代になりました。彼らが快適な学校生活を送るために必要なのは、努力や我慢を求めることではありません。学校や地域が、自分たちの文化や常識を言葉にし、伝えることなのだと思います。
「わかっているはず」「できて当たり前」という前提を一度疑うところから、共に学ぶ関係は始まるのではないでしょうか。
6.文化の違いは、日常の中に
外国に限らず、文化の違いは地域や暮らしの中にも存在します。北国で育てば、雪道の歩き方や凍結路面での運転に、独特の感覚が身につきます。それは、体験しなければわからない文化でもあります。子どもの言動にも、こうした違いが反映されているのでしょう。
子どもや保護者の言動を理解しようとするとき、文化の違いという視点を加えることは、対話への第一歩になるのではないでしょうか。適応するのは、子どもなのでしょうか。それとも、学校や大人のまなざしなのでしょうか。
「適応できない子ども」がいるのではなく、「子どもが適応することを前提にしている学校」がある。そう捉え直すと、別の景色が見えてきます。そして、そうした学校文化を日々維持してきた一員に、私自身も含まれていたことに気づかされるのです。
〇参考文献・資料
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す, 個別最適な学びと協働的な学びの実現~ (答申) 文部科学省 令和3年1月
第Ⅱ部 各論 5.増加する外国人児童生徒等への教育の在り方について p.69~74

高田保則先生プロフィール
たかだ・やすのり。1964年北海道紋別市生まれ。オホーツク地域の公立小学校教諭。公認心理師。特別支援教育士。開設された通級指導教室の運営を任され、新たな指導スタイルを模索している。趣味はバンド演奏。

