2019年度 第55回 「実践! わたしの教育記録」 全入選作品選評
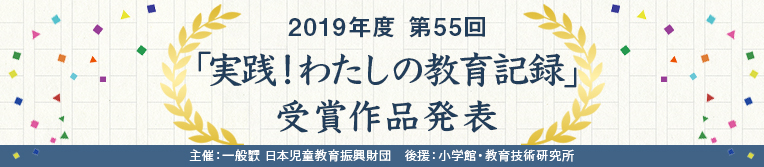
第55回「実践! わたしの教育記録」入選作品が決定しました。審査をお願いした、赤坂真二先生、岩瀬直樹先生、菊池省三先生、木村泰子先生ら4名の審査員の選評をお届けします。
赤坂真二:教育界の共有財産としての「価値」ある実践群

上越教育大学
教職大学院教授
赤坂 真二 さん
初めて「実践! わたしの教育記録」の審査を担当させていただきましたが、いずれ劣らぬ力作揃いで圧倒されました。
特選に選ばれた内山智枝子先生の実践記録は、まず、依って立つ考え方が明確に示されていて、一貫性のある主張でとてもわかりやすかったです。「作家の時間」の発想を自らの専門教科に応用し、生徒たちが科学に没頭する時間を創り上げていく指導過程が矛盾なく構築されていて説得力がありました。また、恐らくもっとたくさんの生徒の活動や変容に関わるデータがあっただろうにもかかわらず、効果的に抑制された結果表記によって、より鮮明に授業の成果が伝わってきました。
「実践記録」といえども、応募し、審査を受けるようなものは、共有財産としての「価値」が問われるのではないでしょうか。共有財産となるためには、どのような考えに基づいて、どのような手立てによって、どのような変化が起こったかの明記が大事だと考えます。そうした視点から見て、内山先生の実践記録の評価は妥当なものだと受け止められます。
共有財産としての「価値」という点から見ると、特別賞に選ばれた髙槗朋彦先生の実践記録も見逃せないでしょう。「校内研修」をテーマに据えたことは、現代的なニーズをよく捉えたものだと指摘できます。「働き方改革」が叫ばれる昨今、真っ先にやり玉に挙げられ、削減の対象になりそうなものの一つに校内研修が挙げられます。一方で、未だに、「研修のための研修」を繰り返しルーティンのように実施している現実もあります。そのような現状に対して、校内研修を、職員のチームビルディングの場として再定義し、職員の関係性と実践力を両方とも高めようとする取り組みは大いに評価できます。
紙幅の都合で詳細は述べられませんが、五十嵐太一先生、伊藤智子先生、松井香奈先生の実践は、すぐに他者と共有可能な実用性の高い実践でした。いずれも共有財産としての価値の高いものだったと思います。しかし一方で、やったことの羅列になっている記録が散見されました。実践したことそのものには高い価値があろうかと思います。ただ、教育界への貢献を考えると、もう一歩の記述の工夫がほしかったところです。
岩瀬直樹:「新しい実践を開発しよう」という気概に満ちた特選作品に感動

一般財団法人軽井沢風越学園
設立準備財団副理事長
岩瀬 直樹 さん
情熱的な実践記録を数多く読ませていただいた。
特選に選ばれた「中等教育理科における『教科する』授業の追究」の内山智枝子さんの実践を読ませていただいたときには、審査員をお引き受けして本当によかったと感動した。探究的な学びの重要性が広く共有されてきているが、その中でも内山実践は、既存の一般的な授業に囚われず「新しい実践を開発しよう」という気概に満ちた、提案性が高い魅力的な実践である。生徒自身が科学者となり、専門家が取り組むリアルで有意味な探究過程を追体験する「科学者の時間」は、私が生徒になって学びたいと思える「教科する」授業であった。なにより内山さんの実践の中での試行錯誤が記録されていることを評価したい。結果だけではなく、実践をつくっていくプロセスの開示は多くの人の参考になるだろう。
また特別賞「校内研修を活性化する研修デザイン」の髙槗朋彦さんの実践は、従来の「校内研修=研究授業」という常識に囚われず、教師の力量向上に焦点を当てて設計されていて興味深い。一人ひとりの教師にとって学びがあり、成長を感じさらに言えば「楽しい」と思える研修。既存のリソースを活用しつつ、研修を通して職員室に新しい同僚性を構築しようという試みは、校内研修のデザインで悩んでいる多くの学校の刺激になるのではないか。
入選の五十嵐さん。「習字の授業かくあるべし」の思い込みを問い直し、学び合う習字を試行錯誤されているが、子どもたちの声がこの授業の価値を体現している。伊藤さんの取り組みは、教科の授業と生徒会活動をつないだダイナミックな実践であり、学級づくり部門としてはもちろん、学校づくり部門としても評価したい。永田さんの学校づくりの実践は、極めてシンプルな取り組みながら、教職員のチームづくりや力量形成に寄与している点において大いに評価したい。ユーモアあふれ、学びへの誘いもある「きらめき言動」集は読み物としても出版する価値があるのでは、と思うほどだ。新人賞の松井さん、若いエネルギーを感じる勢いのある実践だ。実践しながら子どもの声を大切にして生成的に展開される実践で、今後の発展を楽しみにしている。

