2019年度 第55回 「実践!わたしの教育記録」 授業・学級づくり部門:入選作品発表
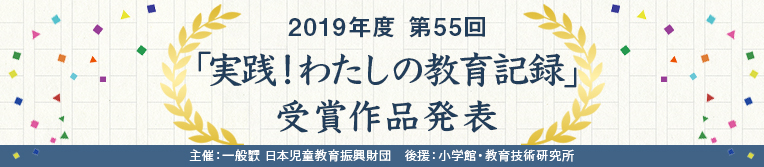
※入選作品をウェブに掲載するにあたり、画像資料の指示語をウェブページレイアウトに適した語に変更しています。
オーストラリアとの交流を通した「主体的・対話的で深い学び」の実践
―英語科と生徒会を軸に、活動を言語でつなぐ―
東京都足立区立江北桜中学校 伊藤智子
1.はじめに 「なんで英語やるの?」着任初日に叩きつけられた、生徒からの挑戦状
「先生、英語の先生なんだ? 私、英語大嫌いだから。なんで英語なんてやらなきゃいけないの。絶対勉強しないから。授業も寝るからね!」。赴任した2017年4月の着任式、続く始業式が終わって体育館から戻る時に、まだ名前も知らない生徒から言われたのがこの一言。こんな風に本校での一日目が始まった。「なんで英語をやるかって? いい質問! 助けるためだよ、英語で、人を」。私はそう答えた。
「なぜ英語をやるのか」。この問いに正対し、生徒が考え、自分の意見を持ち、表現し、自分の生き方を決めていく授業をしよう。行動力につながる意欲を、授業を通して育てたい。そして学ぶ理由を、生徒自身がつかみ、決めていけたらすばらしいではないか。学習意欲、学力テストで測られる点数ともに課題がある本校だが、それがどうしたというのだ。生徒は素直で明るく、こんなに正直だ。そんな生徒たちと、筆記テストの点数だけでは測り得ない、知識が行動力に転化する自律的な学びを、英語の授業で展開しよう。それがいつか点数にもつながるはずだ。そんな本校に、絶好の学びの機会が訪れた。
2.本物に触れる・世界に触れる
スプリングフィールド・レイクス州立学校(以下SLSS。クインズランド州、オーストラリア)は、生徒数1000人を超える小学校で、小学5年生より第二言語履修が必須であり、とりわけその将来性から日本語が人気で、熱心に学習されている。2017年秋、クインズランド教育省の承認を経て、SLSSの修学旅行(全10日間)の最終行程に、本校訪問の依頼を受けることになった。先方22名の生徒は、全員本校生徒宅へのホームステイも希望している。日豪双方の子どもたちにとって絶好の直接交流の機会である。これ以上のリアルはない。折しもオリンピック・パラリンピックの前年であり、手作りの「おもてなし」実践の場となる。そして、2019年7月の来校を目標に、英語科と生徒会を軸として、2年間にわたる学びのロードマップを学校全体で進めることになった。
3.学校全体で「主体的・対話的で深い学び」につなぐための手立て
手立て①リアル文通で交流
「聞く」「話す」「読む」「書く」の英語4技能のうち、書くことは最もハードルが高く、また通常の英語授業では、英語で書く必然性を感じづらいことから相手意識をもたせにくく、「英作文」の域を出ないことがある。SLSSから送られてきた日本語と英語交じりの直筆の手紙は、生徒たちに「相手がなんて伝えたいのか、知りたい」という読む意欲と、「その子のために役立つ情報を伝えたい」というコミュニケーションの根幹を教え、体験させてくれた。教科書の英文では「どうせわからない、読めない」と諦めてしまう生徒も、英和辞典を片手に黙々と手紙を読む。こなれたアルファベットの文字でも、内容を読みたいから「先生、これなんていう文字?」と我先にと質問してくる。本校からは返事として、おすすめしたい日本文化紹介を添えた自己紹介を、英語と日本語で書き、送った。メールやSNSの時代、紙の手紙に慣れていない生徒にとって、いきなり手紙を、しかも英語で書くのは難しいこと。そこで、全学年の授業で自己表現スピーチや、「会話すごろく」を活用して、自己紹介や考えを伝えあう活動を毎時間繰り返し行ってきた。そのため、話す活動から書く活動への心理的なハードルが低くなることにつながり、生徒たちは英語の間違えを恐れず、「本当に伝えたい内容」に集中して返事を書いていた。日本文化の紹介は、入学して間もない時期からプレゼンポスター制作を、意図的・計画的に取り組ませていたため、返事を書く頃には随分慣れてきてスムーズになっており、日本のお菓子やキャラクター、観光地や風習など、バリエーションに富んだ内容での返事を送ることができ、生徒たちの達成感も高かった。自分が書いた手紙が、オーストラリアの教室での日本語の教材になるのだから、がぜん頑張るわけである。
手立て②給食メニューを考える「おもてなし」 Let’s decide the lunch menu for SLSS!
日本語、そして日本文化を学ぶSLSS生徒にとって、日本の学校を一日体験することは、Japan Tourのハイライトであった。足立区は食育の一環として「おいしい給食」を教育施策の看板にしている。そこで、栄養士さんのご協力のもと、来校日の給食の主食メニューを生徒たちが決めることになり、2年生で授業を行った。
授業の流れは、まず、世界の食文化について生徒がもつ既存知識を生かしながら、さまざまな国の名物について世界地図に記していく。
T:Let’s talk about world dishes today. Miso soup is a specialty of Japan. Anything else?
(今日は世界の料理について話そう。日本食といったら、味噌汁とか。他には?)
S:How about ramen? We have tempura,katsudon,too.
(ラーメンはどう? 天ぷらやかつ丼も)
T:Look at the blackboard. I draw a world map. Here? Yes,it’s India. What food is famous in India?
(黒板に世界地図を描きますね。ここは? そう、インド。インドでは何が有名?)
S: Curry. Nan. Biryani.
(カレー。ナン。ビリヤニも。)
T:Right. We eat curry in Japan. We use spoons. How do people in India eat curry, do you remember?
(そうですね。日本でもカレーを食べるけどスプーンで食べますね。インドの人たちは何で食べるか、覚えていますか?)
S: With their right hands!
(右手を使って食べる!)
昨年度のALTはインド出身の方で、世界の食文化や食習慣についてCLIL(内容言語統合型学習)でインドの食文化についても学習したので、その時のことを想起させることから始めた。また、社会科や家庭科で学んだ知識を活用させながら、国や文化、宗教によって食べない食品があることにも触れ、文化の多様性について考えさせた。さらに、今回のゲストSLSSの出身、オーストラリアの名物って何だろう、という話につなげ、調べ学習課題として行い、発表させることで理解を深めさせた。
T:It’s the first time for SLSS students to see Japanese school lunch. Why don’t we decide the menu of that day?
(SLSSの生徒にとって、給食という日本の学校文化を見るのは初めてです。その日の給食のメニューを、君たちが決めてみない?)
授業は少人数授業のため3名の専任で授業を分担しているが、各少人数グループで打ち合わせをして同じ展開で授業をし、「主食は麺類」と決まった。麺といってもさまざまある。そこで、生徒たちは自分のおすすめ麺メニューを考え、英語で調査活動とプレゼンテーション活動をした。
結果、「地元野菜たっぷり塩ラーメン」に決定。さて、ここで栄養士さんからの情報が入る。普段は豚骨でダシを採っているとのこと。「先生、ムスリムの子がいたとしても、誰でも安心して食べられるように、世界標準の配慮をしませんか」。授業で学んだ食文化の知識を活かし、相手意識と思いやりをもって想像し、行動に移そうとする生徒の成長に、私自身が感動した。そこからはダシ(Soup stock)の話題に移っていく。すると、家庭科で学んださまざまなダシ(bonitoカツオ、mushroomsしいたけ、sea weed昆布)へと、生徒たちのアイデアと発言がとまらない。「昆布って、英語でどう説明するの?」と自ら和英辞典を引く生徒たち。そして、栄養士さんの助言をいただいて、鶏ガラだしに決定。「ハラル対応野菜たっぷり塩ラーメン」である。来校日が七夕に近かったので、星の形のナタデココ入りの七夕ゼリーを添えたメニューが、こうして完成した。生徒にとっては英語授業と給食がコラボした、記憶に残る給食となった。
手立て③交流会の構築 得意なことを、他の人のために発揮しよう
2017年春に統合新校としてスタートした本校は、開校当時「生徒が主体的に考え活動する」というよりは、「教師からの指示を受けてその通りに動く」という学習スタイルに重点が置かれていた。その気風を、生徒会活動を通して1年半の時間をかけて同僚と共に変えていった。例えば、新入生歓迎会や3年生を送る会、定例の生徒朝礼などの在り方は、「言語活動」というキーワードで意図的につなぎ、スピーチや寸劇、インタビューなどのやりとりを多用することで、生徒が自身の言葉で語る機会を設け、躍動的なパフォーマンスの形へと、設計をモデルチェンジさせた。何を聞かれても「別に」「わからない」と、意見をもたなかった生徒たちが少しずつ変わっていったのは、英語授業での自己表現活動と生徒会活動との両輪が形づくられてきた時期と一致する。イベントの企画・広報や運営の仕方をやりながら教え、話し合いを経ての合意形成を体験、実践、分析・改善させ、ほめることで生徒たちの自信を形にしていくことにした。各授業や学級で日々学んでいる、図を描いて考えることや、伝える順番を意識して話すことなどを、実際の行動の場面にこそ、活かすのである。そして、「為すことによって学ぶ」という体験を、生徒会組織を軸に積み重ねた。生徒だけでなく教員も、生徒の姿をもって互いに指導を見合い振り返る機会ができたことで、職員室の話題がふくらみ、互いに取り入れ、教科や学年の活動等と連動させることにつながった。そうした教員同士のコミュニケーションや連携こそが、学校全体の学習観や指導観の豊かさにつながるということを、私自身が目の当たりにし、まさに体験的に学ばせていただいた。
生徒会本部、中央委員会、各委員会、部活動等の組織を、各行事と無理なくリンクさせることで、リーダー育成と生徒によるアイデア構築実現に生かすことをねらいとした。生徒たちは自分を表現する方法や場面が様々あることを、得意な生徒や先輩から学んでいった。「前に出て皆に指示したり、自分の得意なことや好きなことを生かして人を楽しませたり助けたりすることが、君にもできるんだよ」、というメッセ―ジを、教員からも絶えず発信し続け、やってみせ、繰り返しやらせ、自信のない生徒たちを信じ、励まし続けた。
生徒会活動で培った、「積極的に一歩踏み出して人と関わり、行動すれば、自分も周りも楽しくなる。人の役に立てると達成感があり自分もハッピーになる」という一連の経験は、今回のSLSS訪問において、生徒が主体的にプロジェクトを推進する上での大きな基礎体力となった。交流会開催に際して、生徒のアイデアを基にボランティア募集の英文広告を読解する授業を行ったところ、またたく間にスタッフが決まった。来校2か月前から全学年の英語授業を中心に、いよいよ交流会での出し物等の準備が本格的に始まった。普段の教科書や単語テストさえも、実践コミュニケーションへの大切なリソースに変わった。生徒はもう英語から逃げてなどいない。学ぶ目的をもった英語学習では、集中が高まり、音読の声も、歌や暗誦の声も断然大きくなった。相手が困っていたら、言葉と行動でどう助ければいいか、生徒が自分で考えるようになった。英語と生徒会の相乗効果である。
交流会運営でのボランティアの仕事では、特に相手意識が大切だ。ゴールは何か、「自分たちの言葉で日本の学校を紹介する」とはどういうことか、それを実現するプログラムを考えさせ、各係のチーフを決める。もうこの時点では、最低限の指示だけ与えれば、生徒たちが自分で役割分担とスケジュールを決め、学年を問わず言葉で関わり合い、プロジェクト全体の「おもてなし」がうまくいくことを目指して動く、主体的な生徒の姿に変わっていた。教員では思いつかないような、柔軟なアイデアも飛び出した。例えば、区のキャラクターである「ビュー坊」の着ぐるみを区役所から借りて活用できないか、などである。この提案は区役所の協力を得て実現し、3年生の男子が着ぐるみを担当し、愛くるしい動作で大いに盛り上がった。また、日豪全員で歌う歌「Count on me(Bruno Mars)=友情がテーマの歌」とオーストラリア民謡「Waltzing Matilda」の練習は、英語授業の他にも音楽の授業や昼休みの有志合唱団にも波及し、学校全体が音楽のすばらしさや歌うことの意義、メッセージを伝える尊さを、身をもって経験する機会となった。当日の感想アンケートからは、日豪大合唱も含め、大きなインパクトとして記憶に残ったことがうかがえる。ボランティアは、一緒に授業に参加し一日お世話係となるバディ、交流会の司会やクイズショー出演者、学校紹介プレゼンテーションや英語コント、入場の際の花アーチ、プレゼントとなる折り紙やポスター作成のスタッフなど、最終的には全校生徒の3分の2の生徒が、何らかのボランティアに関わることとなった。このような体験をしてしまったら、生徒はもはや「なんで英語を学ぶの」とは言わない。目の前のオーストラリアのその子が言うことをわかりたい、こちらの伝えたいことをどうにかして英語で伝えたい、というフェイズへと、瞬く間に達してしまう。やはり、本物はすごい。中学生の学ぶ力ってすごい。本物の力、直接交流の圧倒的なパワーを日豪の子どもたちから見せつけられる交流会となった。そして終学活の頃には、各クラスに散らばったSLSS生徒は、昨日までの「オーストラリアの子が来る」ではなく、「ケイトリンが」「トラヴィスが」というように、一人ひとり向き合うべき大切な存在へと変容していた。それは本校生徒同士にも言えることで、この交流体験を通して生徒たちは、自分を含む多様性を尊重することの大切さを学んだようである。
4.成果と課題 「為すことによって学ぶ」
【生徒感想より】
- 人と関わることは楽しい!と思った。
- 歌詞を覚えて、みんなで一緒に大きな声で歌を歌ったのがすっごく楽しかった。
- 2年生の英語コントで一緒に大爆笑した。異国の文化に興味をもつきっかけになった。
- スクールバディをしたり、放課後に交流会の準備や練習をしました。外国人との関わりをもって学べたことがたくさんあってよかった。
- オーストラリアの生徒を桜中のみんなで歓迎して迎えることができました。この経験を生かして、積極的に外国から来た人と話をしてみたいと思いました。
- クイズショーのボランティアに参加しました。言葉は違っても、楽しめることは同じなのだとわかりました。英語はまだまだ分からない言葉が多いけど、伝えたいという思いがあれば伝わるのだとわかりました。もしまた機会があれば、もっとうまく話せるよう、英語をしっかり学んでいきます。
- 英語を使って、日本で困っている外国人を助けたい。私もホームステイしてみたい。
- 人を学校に招くときにボランティアで携わるのは、良い気持ちになると思いました。オーストラリアの子たちが一生懸命日本語で話しているのを聞いて、心が温かくなりました。日本語を勉強してくれてありがとうと思いました。
- 交流会の時、私は花のアーチをやりました。オーストラリアの子たちが通るときに、Helloと言ったら、言い返してくれて、とても嬉しかったです。
- プレゼントする折り鶴や兜を作って準備した。喜んでくれて、嬉しかった。楽しかった!
- 人に楽しんでもらえるのはこんなにも嬉しいことなんだなと思いました。
保護者と地域の協力を得てのホームステイを含め、SLSS来校に関する今回の一連の取り組みは、日豪生徒にとって「言語学習には人ありき」ということを体験的に学ぶ機会となった。「人」「文化」「思い」を通すことで、机上のものだった英語学習は立体的なものとなり、生徒たちは「学びの当事者」となった。
なぜ英語を学ぶのか、学校で何を体験しそこから何を学びとるのか。その答えは生徒一人ひとり違うが、それぞれが「学んでよかった」、「コミュニケーションは楽しい」、「英語が通じて嬉しい、人の役に立てて嬉しい」、と思える機会を持たせたい。今後は、次なる目標を子ども自身が自ら設定していける、そのような「自律した学習者」としての生徒育成が課題である。そのためのヒントやエネルギーを与えられるような授業・教育活動を、今後も仲間とともに展開していきたい。

