立場が人をつくるとは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #22

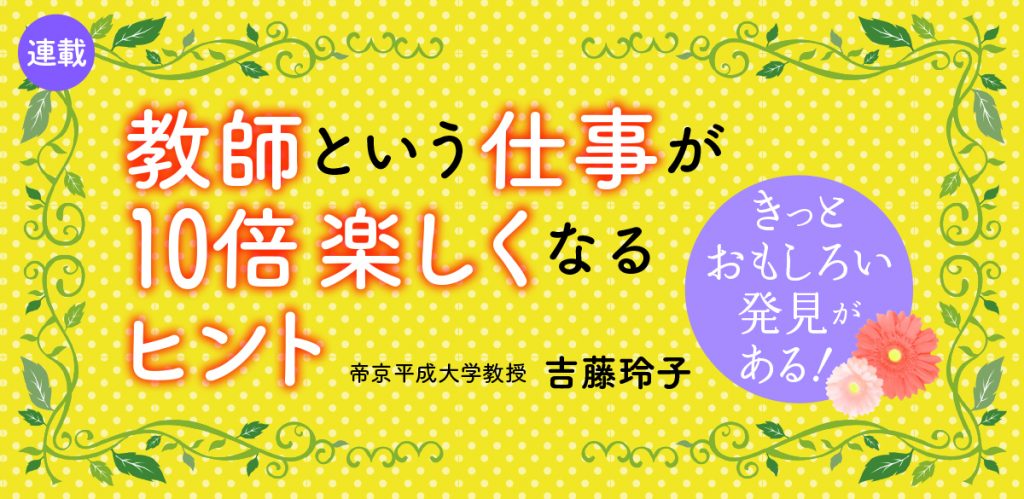
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの22回目のテーマは、「立場が人をつくるとは?」です。教員もある程度経験を積むと、「主任教諭の試験を受けないか」「指導主事の試験を受けないか」「副校長を目指さないか」などいろいろと管理職から言われることが増えていませんか。これ以上忙しくなるのは容赦願いたい、管理職は無理だと思う人もいるでしょう。吉藤先生もその1人でした。でも結果として副校長、校長となって最後はよかったとのことです。管理職試験を勧められて悩んでいる方、ぜひ今回の記事を参考にして、新しい世界のチャンスをつかんでください。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
自分の経験から
20代後半から30代前半で結婚し、その後、数年して出産、子育てと続く女性教諭を数多く見受けます。私もそうでした。東京都の場合は、8年間勤務すると主任試験を受けることができます。ライフステージを考えれば、できれば、主任試験は早めに受験しておくとよいでしょう。管理職の道を進むか、教科指導を究めて指導教諭の道へ進むか、いずれもそのときに主任教諭の資格が必要です。育休中でも試験を受けていた女性教諭もいました。主任教諭になると他地区で行われている公募採用などにも応募できますので、資格として取っていてもよいと思います。
私の場合、夫も教員でしたので、夫が指導主事や管理職になればよいと思っていました。しかし、夫は「子供たちと授業をしているほうが楽しい」と言って、なかなか管理職試験を受けませんでした。そうこうするうちに、自分も試験を受けることができる年齢になり、夫が受けないなら受験してもよいかぐらいの気持ちで挑戦しました。学校経営にも興味があったので、自分にとってはちょうどよいタイミングでした。夫も私の後に、管理職試験を受験しました。皆さんも試験を受けようか迷う時期があると思います。人によってタイミングは違いますが、私は、新しい世界への挑戦にもなるので、一歩踏み出して管理職試験を受けることを勧めます。

OJTの仕事を通して
教員も経験を積むと、主任教諭でなくても○○主任という名前の付く仕事に従事するようになります。当然、責任ももたされます。若手の指導もしていかなくてはなりません。今は、若手だけでなく、中途採用でも多くの教員が入ってきますから、自分より年上の人の指導をしなくてはならない場合もあります。指導教諭になると、新規採用教員(以下、新採)の授業や子供の生活指導、学級経営なども見ていきます。
私が主幹教諭のときでした。自分と3歳ぐらいしか変わらない社会人枠の新採の指導を担当することになりました。社会での経験が豊富なその先生は、学校経営上のいろいろなことを私に聞いてきました。そのときに、管理職が言っているからでなく、自分として学校の教育目標をどう具現化していくか考え、実践していくことの大切さを学びました。学校目標に沿った今年の重点課題や担当学年の留意する点などを確認していくと、それはおのずと学校経営の視点につながります。もし、皆さんも「自分が学校全体のことを考えるようになった」と思ったら、それは管理職試験に一歩近付いていることなので、どんどんその意欲を進めてほしいと思います。

