インタビュー/片山敏郎さん|「六つの時短の取組を進めながら、教職員と子供のwell-being実現を目指す【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは④】

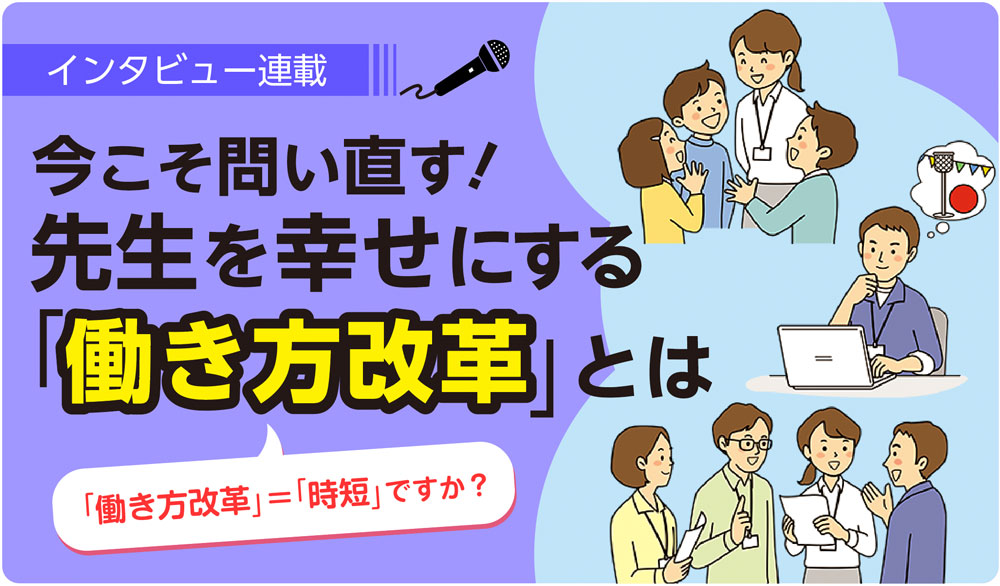
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載第4回は、新潟市立大野小学校校長の片山敏郎先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
片山敏郎(かたやま・としろう)
新潟市立大野小学校校長。小学校教諭として新潟県内の公立小学校、新潟大学教育学部附属新潟小学校等に勤務し、新潟市教育委員会学校支援課指導主事を経て、2023年4月より現職。長年、情報教育主任を務め、新潟市を中心に情報教育の推進に力を注いできた経験を生かし、小学校で教育DXを推進中。日本デジタル教科書学会副会長でもある。

目次
時短のために進めてきた六つの取組
「働き方改革」の目的は、教職員と子供のウェルビーイング(well-being)を実現していくことだと考えています。そのためには教職員の働く時間を減らすだけではなく、やりがいや技術、充実感を高めることが重要です。様々な工夫によって生み出した時間を使って、教職員がやりがいや技術を高めていくこと、教育活動の質を高めていくこと、その両方を充実させることによって、子供のwell-beingを高めていくことにつながるからです。
当然、この目的を達成するためには、時短(勤務時間の短縮)は欠かせないものです。教職員が時間に対してコスト意識を高め、仕事の優先順位をつけるなどして時間を大切にしながら効率よく働くのは必要なことだと私は思っています。
普段から残業することを前提にパフォーマンスを保っている先生の場合、学級や仕事がうまくいっているときはそれでもよいのです。しかし、生徒指導上の問題が起きたり、保護者との関係性が崩れたり、業務が立て込んだりしたときに、残業時間をさらに増やさないと乗り越えられなくなります。普段から長時間勤務で疲れている人にはその余力がありません。そのため、判断を誤ったり、体調を崩したりしてしまうのではないでしょうか。実際に、「残業時間の多い職員は体調を崩しやすい」と、これまでの経験から感じています。
ですから、余力をもってもらうために当校では時短を進めています。具体的には、以下の六つのことを行っています。
①教育DXの徹底
連絡をフルデジタルにして、いつでもどこでも仕事ができる状態をつくっています。それにより、打ち合わせのために集まる時間や、そのための資料を印刷する時間を削減できました。情報の受け手のほうも、自分のペースで情報を確認できるので、隙間時間を有効に使えますし、心理的にも多忙感が減るのではないかと思います。
②校時表の見直し
水曜日を4時間授業にして、「ウェルビーイングDay」としました。水曜日の放課後には会議を入れないようにして、各教員が自分の判断で使える個人裁量の時間としています。それと同時に、休み時間や掃除の時間などを見直し、他の曜日も子供たちは昨年度より約25分早く下校できるようにしました。このような小さな工夫を積み重ねた結果、昨年度よりも週当たり3時間半多く、勤務時間内に教員が校務をする時間を生み出すことができました。
③行事等の見直し
運動会を半日にする、陸上の朝練習を廃止する、陸上記録会に向けた練習の回数を見直すなど、持続可能な方向に行事等を減らしました。
④研修による教職員のスキルアップ・力量形成
教職員が仕事を効率よくこなせるようになれば、結局、時短になります。生成AI研修、ICT研修など、教職員の力量形成につながる研修を組織的に実施し、時間を効率的に使って仕事をする能力を高めています。
⑤解錠時間と施錠時間の設定
基本的に朝は7時に解錠し、帰りは18時30分には施錠をします。水曜日は「ウェルビーイングDay」ですので、17時15分に施錠します。これは、やる気があって際限なく働いてしまう人が出ないようにするためでもあります。
ただし、どうしても必要な場合は、管理職に申し出れば残れることになっています。実際には、生徒指導上の問題が起きたときなどは、施錠時間が19時になることもあります。
この取組を始めたのは2023年度からです。1年目には「これでは仕事が終わらない」と不満の声も聞かれましたが、2年目の今年度は全員が時間内に仕事を終えられるようになりました。
⑥保護者や地域の理解を得る
当校では「教職員のwell-being実現のための八策」を掲げ、学校教育ビジョンに明示して、保護者や地域にも示しています。それにより、「働き方改革」への理解を得たいと考えています。
●教職員のwell-being実現のための八策
1 安心・安全で向上的な職場の支持的風土の醸成
2 人材育成
3 授業力向上重視
4 教育DXの推進
5 ゆとりとリズムを生み出す校時表と裁量時間の設定
6 計画的な研修と学年・学級担任裁量時間の保障
7 解錠・退勤時間の設定
8 業務負担の均等化とミッションの設定
時短の取組によるよい効果は?
これらの時短のための取組の主な効果を二つ挙げておきます。一つ目は、この1年半、欠員が出ていないことです。私が当校に着任して1年半になりますが、現在まで心の病気での療養休暇による欠員は一人も出ていません。もちろん、「働き方改革」だけで防げるものではありませんが、主要な要素の一つではあるとは思っています。もしも誰か一人が体調を崩して療養に入ってしまうと、その人の穴を埋めるために他の教員の負担が増えますので、校内の仕事のバランスが崩れていきます。それを防げたのは大事なことだと思っています。
二つ目の効果は、水曜日の「ウェルビーイングDay」のおかげで、教員が余裕をもって仕事ができるようになったことです。子供たちは午前中までで帰りますから、午後は研修を入れたり、個人裁量の時間にしたりしています。子供も喜んでいて、「水曜日は早く帰れるから、いっぱい遊べてうれしい」という声が聞かれます。
放課後に校務をする時間がない中で管理職が「早く帰ろう」と言えば、教員には不満がたまります。現実に昨年度は「早く帰ろうね」と声はかけるものの、勤務時間内に校務を行う時間が足りない状況でした。しかし、今年度はその反省から校時表を見直し、行事も減らし、個人裁量の時間を増やしましたので、不満の声は聞こえてこなくなりました。
ただ、保護者や地域の理解を得られているかという点では、課題は残ります。前述した「教職員のwell-being実現のための八策」をHPで公開するなどして理解を得る努力をしてきましたが、例えば、「運動会を1日開催にしてほしい」などの声が出てくることがあります。行事の精選は、熱中症予防や子供の多様化への対応、カリキュラム・マネジメントなど、様々なことを考慮して行っているのですが、「働き方改革」のためと教員のためにのみ行っていると誤解されないよう、情報発信と対話が大切だと考えています。

