インタビュー/山田洋一さん|「働き方改革」を達成するために管理職が重視すべきなのは、職員室のコミュニケーション【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは②】

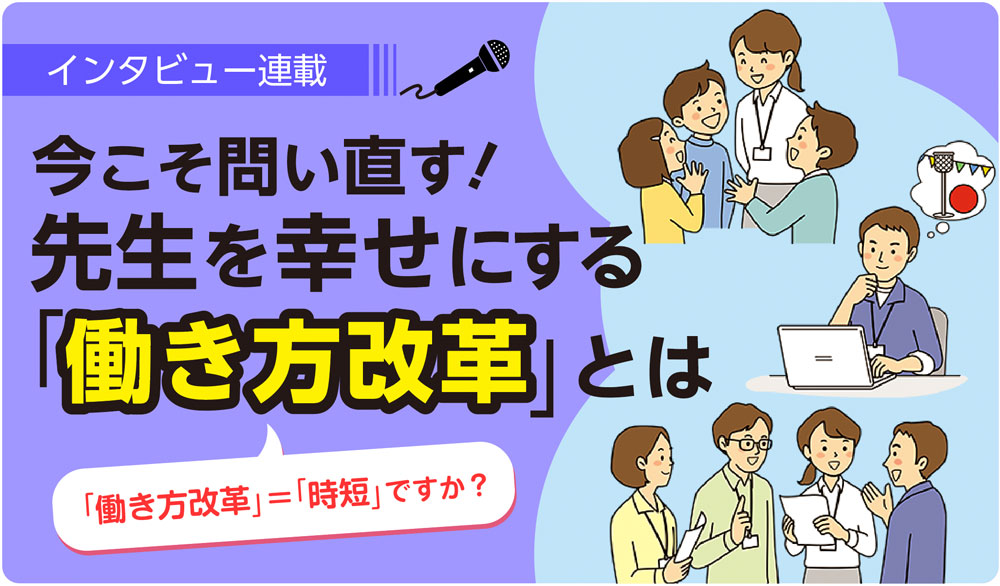
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載2回目は、北海道公立小学校教諭 山田洋一先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
山田洋一(やまだ・よういち)
1969年北海道札幌市生まれ。北海道教育大学旭川校卒業。北海道教育大学教職大学院修了(教職修士)。2年間私立幼稚園に勤務した後、公立小学校の教員になる。教育研修サークル「北の教育文化フェスティバル」代表。日本学級経営学会理事。公認心理師。『人間関係の「ピンチ!」自分で解決マニュアル』(小学館、2024)など著書多数。

目次
時短のメリットとデメリット
現在、時短の徹底ぶりは学校によって異なり、「早く帰れ」と管理職にうるさく言われる学校もあれば、そうでもない学校もあります。それでも、教育界全体で「働き方改革」に取り組んでいることで、多くの学校の職員室に「早く帰ろう」という雰囲気が生まれ、以前より圧倒的に帰りやすくなりました。「まずは時短をしましょう」という感覚が教員の間に根付いたのではないかと思います。
例えば、現任校では同じ学年の先輩の教員が残っているから若手は帰りにくい、ということはないですし、教頭が毎日最後まで残っていることもありません。家庭にいろいろな事情がある教員たちについても、「みんなが多様な働き方をしていいのだ」という考え方が広まりましたので、朝はわが子を保育園に送り、帰りも迎えに行くために早く帰る人もいます。周囲の教員たちも、早く帰る人が同じ学年にいる場合は、みんなで話し合った方がいいことを絞り込んで、その人がいるうちに話すなどの配慮をしています。少なくとも私の周りでは、早く帰ることへの罪悪感、多様な働き方をすることへの罪悪感はほとんどなくなっているように思います。これは本当によいことです。
ただ、時短によって失われたものもあります。やらなくてはいけない業務があって、その量は物理的に変わらないのです。そうすると、早く帰るために何の時間を削るかというと、管理職と教員、教員同士のコミュニケーションの部分です。職員室で雑談をする時間が減りました。以前だったら、仕事をしながら「ちょっと疲れたな」と感じ、休憩をしようと思って職員室でお茶を飲んでいるうちに、同じ学年の先生とおしゃべりが始まり、気が付けば30分経っていて、あわてて仕事に戻る……のようなことがありましたが、それはなくなりました。
よく管理職は「困ったことがあったらすぐに報告や相談をしてください」と言いますが、短い、ちょっとしたおしゃべりの先に、報告や相談があるのだと思うのです。普段から話をしない人にいきなり深刻な報告や相談はしにくいものです。コミュニケーションが減ったことで管理職に報告や相談をしにくいと感じている教員もいると思います。
それから、時短の推進によって自分の仕事を早く終わらせることが最優先になりましたので、 他の人の働きぶりや働き方に目が向かなくなり、悪しき個人主義になりやすくなったと感じます。特にパソコンが普及してからは、みんな画面を見て仕事をしていますから、他者に気を配ったり、変化に気づけたりすることが少なくなりました。
「教員の変化」を忘れてはいけない
今後も「働き方改革」を進めていくにあたって、考慮すべき点を指摘しておきたいと思います。それは、教員になる人たちに変化が起きていることです。今までは教員になるのは、自分の人生と仕事の境目がなくて、教師として生きることを自分の喜びとし、生きがいだと感じている人が多かったと思うのです。
しかし、 おそらく今の「働き方改革」が目指しているのは、学校をそういう感覚ではない人でも働ける職場にすることだと思うのです。学校は「『働き方改革』で働く時間が短くなりました。コンピューターが入って仕事が効率化されたので、誰でも働けます」とアピールして人を集めているからです。「流動性が高い」とはそういうことだと思うのですが、私たちの感覚からすると、今までだったら教員にならないような人、つまり、それほど教育に興味のない人が教員になって学校現場に入ってきているという印象を受けます。
例えば、保護者から勤務時間外に電話がかかってきたときに、担任に「〇〇さん、Aくんの保護者から電話が来ていますよ」と伝えたとします。
自分の人生と教師という立場の境界線を曖昧にして生きてきた私たちの世代の感覚では、勤務時間外だろうが、それは教師の仕事だと思ってこのような電話に出てきました。もしも出ない教員がいたとしたら、「あの人は教員としてはダメだよね」と心の中で思ってきました。
ところが今は、そう言われたら時計を見て「勤務時間外なので出ません」と言える人たちが現れてきています。しかも、「働き方改革」の下では、断ることが「正しいこと」になったのです。
保護者が多様で、子供も多様なのと同時に、教員の側も多様になりつつあります。これまで学校は、教えることが得意で、社交的で、子供が好きで、教育のためだったらすべてをかけてもいい、そんな人たちが教員をしていることが前提で、運営されてきたわけですが、その前提が崩れることになります。
ですから、教師という仕事に対する感覚が違う人たちも含めて、どうやって学校を運営していくかが今後の課題になると思います。今までは、新しく入ってくる人たちを今の学校文化に染めようとしてきましたが、その結果、不適応を起こして辞めていく人が出てきています。そうではなく、受け入れる側が変わらなければいけないのではないでしょうか。システムはもちろんですが、働いている人たちのメンタリティまでともに変えていき、学校が多様な教員を受け入れていくための土壌づくりも「働き方改革」と同時に進めていかなければいけない気がします。

