子供を見る目を鍛える|全員を見取る仕掛けと声かけ
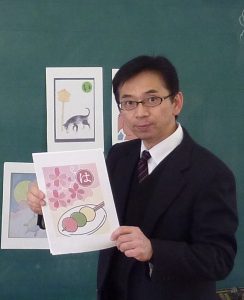
「子供たちを『見る』ために、毎日していること」「場面場面で気になる子の見取りとアプローチ」「子供を見る目の鍛え方 若手へのアドバイス」といったテーマで、百戦錬磨の実践者、福山憲市先生が実践する仕掛けと具体例についてご紹介します。
執筆/山口県公立小学校・福山憲市
ふくやまけんいち●1960年山口県下関市生まれ。広島大学卒。「ふくの会」というサークルを30年以上継続しており、「ミスをいかす子どもたちを育てる研究会」も組織している。著書は『スペシャリスト直伝! 学級づくり“仕掛け”の極意』『20代からの教師修業の極意』(ともに明治図書)等、多数。
関連記事
・子供を見る目を鍛える|いつ、どこで?~5つの場づくりと3つのポイント はこちら
・子供を見る目を鍛える|定点観測+集団分析!2面作戦 はこちら

目次
朝の時間に、子供たちの日々の微かな変化を感じる
自分の姉と妹は、看護師です。自分が20代の時、こんな質問をしたことがあります。「患者さんの様子を見るために、日頃から気を付けていることある?」
ちょっとした見逃しが、命に直結している仕事です。それだけに、どんなことに気を付けているのかが気になったのです。二人のやっていることは、全くと言ってよいほど同じでした。
① まず、顔を見る。表情、目、唇、色、息遣いなどをチェックする。
② 会話する。ちょっとした質問をした時の、受け応えの様子をチェックする。
③ 体温・脈・食事の様子などをチェックする。
わずか数分の触れ合いだけれど、自分が決めたポイントでさっとチェック。それをすぐに記録する。記録を欠かさないと言うのです。記録があるから、微かな変化に敏感になれると言うのです。
この姉と妹の言葉が、自分が子供たちを「見る」ために毎日していることにつながっています。まずは、朝、可能な限り子供たちより早く、教室に行くということです。それは、教室に入ってくる子供たちの様子をしっかりと見るためです。
・教室に入って来た時の目線、顔つき
・服装の様子
・挨拶の声
・机の中に学習道具を入れる時の様子
・ランドセルの片付け方
・友達との会話の様子
など、ちょっとしたことですが、子供たちの様子を見ています。感じています。さらに、ちょっとした会話を子供たちと楽しみます。子供たちの言葉から、目に見えない心を感じるようにしています。
「昨日、いいテレビ番組あった?」
「今、はやっているアニメって何?」
「今、何か集めている?」
「昨日の晩ご飯、好きなもの出た?」
こんな他愛もない言葉をかけて、会話のきっかけにしています。授業中とは違う子供たちの一面を、見たり感じたりすることができます。続々と子供たちが集まり始めると、プリントや自学などが提出されます。その時も、声かけをします。
「今日の自学のテーマいいねえ。ここの部分、もう少し調べるといいなあ。やってくれる?」
「いい字、書くなあ。さすが!」
「プリント揃えてくれて、ありがとう。助かるなあ~」
など、子供たちの表情などを感知しながら声かけをしています。こんな朝の時間を続けるだけでも、姉や妹が、患者さんと接していたような「日々の微かな変化」を感じることができるようになります。子供たちを「見る」眼が鍛えられていくのを実感します。
帰りの時間に、子供たちの成長・変化を思い出す
さらに、こんなこともしています。毎日の授業のノートは、必ず集めるということです。例えば、国語・算数・社会・体育・図工・音楽という日課なら、国語・算数・社会のノートを必ず集めます。ノートは、子供たちとの対話の元になると思っているからです。必ず「ひと言」書いて返します。「うん、いいノートだ!」これだけのこともあります。時間がある時は、たっぷり書いて、多くの場合、その中に質問を書き入れます。「今日の勉強、分かった?」「いい発表するけど、よく本読むの?」などと、ノートで子供とやりとりをしています。ここでも、次々と子供たちの新しい一面を感じることができます。
朝にすることは前述しましたが、一日の学校生活の終わりにしていることもあります。それは、一人一人の成長・変化を感じる時間を持つということです。まずは、教室を軽く整理整頓します。一日の締めくくりです。明日の朝、気持ちよく子供たちを迎えることができる教室になっているかどうかを簡単に確認します。ごみ一つない教室か、学びの環境になっているかを見ます。その後、一人一人の机の上をきれいな雑巾で拭きながら、それぞれのことを思い出しています。
・今日、どんな様子だったか。
・授業中、どんな発表をしたか。
・掃除時間、ボランティアタイムなどの時、どんな動きをしていたか。
などを、机の上をきれいにしながら思い出しています。思い出せなかったら、その日はその子と関わっていないということになります。見ていないということです。
ちなみに、この子供たちの成長・変化の思い出しは、家に帰ると、一人一人の記録・変化としてエクセルに打ち込んでいます。記憶は消えます。記録したことは、読み直すことで思い出すことができるからです。記録をする時は、生活面・学習面に分けて打ち込んでいます。自分自身が、どちらにウエイトを置いて子供たちを見ているか、記録したものから分かります。バランスよく見ていない時は、記録の少ない方の視点で、意識的に子供たちを見ることもしています。
ところで、時には「共育カード」というものを作成することがあります。これは、保護者に「子供の微かな成長」を書いてもらうものです。
・初めて料理を手伝った。
・敬語を上手に使えるようになった。
・アイロンのかけ方がうまくなってきた。
どんな些細なことでも教えてほしいとお願いし、書いていただいていました。もちろん、書いてくださった保護者に、お礼のカードを渡します。そこに、さらに教えてほしいと付け加えます。
自分の知らない子供たちの家での様子を知ることで、子供たちを見る目が変わります。まだまだ見ていない、気付いていないという気持ちで、一人一人に接することができます。こんなことを何十年もしている自分です。

