提言|玉置崇 大学、教育委員会、学校が今、すべきことは? 【緊急検証! 教員のなり手不足問題、私はこう考える! #1】
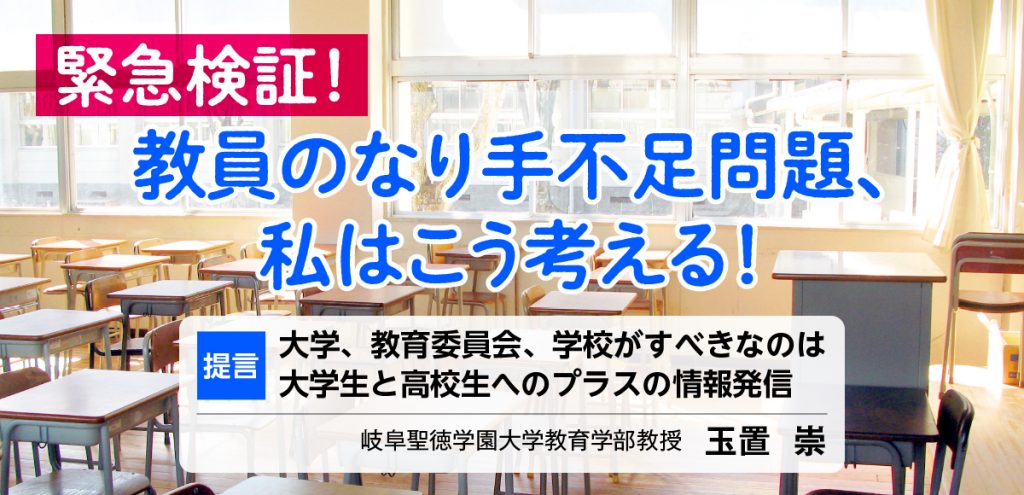
教員のなり手不足問題は深刻であり、日本の学校にとってその解決が目下の急務です。現在、文部科学省が進めている働き方改革や給特法に関する議論は確かに重要ではありますが、果たしてそれだけで解決となるでしょうか。教育関係者がその他にできること、するべきことは何かを考える7回シリーズの第1回目です。大学、教育委員会、学校が今すぐにすべきことは何でしょうか。元中学校の校長で、県教育委員会での勤務経験もあり、現在は教員養成系の大学で大学生を指導している岐阜聖徳学園大学の玉置崇教授に話を聞きました。
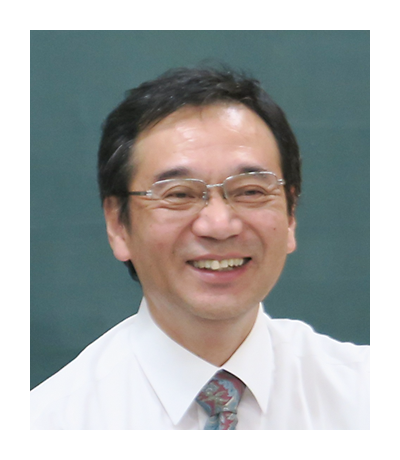
玉置崇(たまおき・たかし)
1956年、愛知県生まれ。公立小中学校教諭、国立大学附属中学校教官、中学校教頭・校長、県教委主査、教育事務所長などを経て、2015年4月より現職。教員養成に精力的に取り組みながら、文部科学省「校務におけるICT活用促進事業における事業検討委員会委員」などを歴任し、現在は岐阜市教育振興基本計画検討委員会委員長、デジタル庁デジタル推進委員でもある。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全7回予定)
●提言|玉置崇 大学、教育委員会、学校が今、すべきことは?(本記事)
目次
教員養成系の大学がすべき二つのこと
教員のなり手不足問題を解消するためには、教員養成系の大学、教育委員会、学校、それぞれが今すぐに行動を起こす必要があると感じます。特に、私がご提案したいのは情報発信です。そもそも「学校はブラックだ」と広く知られるきっかけになったのは、2021年に文部科学省がTwitterなどで始めた「#教師のバトン」プロジェクトだと思うのです。「無制限働かせ放題」などとマスコミに書かれるようになり、あたかも全国のすべての教員が毎日つらい思いをしているかのような、ネガティブなイメージが定着してしまいました。しかし、教員の仕事はつらいことばかりではありませんし、実際に早く帰っている教員もいます。仕事にやりがいを感じている教員もいます。ですから、ネガティブな情報ばかりの報道には疑問を感じます。
このような現状を変えるために、まず、教員養成系の大学が行ってほしいことは二つあります。一つ目は、教師という職業の素晴らしさを大学生に伝えることです。そういうと「美談でごまかすな」などの声が聞こえてきそうですが、あえてこのことが必要だと思うのは、今の学生たちは、教師の素晴らしさを知る前に「ブラックであること」を知り、教員になることを避けようとする現実があるからです。
私は大学で、1年生の教師論の授業を担当しています。授業の中では菊池省三さんなど、著名な方の授業のDVDを見せるのですが、それを見た学生たちは「教師って素晴らしい仕事ですね」と感動するのです。教育学部以外の学生もこの授業を受けているのですが、「教育学部に入り直そうか」と考える学生も出てくるほどです。
なぜ、教師という仕事の素晴らしさを知らずに、学生たちは教員養成系の大学に進学してきたのかと不思議に思う方もいることでしょう。私の大学では、教員採用試験を受験する学生のために面接の練習を行っています。その際に、志望動機を尋ねると、ほとんどすべての学生が「素晴らしい先生と出会ったから」と答えます。つまり、学生たちの多くは、素晴らしい先生の存在は知っていますが、教師という仕事の素晴らしさを実は知らないのです。このような学生たちに、まずはそれを伝えることが大学にとって一番大事なことだと思います。
そして、大学でそれができるのは、実務者教員です。文部科学省は、大学教員のうち2割を実務者教員にするという方針を出していますが、それは必要なことです。もちろん、教師の仕事には苦しさもあるわけですが、それでも子どもから人生の恩師として慕われることもある素晴らしい職業なのだと、リアリティをもって学生に話せるのは、学校で実際に働いた経験がある実務家教員でしょう。
教員養成系の大学で行ってほしいことの二つ目は、現場に学生を連れていったときにきちんと価値づけをすることです。今は各大学で1年生から様々な学校体験活動を行っていますが、体験したことに対して大学の教員が価値付けをしないと、表面しか見ていない多くの学生は、教師のすごさに気づけないからです。例えば、ある子どもが泣いていたけれど、担任の対応によって泣き止んで元気になったとします。その様子をぼーっと見ているだけでは、いろんな子どもがいて担任の先生は大変だな、と感じるだけで終わってしまいます。その場面に対して「担任の先生はああいう風に対応したから、あの子は元気になったんだよ」と価値づけをして、その担任の指導の背景にある思い、長い目で見て子どもをどんなふうに育てようとしているのか、どんな点に配慮しているのか、子どもの変容がどんなにうれしいことか、などを学生に伝えてほしいのです。これも実務者教員だからこそ、できることだと思います。
教育委員会が情報提供をする際の二つのポイント
続いて、教育委員会にお願いしたいのは、高校生や大学生に向けて、必要な情報を上手に提供することです。ポイントは二つあります。
一つ目は、県や自治体の教育の特徴と、実際に働いている先生をセットで紹介することです。例えば、本県では授業中にICTをこんな風に子どもたちが使っていますなどと、県の教育の特徴を捉えて伝えつつ、こんな先生がいますと実際に働いている2、3年目の教師の仕事ぶりを伝えてほしいです。そのうえで、本県で働きませんかと、待遇面で他県に比べるとこのような配慮をしていますとアピールするのです。最近は、教員志望者の目を意識して 給料や待遇などの情報を強調する教育委員会が多いのではないかと思います。それはもちろん必要ですが、その前にまずは魅力です。これから教員になろうとする人が、自分が教員になって2、3年後の姿をイメージできるような、自分も先生になってこの県の教育をしたいと思えるような情報を提供することが重要です。
二つ目は情報の出し方を工夫することです。最近では、多くの教育委員会が採用説明会を行っていますので、大学生は、複数の県や市の説明会に参加しています。とても興味深いエピソードがありましたのでご紹介しますと、私のゼミの3年生が、A市教育委員会の説明会と、B県教育委員会の説明会に行きました。そして、「私はA市に魅力を感じました」と言うのです。理由を尋ねると、「A市では、初任者は週1回研修が受けられて、新学期が始まる前の春休みにも、事前の研修が受けられるからです」と答えました。週1回の新人研修も、春休みの事前の研修もA市だけが行っているわけではなく、B県でも行っています。つまり、やっていることは同じでも、伝え方が違うと、学生の受ける印象が全く違うのです。やはり、PRの仕方が大事なのです。
大学生はあまり情報を持っていませんから、教育委員会は丁寧に、より働きやすいイメージが描けるような説明を心がける必要があります。1、2年目の新人には手厚く指導しますと、指導体制をアピールすることも重要です。それをしないと、説明がまずいために、居住している県ではなく、他県の教員になってしまう可能性があります。
それから、この他にも県や自治体の教育委員会にお願いしておきたいことがあります。それは必要な人員を配置して、教員が働きやすい環境を整えることです。正規の教員の数が足りないなら、講師やボランティアなどの体制を整え、そのことを情報発信してはどうでしょう。それにより、教員志望者が集まりやすくなるのではないかと思います。もちろん、人の確保は簡単にできることではありませんが、人手不足によって疲弊する現場を救うためにもぜひ取り組んでもらいたいことです。

