「義務標準法」の見直しを中心に、予算をかけた働き方改革を【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #02】
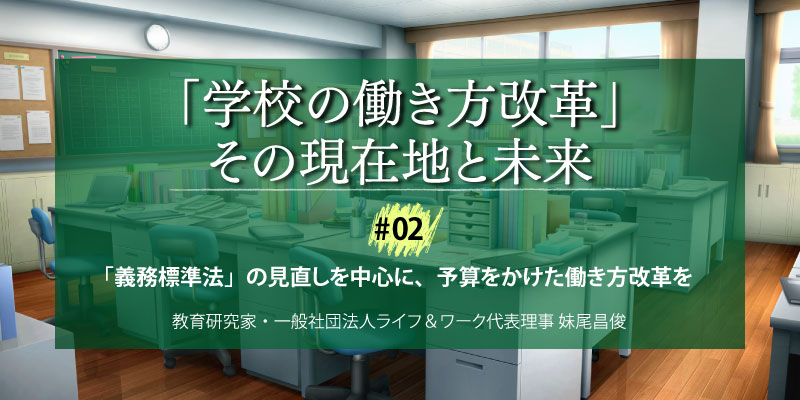
2016年に実施された教員勤務実態調査の結果を受け、行政が進めてきた学校の働き方改革。果たして、今日に至るまで前進したといえるのか。また、教師の負担軽減のために今、とるべき策は何なのか。中央教育審議会・働き方改革特別部会委員を務めた妹尾昌俊氏に話を伺った。

教育研究家・一般社団法人ライフ&ワーク代表理事
妹尾昌俊
徳島県出身。野村総合研究所を経て独立。教職員向け研修などを手がけ、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた。主な著書に『変わる学校、変わらない学校』(学事出版)、『「先生が忙しすぎる」をあきらめない』(教育開発研究所)、『教師崩壊 先生の数が足りない、質も危ない』(PHP研究所)、最新著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』(教育開発研究所)など。
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の2回目です。記事一覧はこちら
目次
「学校の働き方改革」はどれくらい前進したのか
文部科学省が学校の働き方改革を本格的に進めるようになった契機のひとつが、2013年にOECDが行ったTALIS(国際教員指導環境調査)です。その調査で、日本の中学校の教員が世界一忙しいということが明らかになりました。その後、2016年に文部科学省が行った教員勤務実態調査でも、小・中学校の教員の平日1日当たりの在校等時間が11時間を超えるなど、かなり大変な現場の状況が結果として表れました。その頃、民間企業での事件もあって社会的に働き方改革が盛り上がったことも政策の後押しとなったかと思います。その後、部活動ガイドラインの策定や、勤務時間の上限に関するガイドラインの策定など、一部の改善は行われてきました。
各自治体でも、2017~2018年くらいから、働き方改革に向けての動きが活発になってきました。ただその矢先の2020年、コロナ禍による急な休校で様々な対応に追われ、働き方改革が停滞してしまった現場もあったかと思います。学校再開後はまず教科書を終わらせないといけないということで、働き方改革どころではない、と考えた校長先生もいたようですし、「働き方改革とは何をしたらいいのか、現場でやれることはもうない」という感覚をもつ現場も多かったようです。そのような中で、だんだんトーンダウンしていったところもあるのではないかと思っています。
2022年に教員勤務実態調査が再び行われ、2023年4月にその速報値が発表されました。その結果、小・中学校の教師の1日あたりの在校等時間が、前回の2016年調査より30分ほど減っていることがわかりました。この結果を、働き方改革の前進と捉えるか、たった30分の短縮で前進とは言えないと感じるかは、人によって評価が分かれると思います。
よい面としては、2016年にはタイムカードすらなかったような労務管理は改善されましたし、遅くまで残ることが熱意の表れという学校文化も、働き方改革の名のもとで変わってきた部分があると思います。留守番電話の導入や会議時間の短縮、業務支援員さんに来てもらうなど、学校間の差はありますが、先生の負担を減らすにはどうすればよいか、考えられるようになってきたのではないでしょうか。
一方、GIGAスクール構想による1人1台端末の配付によって、先生たちの負担がむしろ増えているという実態もあるかと思います。端末の配布自体にはよい点がたくさんありますが、機器の点検・補修や、いじめにつながる書き込みの対応などの仕事も増えました。さらに、学習指導要領も改訂されるたびに先生に求められることが高度化し、増えていますから、授業・授業準備の本務も相変わらず大変です。そのため、数字としては30分減ったけれども、大きく改善したという実感はもてない先生の方が多いのではないかと思います。
この速報値の分析で明らかなのは、学校行事に関する業務時間が減っているということ。それが30分減ったことの大きな要因となっているため、コロナが5類に移行したことで、学校行事が復活すると勤務実態がまた厳しくなる可能性があります。また、あくまで30分減ったというのは全国の学校の平均値ですから、この数字ではわからない過酷な状況の中働いている先生もいるはず。働き方改革として一部前進したのは確かですが、十分とは言えない現場も多く、決して楽観視はできない状況です。
給特法さえ廃止すれば、働き方改革が進むとは言えない
ここ数年、文科省は給特法の見直しに関して、2022年の教員勤務実態調査の結果を見ながら検討するとして、先延ばしにしてきました。やっと結果が出ましたので、私も参加する中教審の特別委員会で議論することになっています。しかし、すでに自民党から、抜本的な改正はせずに教職調整額を上げることで対応する案が出されています。働き方改革の重要性が世間に広まった2016年から2023年の現在まで、給特法の抜本的な見直しに向けての議論・検討が十分行われてきたとは言えず、先生たちの残業のほとんどが自発的なものとされ、労働とさえ見なされないというのは大きな問題です。
他方、私は、給特法を廃止にすると学校の働き方改革が劇的に進む、という意見には懐疑的です。残業代を出すには使用者の財政負担が伴うため、残業抑制に働くのではないかという見方はありますが、そもそも教育は予算があまりない中で動いているため、その分基本給などをだんだん減額していくということにもなりかねません。ですから、「残業代が発生するから業務量が減る」と教科書的に進むのかどうか、慎重に考えなければならないと思います。
もうひとつ、残業代が出るとなると、むしろ働きすぎるという人もいるわけです。今の教職調整額4%は、残業時間に比べたら少ないというのは多くの教員にとって事実ですが、月々1万数千円になる場合もありますし、退職後の年金算定にも反映されていきます。調整額を廃止し、残業代のみとなると、育児や介護で残業できない人は損をする一方、比較的制約がなく、残業できる人は、生活水準の維持のためにも長く働こうとするかもしれません。民間や国家公務員でも言われていることですが、これは働き方改革と逆行します。

