「学校の働き方改革」と「給特法」の課題と展望【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #01】
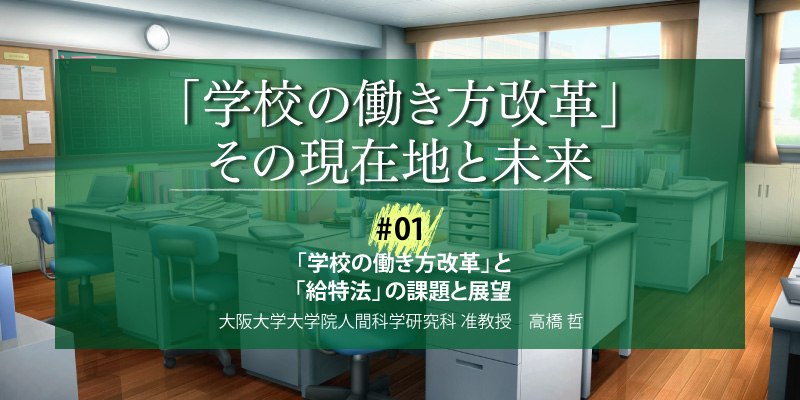
「学校の働き方改革」の議論の中で、その前提となる「給特法」の見直しも進められている。教育法学を専門とし、著書などを通じて学校の働き方改革の課題や問題点を指摘している高橋哲氏に、学校の働き方改革の現状と、その改善に向けての考えを語ってもらった。

大阪大学大学院人間科学研究科准教授
高橋 哲
博士(教育学)。コロンビア大学客員研究員(フルブライト研究員)、埼玉大学教育学部准教授などを経て2023年より現職。専門は教育法学。著書に『聖職と労働のあいだ―「教員の働き方改革」への法理論』(岩波書店)、『現代米国の教員団体と教育労働法制改革―公立学校教員の労働基本権と専門職性をめぐる相克』(風間書房)、『迷走する教員の働き方改革―変形労働時間制を考える』(岩波ブックレット)など。
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の1回目です。記事一覧はこちら
目次
「学校の働き方改革」の現状とは
2018年、2023年の文部科学省による「教員勤務実態調査」により、学校教員の働き方がいかに過酷であるかが可視化されました。それまで教員は、学校の不祥事や体罰、校則問題などを通じて社会的に厳しい目で見られていましたが、この勤務実態が明かされたことにより、過労死ラインを超える勤務時間や育児休暇が取得できないなどの厳しい労働条件が浮き彫りとなったのです。
こうした流れから、教育委員会や学校管理職に「勤務時間管理」という意識が芽生えたという意味では、「学校の働き方改革」の大きな前進であったと思います。ただ、教員の勤務実態を改善するための人や予算は増えていません。今の学校の働き方改革は、政府が責任をもたず、基本的に教育委員会と学校にお任せという形になっています。
例えば、2019年改正給特法によって導入された「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」では、公立学校教員の残業時間を「原則月45時間、年間360時間」としていますが、この義務を教育委員会や校長に課して、人も予算も十分に増やしてきませんでした。その結果、「校長ガチャ」といわれるような、校長先生次第で働きやすい環境もあれば、依然として過酷な労働条件の環境も生み出されています。2023年4月28日に発表された最新の勤務実態調査の速報値では、若干の改善は見られたものの、過酷な労働条件を抜本的に改善することには至っていません。そのため、これまでの働き方改革は有効ではなかったことが示されていると思っています。
学校自治によるボトムアップの施策を
また、「時間さえ減らせばいい」というような働き方改革をしていく中で、業務の一つ一つがおろそかになってしまい、教育そのものを大事にできないという声も聞こえます。授業の準備や、子ども一人一人に対する個別指導、保護者への対応などにしっかりと時間を割きたいと思っていても、時間が過ぎたら学校の外に出されてしまうといった「時短ハラスメント」も起こっています。
当事者の教員が教育活動として大事だと思う業務を優先して、そうではないところを削っていきたいところですが、実際の改革は教育委員会や校長によるトップダウンで決められてしまっています。このように当事者の声が反映されない上意下達の働き方改革の弊害も顕在化しつつあります。
校長が当事者の声を反映させて施策を実行すべきだという考え方もありますが、それよりも、労使自治ないしは学校自治的に決定するべきだと私は思っています。つまり、校長先生が一人で決定するのではなく、当事者である教員、場合によっては保護者や子どもたちをも含めて、学校においてどのような教育活動を優先していくのかをボトムアップによって決めていく必要があります。
現在まで続く「給特法」の問題点とは
教員の超過勤務問題は、今に始まったことではありません。戦後長らく、教員の長時間勤務や時間外労働をどうするのかという問題がありました。その結果生まれたのが「給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)」という法律です。
ご存じのように、この「給特法」は、給料月額4%の教職調整額という教員独自の給与を払う代わりに、時間外勤務に対して労働基準法に定められた超勤手当を出さないという特殊なしくみです。教職調整額の4%だけを払って、あとはいくら働いても支払いなしということで、携帯電話のサービスにたとえて「定額働かせ放題」と言われてきました。
しかしながら、給特法にはもう一つ大事なルールがあり、教員の時間外勤務は4つの業務に限るとしています。これを「超勤4項目」と呼び、具体的には、(1)児童生徒の実習や校外学習の業務、(2)修学旅行などの学校行事に関する業務、(3)職員会議などに関する業務、(4)非常災害などのやむを得ない業務としています。これ以外の時間外勤務は、原則として禁じるということになっています。
給特法ができた当時の国会審議を見てみると、教員の仕事というのは、勤務時間内であったとしても、授業がなければ学校外や自宅で行えるものもありました。しかし、それでは時間計測が正確にできないということで、量ではなく、内容によってその歯止めをかけようということになったわけです。携帯電話で言うならば、従量課金はできないが、使えるアプリは4つに限るということ。それが給特法の本来のしくみです。
ところが、今の教員の時間外業務は、この4つのアプリ以外に広がっているのが現状です。授業の準備やテストの採点、行政から下りてくる書類作成などは、超勤4項目には入っていません。また、代表的なものに部活動が挙げられます。これも超勤4項目には入っていませんが、中学や高校では、部活動の指導が時間外勤務の大半を占めています。
問題はこうした超勤4項目以外の業務をどう扱うのかということですが、文部(科学)省はこれを「自発的な行為」だと言ってきました。要するに、「校長先生があずかり知らぬところで教員が勝手に行った仕事」という解釈で、労働時間にカウントせず、そのため超勤手当も必要ないとしてきた。これが、教員の無定量な時間外勤務を生んできたということです。つまり、給特法が今の無定量な労働時間を合法化しているわけではなく、文部科学省の解釈と運用こそが諸悪の根源というわけです。このことは、給特法についていちばん誤解されている点だと思っています。
「給特法」を知る機会が失われてきている
「給特法があるから働かせ放題になっている」という指摘もありますが、そもそも大学の教職課程で給特法を学ぶこと自体がほとんどありません。教職課程においては、免許を出している以上、勝手なことをさせないようにと、文部科学省がコアカリキュラムを定めています。その中で、教職の入門にあたる「教職の意義及び教員の役割・職務内容」の科目では、教員の義務や服務については教えられるものの、本来知っておくべき、教員の労働条件や労働法上のルール、労働に関わる権利というのは、ほとんど教えられていません。
かつては学校現場に入ってから、教員組合を通じて労働者の権利や労働条件について知ることができました。しかし1970年代以降、全国的に教員組合の加入率は減少傾向にあり、現在は3割程度となっています。このようなことからも、多くの新採教員が給特法を知る機会はますます少なくなっているのです。
「給特法」によるタダ働きを前提とした自民党の改正案
2023年5月、自民党の特命委員会による給特法の改正案で、教職調整額を4%から10%に引き上げることが提言されました。しかしこの案は、「今の給特法のもとであればタダ働きをさせてもいい」ということが前提となっている点で問題だと思っています。
10%への引き上げというのも、時間外労働をどうやって削減していくのかという戦略のもとに立っていない数値です。もともと給特法の4%というのは、1966年時点での実態調査(週あたり2時間の時間外勤務)をもとにつくられた数値です。現在、過労死ラインである月80時間を超える教員は、中学校で6割いるといわれていますが、この現在の勤務実態を当てはめれば、教職調整額は10%ではなく40%にしなければなりません。10%で手を打つという法案が政治主導でつくられようとしているのは大きな問題です。

「36協定」を教育現場にも取り入れる
トップダウンの学校の働き方改革を変えていくための一つのステップとして提唱しているのが、「36協定」を教育現場に取り入れるということです。労働基準法第36条にもとづき、労働者側と、働かせている使用者側の間で、どのような仕事を時間外勤務にするのか、何時間の時間外勤務をするのかなど、業務と業務時間、対象者などについて協定を結び、お互いの合意のもとで運用していくというのが「36協定」のルールです。
その結果、発生した時間外勤務には、超勤手当を支給することが求められます。労働基準法のルールを適応しようとしたときに、超勤手当だけにフォーカスする人もいますが、まずは時間外勤務をするかどうかの労働者側の同意がなければならないという原則こそが注目されるべきです。そのルールの縛りをかけることで、時間外勤務を抑制していくことが重要なのです。
労働時間を減らすには、仕事の効率を上げるか、仕事量を減らすか、人を増やすかの3つしかありません。仕事の効率化においては、ICTの導入で紙資料を減らすなど、これまでもかなり取り組まれてきました。ただし仕事を減らすことや人を増やすことにおいては、個々の教員ではどうにもならないので、そういった意味では、個々人で努力できる範囲はすでに超えてしまっていると思っています。
できることとしては、「36協定」導入の動きを各学校でつくっていくということです。その際も、教員個々人で働きかけを行うのではなく、学校全体で今の働き方をどう変えていくのかということを考え、教員集団として動いていくことが必要です。
「36協定」では組合員が教員の過半数を占める場合には組合として交渉ができますが、そうでない場合でも、労働者の過半数を代表する者が協議を行って協定を締結できるしくみになっています。そのため、まずは自分たちの時間外勤務に合意するのか、合意するとしたらどのような内容で進めていくのかなどを、自分たちでコントロールできるようにすることが大事です。
国や行政に求められること
国や行政は、逆に学校現場へのコントロールを緩めることが必要です。各学校で子どもたちにどういう教育活動を施していくのか、学校ごとにどういうカリキュラム編成をしていくのかなど、従来よりも学校の自由度を上げていかなければなりません。教員が工夫できることや、働き方を模索していくことには限界があるので、人と予算を増やしていくと同時に、例えば現在も法規であると主張する学習指導要領の扱いなど、文部科学省が長らく行ってきた学校現場への支配を緩めることが、教員の多忙化解消の一丁目一番地だと思っています。
働き方改革が、子どもたちのために一生懸命頑張ろうとしている教員に追い風となるような改革になることを心から願っていますし、その教員たちを大切にできるような制度論を今後も考えていきたいと思っています。
取材・文/三井悠貴(カラビナ)
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の1回目です。記事一覧はこちら








