「学校の働き方改革」と「給特法」の課題と展望【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #01】
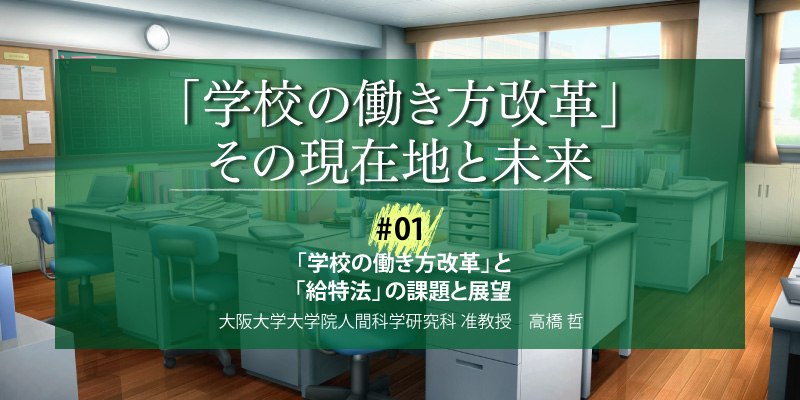
「学校の働き方改革」の議論の中で、その前提となる「給特法」の見直しも進められている。教育法学を専門とし、著書などを通じて学校の働き方改革の課題や問題点を指摘している高橋哲氏に、学校の働き方改革の現状と、その改善に向けての考えを語ってもらった。

大阪大学大学院人間科学研究科准教授
高橋 哲
博士(教育学)。コロンビア大学客員研究員(フルブライト研究員)、埼玉大学教育学部准教授などを経て2023年より現職。専門は教育法学。著書に『聖職と労働のあいだ―「教員の働き方改革」への法理論』(岩波書店)、『現代米国の教員団体と教育労働法制改革―公立学校教員の労働基本権と専門職性をめぐる相克』(風間書房)、『迷走する教員の働き方改革―変形労働時間制を考える』(岩波ブックレット)など。
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の1回目です。記事一覧はこちら
目次
「学校の働き方改革」の現状とは
2018年、2023年の文部科学省による「教員勤務実態調査」により、学校教員の働き方がいかに過酷であるかが可視化されました。それまで教員は、学校の不祥事や体罰、校則問題などを通じて社会的に厳しい目で見られていましたが、この勤務実態が明かされたことにより、過労死ラインを超える勤務時間や育児休暇が取得できないなどの厳しい労働条件が浮き彫りとなったのです。
こうした流れから、教育委員会や学校管理職に「勤務時間管理」という意識が芽生えたという意味では、「学校の働き方改革」の大きな前進であったと思います。ただ、教員の勤務実態を改善するための人や予算は増えていません。今の学校の働き方改革は、政府が責任をもたず、基本的に教育委員会と学校にお任せという形になっています。
例えば、2019年改正給特法によって導入された「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」では、公立学校教員の残業時間を「原則月45時間、年間360時間」としていますが、この義務を教育委員会や校長に課して、人も予算も十分に増やしてきませんでした。その結果、「校長ガチャ」といわれるような、校長先生次第で働きやすい環境もあれば、依然として過酷な労働条件の環境も生み出されています。2023年4月28日に発表された最新の勤務実態調査の速報値では、若干の改善は見られたものの、過酷な労働条件を抜本的に改善することには至っていません。そのため、これまでの働き方改革は有効ではなかったことが示されていると思っています。
学校自治によるボトムアップの施策を
また、「時間さえ減らせばいい」というような働き方改革をしていく中で、業務の一つ一つがおろそかになってしまい、教育そのものを大事にできないという声も聞こえます。授業の準備や、子ども一人一人に対する個別指導、保護者への対応などにしっかりと時間を割きたいと思っていても、時間が過ぎたら学校の外に出されてしまうといった「時短ハラスメント」も起こっています。
当事者の教員が教育活動として大事だと思う業務を優先して、そうではないところを削っていきたいところですが、実際の改革は教育委員会や校長によるトップダウンで決められてしまっています。このように当事者の声が反映されない上意下達の働き方改革の弊害も顕在化しつつあります。
校長が当事者の声を反映させて施策を実行すべきだという考え方もありますが、それよりも、労使自治ないしは学校自治的に決定するべきだと私は思っています。つまり、校長先生が一人で決定するのではなく、当事者である教員、場合によっては保護者や子どもたちをも含めて、学校においてどのような教育活動を優先していくのかをボトムアップによって決めていく必要があります。

