的確な見とりとフィードバック【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第13回】
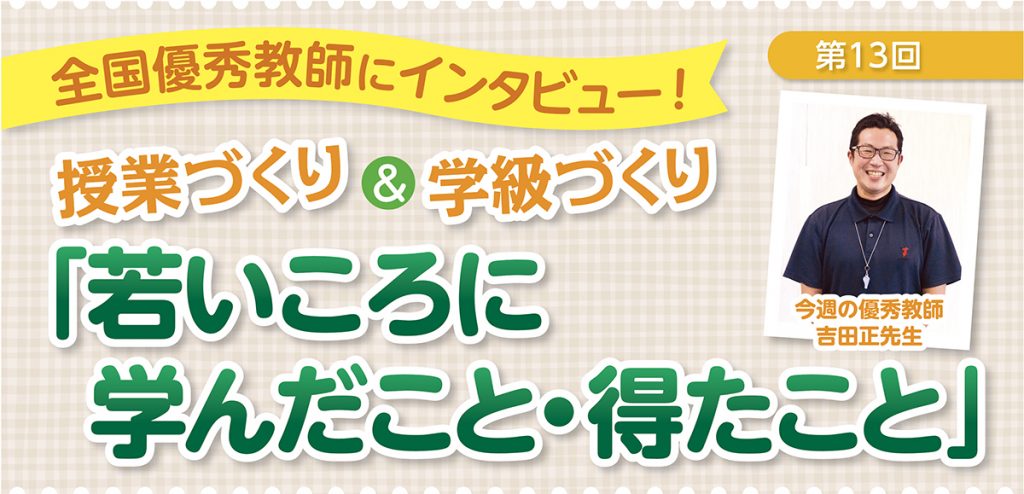
今春から千葉県酒々井町教育委員会の指導主事となった吉田正先生は、昨年度末まで小学校の教員であり、千葉県の魅力ある授業づくりの達人(小学校・体育)にも認定されていました。その吉田先生は、どのようにして小学校教員として体育の道に進み、授業づくりや学級づくりの力を身に付けていったのでしょうか。

目次
子供が成長しているだけでなく、私自身も成長できているような気がする

私はもともと、理科が得意で中学校の理科の教員になろうと思っており、大学も教育学部で理科を専攻していました。ただ、自分自身の学生時代の部活動経験があったこともあり、中学校で理科の教員をやりながら部活動でバレーボールの指導をしたいなと思っていたのです。
その考えが変わり、小学校の教員になろうと思うようになったきっかけは大学3年後期の教育実習でした。中学校の実習後、小学校へ実習に行ったのですが、そこで子供たちに関わっていくと何かができるようになる瞬間を見る機会がたくさんあって、とても魅力を感じたのです。
例えば、体育で逆上がりができるようになる瞬間とか、算数のかけ算の拡張を学習において問題が解決できて、それを友達にうまく説明でき、さらにそれを友達もちゃんと理解できた瞬間とか、いろいろな教科学習や生活場面でそのようなことがありました。そのときの「できた!」という子供の喜びの表現が輝いて見え、その瞬間を共有している私も喜びを分かち合えるわけです。その子が成長しているだけでなく、私自身も成長できているような気がしますよね。「この言葉がけが良かったのかな」とか「この働きかけが良かったのかな」というように、私自身にも学びがあるわけです。そこに最大の魅力を感じました。
それで小学校の教員へと舵を切り、翌年の夏には小学校志望で教員採用試験を受けることにしました。

