子供の姿を想像し、見とる子供理解が必要【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第1回】
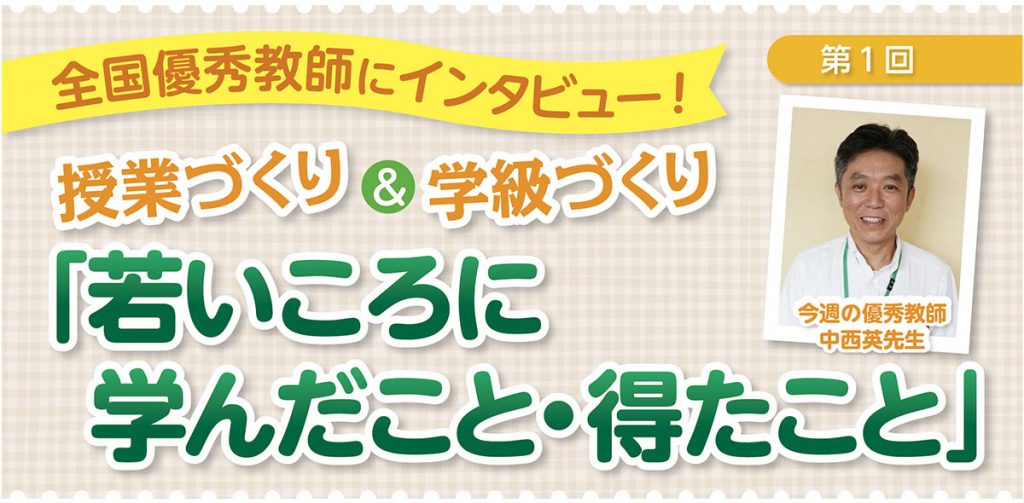
若手の先生方が優秀教師の授業を見ると、「いったい何を学べば、あんな授業ができるようになるのだろう」と思うことでしょう。しかし、どんな優秀教師も経験不足の若手時代を過ごしたはずですし、苦労し、学びながら現在のような高い教師力を身に付けてきたはずです。そこで、この連載では全国各地の優秀な先生方は若手時代にどのように学び、何を身に付けることで現在のような教師になったのかを紹介していきます。そのお話の中には、きっと若い先生方が成長していくうえでの重要なヒントがあるはずです。
連載第1回は、宮崎県のスーパーティーチャー(小学校・算数)である宮崎県公立小学校の中西英教諭が、20代の若手時代に苦労し、学んでいったことを紹介する記事のPart1です。

目次
文部省の資料、関連書籍をたくさん読んだことが自分自身の力になった
私は現在、算数を専門にしており、2022年度は算数専科を担当していますが、大学は文学部の児童教育学科で、もともとは文系だったのです。大学卒業後、宮崎県に教員として採用されたのですが、私が最初に赴任したのは日南市という所でした。その当時、宮崎市のような中核の自治体であれば、ベテランの先生も多かったため、学年主任や研究主任といった主任は年配の先生が任されることが多かったのです。しかし日南市は若手が多く、本当に早い時期から多様な校務分掌を担うことが求められていました。
その日南市の初任校で3年目を終えたときに、私はいきなり研究主任を任されました。当時の学校の教頭先生は少々破天荒な方で、突然、そんなサプライズ人事が行われたのです。そのときにはすでに3年後に算数での公開研究会を行うことが決まっていたにも関わらず、文学部出身で算数を勉強していたわけでもなく、まだ経験不足だった私が研究主任を任されたのでした。
そこからは独学で勉強をしていきました。まず研究主任の仕事自体も分かりませんから、中学校の社会科の教員だった私の父がたまたま持っていた、他県の教育研究所が出している「研究主任の仕事」というようなタイトルの資料を譲り受け、研究はどのように進めていけばよいのかを学びました。
また算数という教科に関しては、文部省(当時)から出されていた「小学校指導書算数編」(下図参照)だとか「指導計画の作成と学習指導」といった資料を読んで、ほぼ独学で研究をどう進めたらよいのかを考えていったのです。放課後はもちろんですが、土日はほぼ図書館にこもって、関係資料を徹底して読み込んでいきました。やはり、研究発表を行うためには多様な資料を読んで自分なりに整理し、事前に決まっている研究テーマに沿った具体的な手立てを、校内の先生方に提案しなければいけないわけです。そのために文部省の資料を読み、関連の専門書を読み、自分自身の授業と関連付けながら整理し、研究の構想を立て、先生方に分かるような提案を作成していったのです。そのときに、たくさんの本を読んだことは本当に自分自身の力になったと思っています。
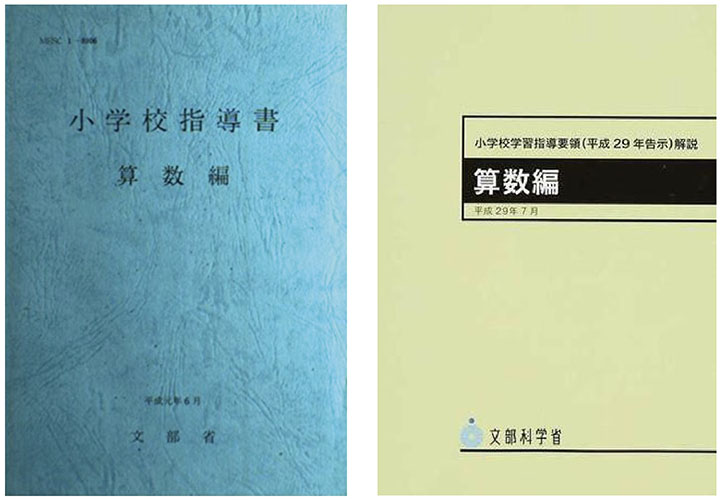
ただし、資料を精読するだけでは実際の授業に落とし込むのは難しいものです。そこで、同じ日南市内の隣の学校に在籍しておられた、算数の授業に卓越した先生にアポを取り、放課後に研究の進め方や実際の授業づくりの仕方などを教えていただきに行きました。ちなみに、同校は本校よりも先に公開をした学校で、その先生は算数の授業づくりでは名前を知られた方だったのです。余談ですが、その先生は後に県教育委員会の要職に就かれるような方で、そこで直接に教えていただいたことも、授業を構想していくうえでとても力になりました。
そのように、まず個人的には関係資料で勉強し、授業については先輩の優秀教師から学ぶという感じで算数の研究を進めていき、無事、公開研究会を終えることができました。

