「纏まる」教育の再興を ー「学級崩壊」「家庭崩壊」からの警告ー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第26回】


教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第26回は、【「纏まる」教育の再興を ー「学級崩壊」「家庭崩壊」からの警告ー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 「纏まり」の崩れ現象
「纏(まと)まる」と書いて、『明鏡国語辞典』では次のような解説がなされている。
①別々にあったものが集まって一つになる。また、統一のとれた集まりになる。
・全員が一丸となって──
・髪がうまく──らない
・土器が──って発見された
・──った金が必要だ
②思考・資料などの整理がつき一つの形に落ち着く。
・クラスの意見が──
・この報告書は分かりやすく──っている
・旅行の計画が──
③話し合いなどの決まりがつく。
・交渉が──
これらによれば、「纏まる」は善であり、望ましいことである。よく「纏まっている」クラスは安心できるし、「纏まっていない」クラスは心配である。
その「善」であり、「望ましい」筈の「纏まり」が、この頃かなり崩れてきているように思えてならない。例えば「崩壊」という言葉の多用現象が一つの象徴である。「学級崩壊」「学年崩壊」「学校崩壊」などとも言われ、「家庭崩壊」などとも言われる。「崩壊」という言葉が使われる前には「荒れている」という言い方がなされ、「あのクラスは少し荒れている」というように言われていた。「崩壊」よりはやや和らぎがあるように感じられる。「崩壊」は激しい。
「崩壊」とは言われないまでも、現象としては「纏まり」の崩れが増えているようだ。例えば、昔は学校の全職員が楽しみにしていた「職員旅行」がほとんど宿泊を伴ってなされていたものだが、この頃はそれが減っているらしい。宿泊はおろか、日帰りのそれも「希望者」で実施しているところもあるようだ。また、一つの学期が終わると、やれやれということで「反省会」や「慰労会」「懇親会」などの名称で全員が飲み食いの会を楽しんだものだが、それすらも「強制」はできなくなっているとも聞く。
校長は一つの学校のリーダーとして様々の指導をしてきた存在であるが、退職をすると「退職校長会」に全員が加入して、あれこれと旧懐の情を交わし合ってきていた。ところが、その会に「非加入」という例が、ちらほらと見られるようになってきた。「もういい」「一人で自由にしたい」ということらしい。「縛られたくない」とも聞く。「みんな仲良く」「伝統を大切に」と教えてきた立場の、これが校長の考えか、といささか疑問に思うところである。
夫婦の別居や離婚、破綻も多くなっているようである。親子の間にも、そのような傾向が生まれ、しかも増えているように見える。田舎の生まれで若い時は都会に出て働き、結婚をし家庭を持った人も多い。やがて、田舎を守ってくれていた親が高齢になり、親の面倒や家や農地の管理もしなくてはいけない立場になってくる。そこで、田舎に帰りたいがという話になると、妻の側が子供も巻きこんでそれを渋る。とどのつまり、独り身になって帰郷という例も散見されるようだ。
善であり、望ましい筈の「纏まり」が、このような形で漸増しているらしく、それは悲しく、淋しく、残念なことだと私は思う。
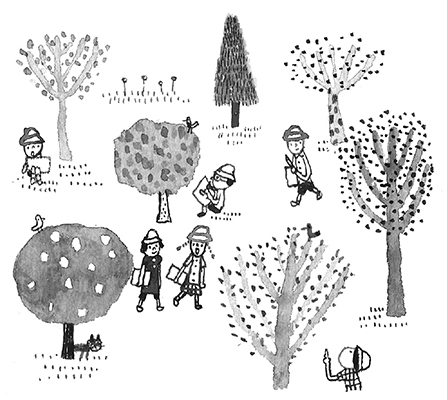
2 「纏まり」の崩れは教育の責任
さて、それらの「悲しく、淋しく、残念な」現象も、帰するところは「教育のあり方の問題だ」ということに落ちつく。
「落ちつく」と書いたが、それは高齢になった教員仲間や飲み友達の間でのことだ。
そうではなく、「社会の問題」と言う人もある。そういう考え方も誤りではないだろうが、私はそうは思わない。少なくとも教員としては言えまいと思うからだ。「教育は国家百年の大計」とも言われることも考えに入れてみたい。
「社会が悪い」「家庭が悪い」という言い方はよく耳にする。だが、社会や家庭の構成員は人間である。その主たる担い手は大人であるが、いきなり大人になる人はいない。全ては赤ん坊として生まれ、乳児から幼児、子供、若者を経て大人になる。その子供の時代は主として学校教育を受けつつ成長していく。その「学校教育」が成功すれば子供は立派な大人になり、その立派な大人が家庭を作り、社会を作るのだ。つまり、家庭や社会の担い手である大人は、例外なく「教育」によって作られ、「教育」の所産として存在する。このように考えることによって教育は重責を担う誇り高い職業として成立することになる。
「家庭の責任」「社会の責任」もむろん存在するが、大人づくりの根本は教育にある。教育基本法第1条「教育の目的」の末尾は「──心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」という文言で結ばれている。「国民の育成」こそが教育の「目的」なのである。そうであることに気づけば、家庭や社会の責任だという言い方は、一つの責任転嫁であり、言い逃れということになるのではないか。私はそのように考えるのだがいかがなものか。

