主体性、自主性の功罪 ー「受け身」ではだめなのかー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第12回】

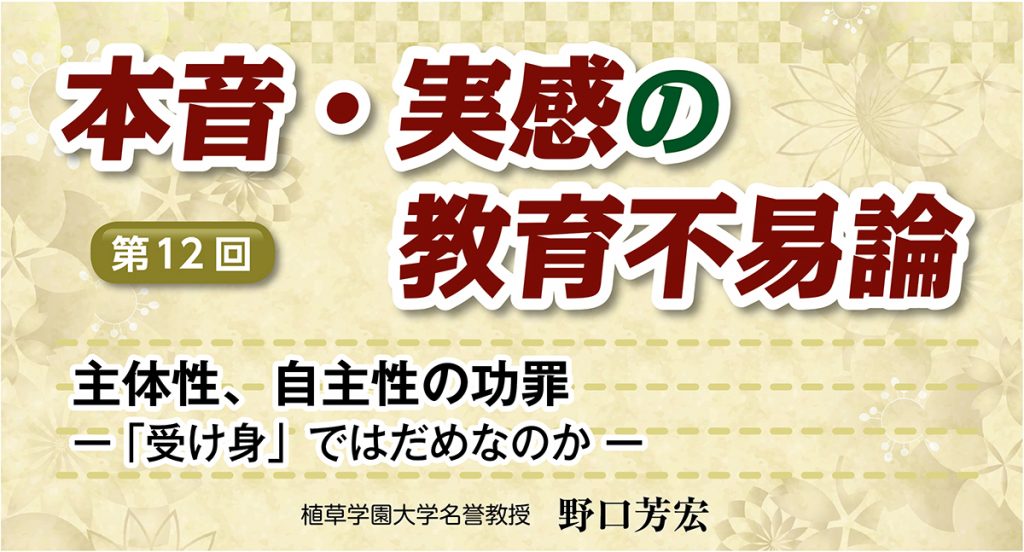
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第12回目は、【主体性、自主性の功罪 ー「受け身」ではだめなのかー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVD等多数。
目次
1 教師の自由研究への不評
校長初任の思い出である。「野口先生が今度の校長だ」という噂とともに、「きっと国語の研究をやらされるぞ」という噂も広がったようだった。私は、初任以来ずっと「右手だけは常に国語教育の綱を握る」と心に決めて歩んできたので、それは無理からぬ予想ではあっただろう。
だが、私はもともと、自分にその気がないのにやらされる仕事は「本物にならない」と考えていたので、私自身はそう考えてはいなかった。しかし、教員は公務として、自分の望まない「やらされる仕事」にも当然従わなければならない。私はそれらについては「左手で」関わり、利き腕の右手は「常に国語教育の綱を」と自戒してきたのだ。左手だから「適当に」という訳ではないが、常に自分のテーマは持ち続け、磨き続けようとしてきたということである。
さて、校長初任校の研究テーマは、「各自が今までやりたくてもやれずにきた研究テーマを主体的、自主的、自発的に決め、それぞれが自由に実践研究をする」という、「各自の自由研究」とした。
これは、学校経営方針の「自主、自立」という子どもの理想像とも合致するので、好テーマと言える。どの先生方もほっと胸をなで下ろし、喜んでくれるに違いない。私は、そのように想像していた。
ところが、これが意外なことに頗る不評を買う結果になって驚いた。「やっぱり、今までのように研究テーマを統一してくれた方がいい」「教科や領域を絞った方がよい」ということなのだ。よくよく聞いてみると「自分が特別に研究したいことなんてない」「何をどうすればいいのか分からない」「今までそんな研究はしたことがない」というような理由だった。「右手で握り続ける綱」など大方の教師が「ない」というのだ。私は驚きもしたが、「そんなものだろうか」とも思った。これは恐らくどの学校にも通ずるごく一般的な傾向なのであろう。では、絞るべき一つの教科、領域は何にするか、ということになると、いろいろな意見が出て中々まとまらないのはどの学校にも通ずることだ。つまり「不平や不満、文句」は言うけれど、「では自由に」ということになると腰が引ける、というのが偽らぬ学校現場の実態なのだ、と改めて私は思わされたことである。
だが、私は、そうであるならなおさらのこと、「校長が私だからこそできる」未経験の「自由研究」に挑ませたいと決めた。在任の2年間をそれで貫いた成果を、これまたありきたりの研究紀要でなく、「実践ノート」と銘打って収録し、雑誌に紹介したところ、多くの希望者があって喜ばれた。当時にあっては注目された実践であったからだろうが、小稿の目的は別にあるので、これ以上の報告は割愛する。

2 子どもに求める「主体性、自主性」
戦後の学習指導要領が一貫して子どもに求めてきた理念に「主体性」「自主性」がある。特別の教科 道徳についての中教審の答申の中の次の文言は、「解説」の2ページでも特に大切なこととして引用されている。
特定の価値観を押し付けたり、主体性をもたず言われるままに行動するよう指導したりすることは、道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わなければならない。
ここでも「主体性」が強調されている。「言われるままに行動するよう指導したりすること」は、どうやら「よくないこと」「やってはいけないこと」らしいから、私などは随分戸惑ってしまう。
子どもを教育する場面では、「主体性」を求め、育てることが常に賞揚されているのに、その指導者である教員自身の「主体性」に至っては冒頭に紹介したとおりなのだ。大人でさえ、教育者でさえ身についていない「主体性」なるものは、それほど子どもらに大切なことなのだろうか。
前にも書いたことなのだが、子どもという存在は、「知識も経験も乏しい未熟体」をその本質とする。この言い方には反発されそうだが、そうであるからこそ「教育」が必要になるのだ。間違いあるまい。その「未熟体」の「主体性」や「自主性」や「自発性」を過大評価するのは危険であるよりも誤認、誤解だとは言えまいか。
さらに言えば、戦後70年に余る日本の教育は総じて「よい実り」を生む「良い方向」に進んできたと言えるのか。反対に、むしろ「良くない方向」に進んできてはいないか。
多くの場で、「日本の教育はこのまま進んでよいと思うか」と問うと、ほぼ全員が「否」と応ずる。私も同感である。
では、その元凶は何か。どこに要因があるのか。私は、ずばりそれを「子ども過信」「子ども天使観」「子ども中心主義」という考え方にあると考えている。そんなことを考えていた私が、はたと膝を打った論考に出合ったので抄録しつつ、私の考えも記してみたい。これこそが「不易の論」だと思う。

