研究授業を成功させるには〈後編〉【伸びる教師 伸びない教師 第24回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

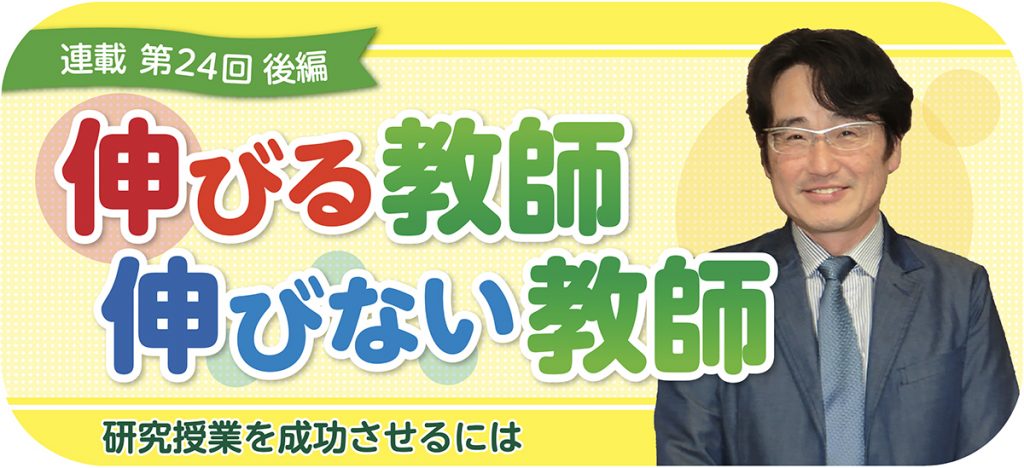
今回は、「研究授業を成功させるには」の後編です。研究授業で、授業のイメージをもたないで臨んだ授業が散々だったこと、授業のイメージをもつことが、目の前の子供に寄り添った生きた授業につながるという話です。豊富な経験で培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載です。
※本記事は、第24回の後編です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県上三川町立明治小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を歴任。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
伸びる教師は、想定外のことをイメージして研究授業に臨み、伸びない教師は、イメージをもたずに研究授業に臨む。
目次
過去に経験した悔いが残る授業
研究授業のイメージをもち全力で授業に臨むことは、真摯に授業と向き合うことであると私は考えます。それは、授業を楽しみにしている子供たち、時間を作って見にきていただいた参観者に対する礼儀でもあります。

研究授業だけ力を入れても意味がないという意見を聞くこともありますが、年に数回もない研究授業に全力で取り組めない人は普段の授業も推して知るべしだと思っています。
しかし、そう言う私も過去に1度、イメージをもたずに授業に臨んだことがありました。
40代半ばの頃でした。
これまで数多くの研究授業を経験してきたので、「なんとかなるだろう」と軽い気持ちで研究授業に臨みました。研究授業中にも学習とは関係のない軽い冗談を言って「自分は研究授業で緊張していない」アピールをするくらい授業を軽んじていました。
しかし、そんな私のぞんざいな態度に加え、事前に授業のイメージをしなかったことがすべて研究授業に出ました。
2年生の体育の長縄くぐり抜けの授業でした。技のポイントの話し合いでは子供の意見をうまく生かすことができず、板書もある程度しか考えていなかったのでひどいものでした。
授業の後半、縄が怖くてなかなかくぐり抜けができない子供がいました。
全員できることが目標だったので焦った私は、その子の手を握りくぐり抜けしようとしたところ、無理やり引きずってしまい大泣きさせてしまいました。
これまで失敗の授業は多くしてきましたが、できることをやり切っての失敗でしたので自分の中では次につなげようと納得していました。しかし、この授業の失敗は違いました。子供や授業に対する謙虚さに欠けていました。そもそも、私には自分が思っているような力はなかったのだと猛省しました。
授業前に私がその子の気持ちになってイメージを広げ対応を考えていたら……。
授業前にうまくいかなかったことを想定していたら……。
今でも悔いが残る授業です。
このことがあって、改めてイメージすることの大切さに気付かされました。

