【木村泰子の「学びは楽しい」#45】「正解主義」と「同調圧力」からの脱却を

すべての子どもが自分らしくいきいきと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載第43回目。今回は、次期学習指導要領の論点整理の中でも取り上げられている「正解主義」と「同調圧力」について考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
不登校を生む教室
前号では次期学習指導要領の論点整理について伝えました。今月はそこで表現されている言葉と子どもの姿をつなげてみませんか。
次期学習指導要領については、これまでの学校の当たり前を大きく転換するチャンスがちりばめられています。私自身の学びが欠けているからとも言えるのですが、これまでの学習指導要領にはワクワクするような未来への期待感や希望のようなものはあまり感じませんでした。ところが次期学習指導要領の論点整理では、これまでみなさん方と共有してきた「子どもにとって必要不可欠なこと」が確実に言語化されています。このことは、現場の先生たちの背中を押す大きなチャンスです。
残念ながら、過去を踏襲して「大人の言うことを聞くのが子ども」といった価値観を子どもに強要している先生方がまだおられるのが現状です。そんな先生方の前で、(そんな過去の指導を引きずって高圧的に子どもを怒鳴りつけているから子どもが学校に来なくなる……)と、心の中でしか言えない職員室の空気が温存されていますよね。(こんなはずではなかった……)と、初任の若い先生が辞めていく数も過去最多と言われます。大人が苦しい学校の空気の中では、子どもも同様に苦しんでいます。
先日、出会った子どもの声です。
「私は一度も怒られたことがないけど、教室で毎日一人の子に先生が怒鳴ります。その子は先生の言うことを聞かないからかもしれないけど、私が困っていたら助けてくれる優しい子です。その子がいつも怒鳴られている教室は苦しくて息ができなくなります。だから学校には行っていません」
この子は自分の言葉を担任には言えないと言います。周りの子たちがどう受け止めているのかを考えたら、周りの子たちに不信感が湧いてしまうとも言います。こんな感情をもった子どもが「不登校」35万人と言われる中で何人いるでしょうか。こんな現状に風穴を空ける手段が「正解主義」と「同調圧力」からの脱却です。
子どもを救う
子どもの「自殺」「不登校」「いじめ」の多くは「正解主義」「同調圧力」が原因ではないでしょうか。
「正解主義」とは、物事にはただ一つの「正解」があり、それを見つけて実行することが正しいとする考え方です。「正解主義」はプロセスではなく正解そのものに着目し、正解を追い求めるあまりに「自分で考える力」を失わせることになりがちで、思考停止の危険性があります。「問題の答えは一つしかない」と教えられる伝統的な学校教育が「正解主義」を助長してきました。既成の正解を追い求めることに慣れてしまうと、目の前の状況に応じて自分で考え、最善を尽くすことができなくなり、手段やプロセスよりも「正解」という結果に重きを置いてしまいます。変化が激しい現代においては、あらかじめ用意された「正解」は存在しないにもかかわらず自分たちで「正解」をつくり出すことを怠り、常にどこかに正解があるのではないかと探し続けてしまう傾向につながってしまいます。
また、「同調圧力」は周囲と同じ行動をとるよう促す心理的な力です。日本の社会で「同調圧力」が強い理由は、日本独自の価値観や文化的背景として、個人よりも集団の調和や秩序を守ることを重視してきたからです。
ある学校が新しい学校文化をつくりたいと「正解のない問いを問い続ける」ことにチャレンジしておられ、校長のプレゼンや出される資料はすばらしく、私も学ばせていただいています。ところが、「もくもく清掃」や「瞑想タイム」はすべての子どもに課されるという日常はそのまま継続されており、この「もくもく・瞑想」ができない子どもは指導されるとのことです。資料の内容・校長の言葉と現実の学校生活の日常が乖離している中で、子どもが育つでしょうか。理不尽を我慢させられている時間は学びにはつながりません。
学級の中で「同調圧力」が働き、他の子どもたちと異なる意見や個性をもつ子どもが孤立したり、分断されたりする傾向がまだまだ全国の学校で現実に起きていないでしょうか。「正解主義」と「同調圧力」の二つが組み合わさると、多数派の意見が常に「正解」とされ、少数意見や人と違う行動は排除されてしまいます。
大人が変わる
「集団を育てる」「多数決で物事を決める」といった従前の学校文化を、まずは全教職員が合意して捨てることです。子どもの学びだけではなく、この「正解主義」「同調圧力」は職員室も分断します。「正解主義」「同調圧力」とはどういうことなのか、どのような子どもの事実につながるのかについて、お茶を飲みながらそこにいる教職員と雑談してみてください。
今、学校で起きている「いじめ」「不登校」「自殺」の子どもの事実は、この「正解主義」と「同調圧力」が原因だと言い切っても過言ではありません。言い換えれば、学校から「正解主義」と「同調圧力」を捨てれば、子どもの残念な事実は発生しないと言うことです。
大人が変わらなければ、「学習指導要領」は飾り物にすぎません。「自殺ゼロ」「不登校ゼロ」のパブリックの学校の当たり前を取り戻しましょう。
〇「正解主義」は子どもから「自分で考える力」を失わせ、変化の激しい時代を生き抜く力を奪う。また「同調圧力」は、他の子どもと異なる意見や個性をもつ子どもを孤立させ、分断する。
〇「正解主義」と「同調主義」が組み合わさると、多数派の意見が「正解」とされ、少数派の意見は排除される。
〇「自殺ゼロ」「不登校ゼロ」の学校の当たり前を取り戻すため、全職員の合意のもと、「正解主義」や「同調主義」を捨てていこう。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#44】多様な子供たちの「深い学び」を確かなものに~次期学習指導要領の論点整理を踏まえて~
【木村泰子の「学びは楽しい」#43】子どもと子どもをつなぐ
【木村泰子の「学びは楽しい」#42】障害に応じた対応ではなく、一人の人として
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
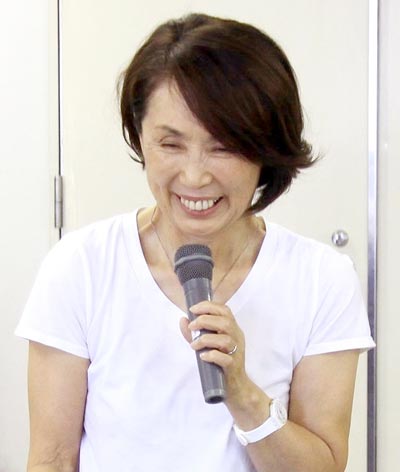
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、すべての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。
【オンライン講座】子どもと大人の響き合い讃歌〜インクルーシブ(共生)な育ちの場づくり《全3回講座》(木村泰子先生✕堀智晴先生)参加申し込み受付中! 大空小学校時代の「同志」お二人によるスペシャルな対談企画です。詳しくは下記バナーをクリックしてご覧ください。

