教師にとっていちばん大切な力は何だと思いますか? シン・コミュニケーション~教師というプロコミュニケーターになるために~

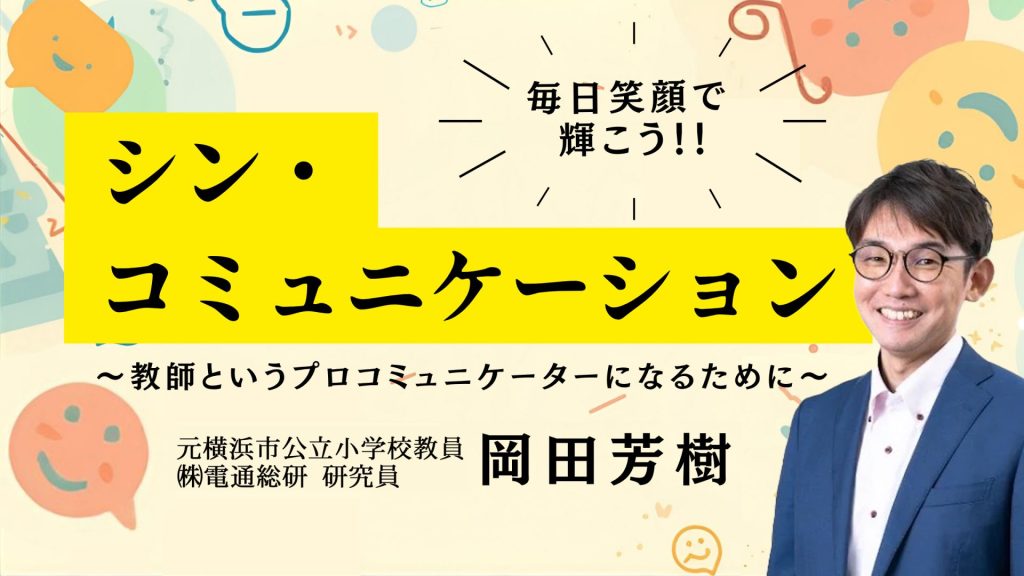
児童生徒はもちろんのこと、保護者や同僚、そして校外の関係者と、教師の仕事はさまざまな人とのコミュニケーションで成り立っています。だからこそやりがいがあり、尊く、そして難しい仕事なのではないかと思います。
本連載では、大学や一般企業の研究機関でコミュニケーションについて深く研究する筆者が、自らの教員経験と研究結果をもとに、教師という仕事に必要な新しいコミュニケーション・スキルを提案していきます。
執筆/株式会社電通総研 研究員・慶應義塾大学SDM研究所 研究員・元横浜市公立小学校教諭
岡田芳樹
シン・コミュニケーション#1
目次
教師はまさにマルチタレント!
「どの言葉を、どのタイミングで言えば子どもたちに響くだろうか?」
これは私の教員生活7年間、ほぼ毎日考えてきたことです。
放課後にじっくり考えることもあれば、授業中瞬時に考え言葉を発する必要性もあったため、自然と思考力が深まり、頭の回転が速くなりました。席替えや体育のチーム分けですらも、能力面やコミュニケーション面など様々な観点から戦略的に考え、常に頭の中で模索していたことを今でも思い出します。
現在、私は教職を離れ、研究職を務めています。学校現場を外から客観的に見ている今、
「教員ほど多くの能力を使う職種はない。まさにマルチなタレントを鍛えられる仕事だった」
と心から思います。
プロジェクトマネジメント力、教員同士のチームワーク構築力、授業のイノベーション力、保護者への交渉術など、普段の業務を細分化することで、教育現場で身に付く能力は山ほどあることに気づきます。教師はまさに鍛え抜かれたマルチタレントなのです。
そして、そのように多く培ったマルチな力も、子どもや保護者など他者に伝わり、最良の結果を得られてこそ意味があります。その際、何より重要なのがコミュニケーション力です。つまり、コミュニケーション力は教師にとって基礎体力であり、最も重要視すべき力といえます。
このコミュニケーション力は一般社会通念上でも、そして個人的な人生においても、最も重要なファクターであり、この力を鍛えることで得られる果実は何より価値が高いと断言できます。一言でコミュニケーション力と言っても、無数に研究され尽くしているファクターでもありますので、その中身は多種多様かつ奥深いです。だからこそ学ぶ価値があり、鍛える価値があります。本連載を通じて、コミュニケーションの奥深さ、そして鍛えるおいしさを味わって頂けたら、筆者として望外の喜びです。
教育現場で非常に重要な「シン・コミュニケーション」
さて、まず最初に大切なことを一言。教師はプロのコミュニケーターであるべきです。
なぜなら、学級経営、保護者対応、そして学校が抱えるあらゆる課題は、教師のコミュニケーション能力なしには解決できないからです。いかに知識や技術があったとしても、コミュニケーション力がなければ意味がありません。
場面ごとに、どのような言葉を用いるか、どのタイミングで発するか、非言語表現(ジェスチャーや表情など)を用いて、いかに自分の意図を伝えるか…。
こうしたコミュニケーションのテクニックは「戦略的コミュニケーション」と呼ばれ、国際的な交渉の場面などで非常に重要視されており、諸国で国家戦略の一つとして研究されています。
かつてコミュニケーションは、人間が成長していく中で自然と身に付けていく力だと捉えられていましたが、今や一つの体系的な知識として習得し、戦略的に活用する武器と言えるようなスキルとなったのです。
本連載では、この新しいコミュニケーションの方法論を「シン・コミュニケーション」と呼ぶことにします。
ここには、具体的には、雑談(インフォーマル・コミュニケーション)、レトリックを用いた話法、ファッションなど言葉いらずの対話など様々な種類の会話・対話などが含まれるかと思います。
ぜひ皆さんと一緒に、この『シン・コミュニケーション』の世界をひもといて行きたいと思います。
今回は第1回ということもあり、シン・コミュニケーションの要素を3つほど簡単に取り上げて説明したいと思います。
(1)雑談(インフォーマル・コミュニケーション)
かつて、雑談は組織の運営で不必要なもの、とされてきました。しかし、コロナ禍でコミュニケーションが断絶され、多くの企業ではテレワークが定着するなかで、あらためて人と人のつながりがいかに重要なのかを皆が思い知ることとなりました。
非公式な会話、いわゆる「インフォーマル・コミュニケーション」は、様々な研究結果より職場風土向上に一役買っていることが証明されています。雑談によってメンバー間の信頼度が上がり、知見の共有が促進されているのです。
これは学校においても同様です。教師間、教師と児童、教師と保護者においてもインフォーマル・コミュニケーションは非常に重要な存在になりつつあります。
(2)レトリックを用いた話法
レトリックは古代ギリシャ人が生み出した弁論術です。
おもに
●ロゴス(論理)
●エトス(人柄)
●パトス(感情)
の3つを用いた話し方であり、近年大学をはじめ学び場が増えつつある注目ワードです。
教育現場に置き換えて説明すると、まずロゴスは一貫性をもってロジカルに説くことです。教師の言葉はぶれないことが大原則であり、言葉がぶれると、小学校高学年ぐらいになれば、「あれ? 先生、以前と言っていること違くない?」と見抜かれてしまい、それは結果として児童生徒に不信感を生み出します。是非、一度発した言葉は1年間、できる限り貫き通しましょう。
次にエトスですが、いわゆる人格的な言葉で説くことを示します。教師の授業力や豊富な知識も大切ですが、何より児童生徒は教師の人格を見ています。もし仮にロゴスが崩れたとしても、立派なエトスを発することが出来ていれば…、つまり高い人格をもって児童生徒に接することができていれば、児童生徒は教師の指導に従おうと思うものです。そのためにも教師は日々人格を磨き続ける必要があります。発する言葉にはその人の人格が宿ります。
最後にパトスですが、感情を込めて説くことを示します。淡々とした無機質な言葉は児童生徒に決して響きません。教師が心の底から思っていること。その誠実さを込めた言葉だけが彼らに届くのです。発する言葉は拙くても全く問題ありません。ただただ、正直でありましょう。建前の長い誉め言葉より、拙く短い本音の言葉こそが彼らの心に残ります。
レトリックは何より相手の感情に訴えかけ、行動変容を促す伝える技術として重宝され続けてきた歴史があり、社会人なら誰しも会得すべき能力の一つです。
特に教師は自分の指示を子どもが納得できる形で伝える必要があり、レトリックを使える教師は子どもへの指導が大変上手になります。習得するには勉強が欠かせませんが、子ども以外にも多くのステークホルダー※と話す機会が多い教師には、今後必修ともいえるコミュニケーションスキルともいえるでしょう。
※ステークホルダー=企業や組織に利害関係を持つあらゆる関係者のこと
(3)ファッション、表情、仕草など言葉いらずの対話
コミュニケーションといえば言葉ありきのイメージですが、言葉を使わずともメッセージを発することができます。その手段の一つがファッションです。服装心理学の研究によれば、たとえばスーツは着ている人の自信を高める作用があることが分かっています。よく「人は見た目が9割」などと言いますが、これはあながち間違いではなく、ファッションには「自分はこういう人間です」というメッセージを発する作用があり、教師のファッションは間違いなく子ども達に無言のメッセージを送っています。
ファッション以外にも、仕草や表情も非言語化コミュニケーションの一つです。拍手(もちろん、心がこもっている前提で)、目配り、腕組み、頭をかく、声のトーン…教師の一挙手一投足に教師自身の感情が込められており、感性が敏感な児童生徒はそこから教師の発するメッセージをくみ取ります。是非ポジティブな非言語メッセージを心掛けたいですね。
以上、事例として3つ挙げましたが、『シン・コミュニケーション』の効果は教師のメンタルヘルス向上や職場風土改善にまで影響を与えるため、学ぶ価値は大いにあります。プロコミュニケーターを目指す上でも、是非ともこの機会にシン・コミュニケーションに触れてもらえたら幸いです。
やっぱり教師の仕事は尊い
教育現場から離れて数年経った今、教師時代から変わらず思うことは「やっぱり教師の仕事は尊い」ということです。人を育て、未来の社会を創ること、これが教師の究極の使命であるため、尊くないはずがありません。
しかし、現実を見れば、その尊い仕事が日本社会においては十分リスペクトされているとは言えない状況にあります。教育への投資を怠ることは、近い将来、ブーメランのようにその代償が自分たちに返ってきます。そのときに気づいても、修復するのにまた長い歳月が必要となるでしょう。
海外では、教師はリスペクトされる対象であり、また教師自身も自負心をもって仕事に取り組んでいます。
日本の教育もきっとそうなれるはず。
その一助となる『シン・コミュニケーション』について次回以降より具体的に解説していきたいと思います。

【参考文献】
石原敬浩(2016)『戦略的コミュニケーションとFOD―対外コミュニケーションにおける整合性と課題―』海幹校戦略研究2016年7月号
山崎喜比古(2013)「医療IT産業従事者の労働環境ストレッサーが精神健康とワークモチベーションに影響を及ぼす過程における職場風土良好度とSOCの効果に関する共分散構造分析結果」『産業精神保健』巻21号,pp.94
ジェイ・ハインリックス(2018)『THE RHETORIC』ポプラ社
Edwards, J. (2020). Psychological Impact of Formal Wear on Self-Perception. Journal of Fashion Psychology

執筆者:岡田芳樹(おかだ・よしき)
1986年、東京都生まれ。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了。新卒で政策シンクタンク勤務を経て、横浜市の小学校教諭として7年間勤務。現在株式会社電通総研にて研究員を務める。同時に慶應義塾大学SDM研究所の研究員、大学院のゲスト講師、『週刊教育資料』のコラムニストを担う(「バーンアウト防止に必要なデータによる感情管理」「安易なウェルビーイング教育は感情の資本化を促進する」など)。研究テーマは感情社会学、教育社会学、戦略(コミュニケーションやインテリジェンス)研究など。

