【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#9 機能する校内連携体制を、どうつくる?―実践編その5―
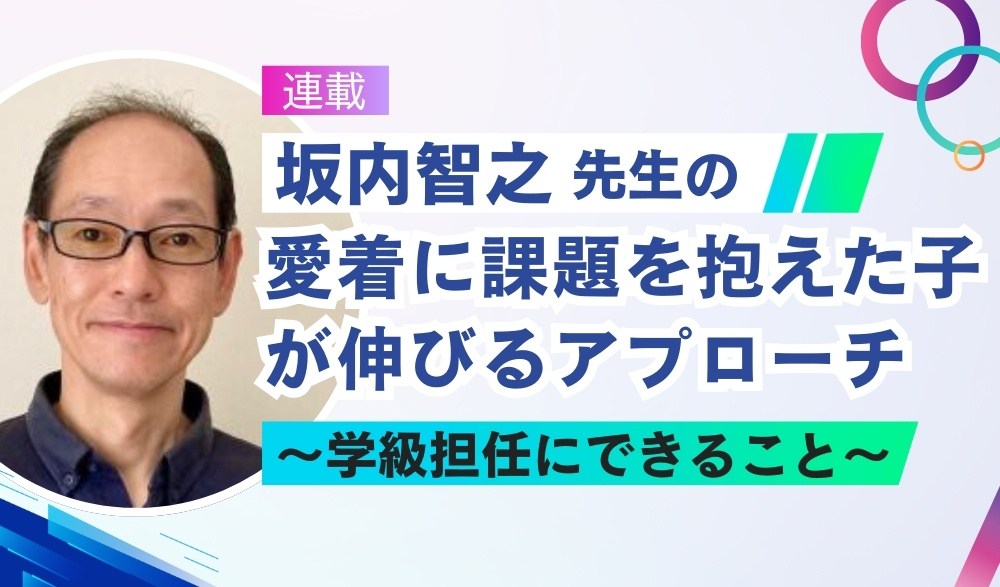
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第9回。今回は、愛着障害の子どもたちへの連携対応について考えていきます。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
大きな不安感を抱えてうまく行動できない子どもや、不適切な言動でトラブルを起こす子ども――。
担任教師は常にその対応に追われ、次第に疲弊していきます。クラスの中にそうした子が複数いる場合は、自分一人では対処しきれず、行き詰まってしまう教師も多いのではないでしょうか。これらの諸問題を複数の教職員の力で解決できるのが「連携」です。ところがこの連携、うまくいっていない現場も多いのではないでしょうか。
特に小学校現場では学級担任制のために、問題を担任一人で抱えこんでしまうことが多く、連携がうまく機能しないことがあります。また、連携による愛着障害の子どもへの対応は大変効果的なのですが、やり方をひとつ間違えるとトラブルを一層悪化させてしまう可能性もあります。
今回の実践編は、この「連携」のあり方について再考しながら、実践する際のポイントについて、みなさんにお伝えしていきたいと思います。
なぜ学校現場では連携が難しいのか
気になる子ども、不適切な言動を繰り返す子どもへの対応には、チーム体制で臨むことが大切ですが、実際は、多くの現場でうまく機能していません。なぜでしょうか。
まずは、スムーズな連携を阻む要因について考えてみます。
原因1「愛着障害の特性」
愛着に課題を抱える子どもは、自分に注目を集め、理解してもらうことを目的として様々な困った言動を繰り返し、それが対人トラブル等につながります。
こうした子どもは、特定の大人と「安心」でつながることにより回復に向かっていくわけですが、連携対応の場合には複数の大人が関わることになり、この「安心」が揺らいでしまいがちです。連携対応の過程で複数の大人から様々な言葉を投げかけられることで、シャットダウン(無反応)や、不安定な行動を引き起こします。その内面と言動とが一致しないことが愛着に課題を抱える子どもの特徴ですから、連携対応にあたっては、細心の配慮が必要です。
原因2「教師の孤独」
小学校の学級担任は、授業のほとんどを自分一人で担当しますし、目の前で起こるトラブルに対しても、よほど大きなものでない限りは自分一人で判断し、対処しなければなりません。事後処理、保護者対応等も基本的には担任教師が行うことが多いでしょう。教師は基本的に孤独なのです。
そうなる背景には、学校現場の忙しさがあります。相談するにも、周りの同僚や管理職も同じように多忙ですから、なかなか相談しにくい雰囲気があります。また、管理職や同僚に相談することで、「指導力不足」だと思われることを恐れ、相談しにくいという側面もあります。同じ子どもが何度もトラブルを起こすと、「またか」「前回ちゃんと指導をしたの?」などと言われるのではないかと心配になり、相談することをためらう教師も多いことでしょう。
こうした理由から、学校現場では連携が機能しにくく、教師が孤立している場合が多いのです。
原因3「連携によって状況を悪化させてしまう」
自分一人では抱えきれないような大きなトラブルが起こった際、真っ先に相談し、助けを求める相手は管理職です。特に教頭は、校長が対処する前のワンクッションとして、担任の相談に乗ったり、子どもへの対応を支援したりする場合が多いだろうと思います。
私がこれまで出会ってきた教頭の多くは、子どもたちへの対応がとても上手で、トラブルを上手に解きほぐし、困っている教師の相談にものってくれました。
一方で、学校によってはその逆の場合もあります。管理職や同僚の中には、大人としてより厳しい態度が必要だという考えのもと、子どもを怒鳴りつけ、力で押さえつけることをよしとする方もいます。強い対応をすれば、瞬間的には問題行動を抑えられますから、「やっぱり厳しい態度が大切だ」「担任はもっと強く厳しい言葉で」などのアドバイスを続けることになります。
担任がそうしたアドバイスに従って強い指導をしてしまい、子どもたちとの関わりが悪化したケースを数多く見てきました。この連載をここまで読まれてきた方はお分かりのように、そうした力による対応は、愛着に課題を抱える子どもにとって、百害あって一利無しです。愛着に課題を抱える子どもへの理解や対応への知識がない人が連携チームのメンバーとして関わることで、状況をさらに悪化させてしまうこともあるのです。
原因4「対応のための知識が足りない」
どこの学校でも生徒指導会議等を開き、気になる子ども、課題を抱える子どもについて、教職員全体で情報を共有しているはずです。しかし、近年ではそうした子どもの事例報告が急増し、多くの場合「どんな課題を抱えているか、どんなことに困っているか」を紹介するだけで会議が終わってしまい、具体的な対応策や対処にまで踏み込んで検討されることは少ないのではないでしょうか。もちろん、担任がどのようなことに苦戦し、困り感を持っているのかを同僚に知ってもらうことは、担任の安心感につながります。
しかし、それだけでは状況そのものは変わりませんから、担任はその後も困難を抱え続けることになります。
なぜ、こうした会議が事案の共有だけで終わってしまうのでしょうか。
それは、時間の不足に加え、対応するための知識も不足しているからです。
愛着の課題を抱える子どもの言動や態度の背景にあるものを読み解くことは、とても困難です。そのためには多様な視点から子どもの観察を行わなければならず、その心理状態や身体状態についての豊富な知識が必要です。それなのに学校現場では従来の経験則が重視されすぎ、愛着障害等の新しい子どもの見方や、対応法に関する知識に、まだ追い付けていません。
原因5「長期的な視野を欠いた対応」
教職員による連携対応は、数日、数週間といった短期間ではうまくいきません。幼いころから愛着の課題を抱えてきた子どもの場合、うまく対応したとしても回復に数年かかる場合があり、その成長はとてもゆっくりです。ですから、長期的な視点や対応が必要です。
今はどの学校でも連携という言葉を使っていることでしょうが、多くの場合その視点は短期的なものです。その結果早く成果を上げたいと考え、強い指導や称賛によって、短期的に回復させようとする取組が多くなります。そうした取組の結果、一時的によくなったように見えても、その強い関わりが弱まると同時に、元に戻ってしまうことが多いのです。
「連携する」とは、どういうことか

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

