賛否両論に対応するには?【伸びる教師 伸びない教師 第57回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

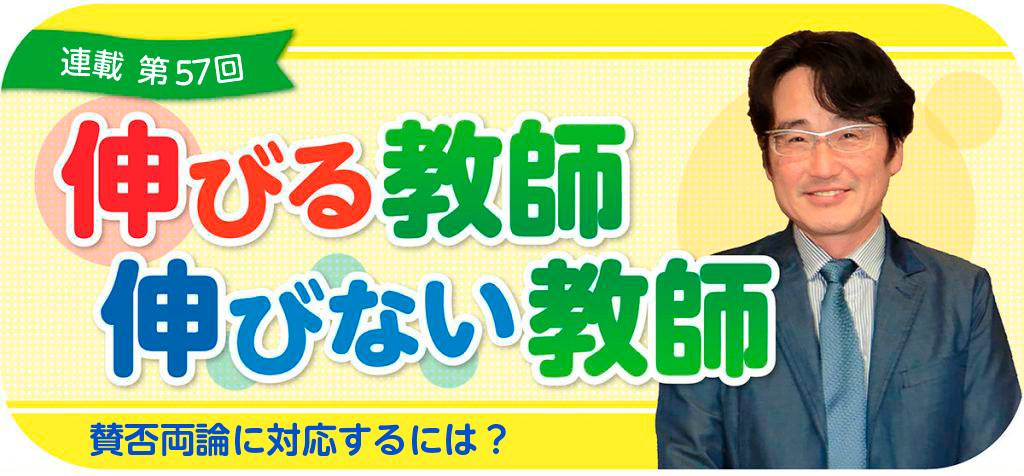
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「賛否両論に対応するには?」です。例えば、宿題の量や担任の指導など、1つの事実に対して、賛成の人もいれば反対の人もいます。それをどういうふうに考えるのかという話をお届けします。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
人によって考えが異なる
若い教師から相談を受けたことがありました。
「個人懇談で、ある保護者から宿題が少ないので増やしてほしいと言われました。学級全体のことを考え今の量にしていることを伝えたのですが、なかなか分かってもらえなくて……」
結構強く言われたようで落ち込んでいる様子が伺えました。宿題の量に関しては、私も担任しているときにこれと似たことを言われた経験がありました。人によって考えが違うので、賛成の人もいれば反対の人もいるのは仕方がないことです。どちらをとってもクレームを言う人は出てきます。
担任の指導に対するクレームについて
人によって考えが違うといえば、以前、こんなことがありました。
保護者4~5人が学校に来たことがありました。担任の指導に対するクレームでした。
話を聞くと、確かに不適切な指導と言われても仕方ない内容でした。ここにいる保護者だけでなく、学級の保護者はみんな同じようなことを言っているとのことでした。とにかく、担任から詳しい事情を聞き、改めて連絡するということでその場は帰ってもらいました。
放課後、担任に話を聞くと、保護者が言っていたことの多くは事実であることが判明しました。そこで、当時の校長の判断で臨時の保護者会を開くことにしました。先日学校に来た保護者には担任から聞き取ったことを説明するとともに、学級全体へ説明する機会を設けることを伝えました。
臨時の保護者会では、初めに学校側が今回のことについて説明した後、保護者に謝罪しました。その後、「どうしてそのような指導をしたのか」「今後、学校としてどう対応するつもりなのか」など、いくつかの質問が出ました。初めは、この前学校に来た保護者が中心となって質問していましたが、しばらくすると他の保護者も発言し始めました。
「私は、臨時の保護者会があるからと連絡を受けて慌てて来たのですが、学級で起こっていることは、今日説明してもらって初めて知りました。ただ、うちの子は、担任の先生が大好きで、子供たちが悪いことをしたのであれば、多少厳しくしてもらっても構いません」
初めに学校にクレームを言いにきた保護者は、「他の保護者もみんな同じようなことを言っている」と話していましたが、事実ではなかったようです。
この発言から、担任の指導をめぐって意見が分かれ、結局、話合いは平行線のままで終わりました。
1つの事実に対して、賛成の人もいれば反対の人もいます。それぞれ考え方、置かれている環境が違うのですから当然のことと言えますが、ここまで捉え方が違うというのは正直意外でした。


