子どもたちの心を豊かに耕す、SEL(社会性と感情の学習)ってどんなもの? 明日からすぐできる、心理教育の実践!

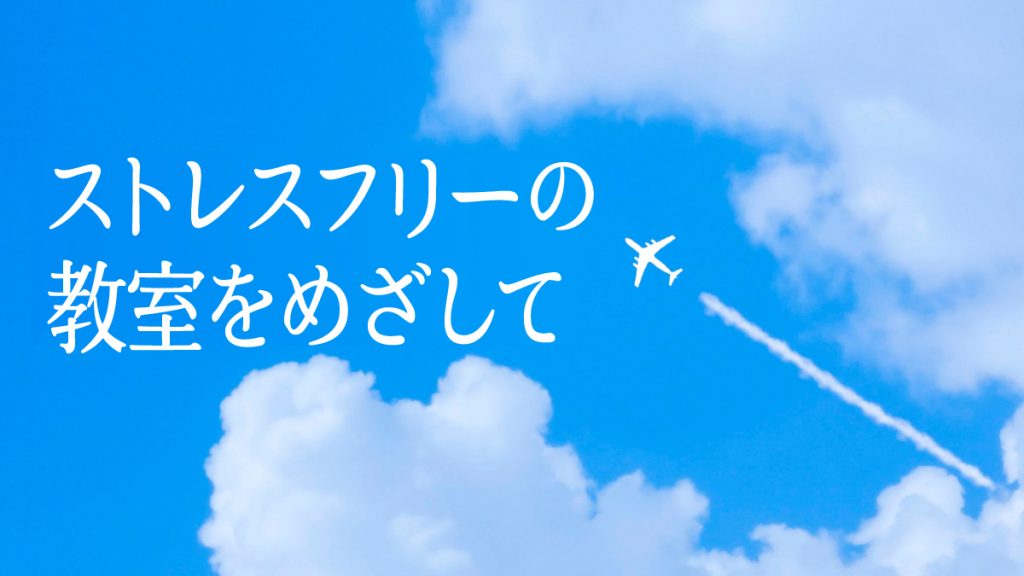
近年学校教育の場では、子どもたちが感情を理解し、適切に表現し、他者と円滑に関わる力を育むことが求められています。このようなスキルを体系的に育てるためのアプローチはSEL(Social and Emotional Learning:社会性と感情の学習)と呼ばれ、注目を集めています。
本記事では、本連載でこれまでに紹介してきた心理教育(ストレスマネジメント教育、アサーショントレーニング、ソーシャルスキルトレーニング(SST)、レジリエンスを育む教育、アンガーマネジメント教育など)について、ダイジェスト版としてまとめました。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #25
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
目次
SELとは何か?心理教育の枠組み
SELは、子どもたちが感情を適切に扱い、人と協力する力を養うための教育的アプローチ(フレームワーク)です。米国のCASELが提唱する5つの力がSELの基盤となっています。
【SELの基盤となる5つの力】
①自己認識:自分の感情や考えを理解し、自身の特性を認識する。
②自己管理:感情をコントロールし、ストレスと向き合いながら適切な行動をとる。
③社会的認識:他者の気持ちを理解し、共感し、協力する。
④対人関係スキル:効果的なコミュニケーションをとり、人間関係を円滑にする。
⑤責任ある意思決定:倫理的な判断をし、問題を解決する力を養う。
これらの力をバランスよく伸ばすことで、子どもたちは自分自身を理解し、他者と協力しながら社会で生きていく力を身につけていきます。
SELの特徴の一つは、「学びの基盤としての役割」を果たすことです。心理的に安全な環境が整っていなければ、子どもたちは新しい知識を吸収し、挑戦することが難しくなります。そのため、SELの考え方を学級経営に取り入れることは、教育活動全体の質を向上させることにつながるのです。
小学校で実践できる心理教育プログラムガイド
「どんなプログラムを選べばいいか分からない…」そんなときには、以下の内容を参考にしてください!「児童の姿」と「先生の願い」から、適切なプログラムを選びましょう。
① ストレスマネジメント教育(#1~4参照)
>#1 小学校の教室で「子どものストレス」をゼロにするために。やってみよう、ストレスマネジメント教育
>#2 実践! 小学校のストレスマネジメント教育~高学年の授業展開をもとに~
>#3 ストレスは小さくなる? 小学校中・高学年のストレスマネジメント教育~ものの見方・考え方を変えてみよう
>#4 ほっと一息 子どもたちと一緒に教室でできるリラクゼーション法
児童の姿:ストレスを感じたときに、自暴自棄になったり、攻撃的になったりする。
先生の願い:ストレスを感じたときに、適切に対処できる力を育みたい。
ストレスマネジメント教育は、子どもがストレスへの理解を深め、適切に対処できる力を育むプログラムです。具体的には、ストレスの原因や反応を学び、リラクセーション技法やポジティブな思考法、適切な対人関係スキルを身につけることを目的とします。小学校では、日常生活に活かせる実践的な方法を取り入れることが重要です。
② アサーショントレーニング(#10・11参照)
>#10 さわやかな自己表現をめざして! 子どもと教員のための アサーション・トレーニング 前編
>#11 「みかんていいな」でさわやかな自己表現を! 子どもと教員のためのアサーション・トレーニング 後編
児童の姿:自分の考えを一方的に主張したり、強いものになびくばかりで自分の意見を言えなかったりする。
先生の願い:自分も相手も大切にした自己表現ができるようになってほしい。
アサーショントレーニングは、自分の考えや気持ちを適切に表現しながら、相手の意見も尊重するコミュニケーション能力を育むためのプログラムです。自己主張が苦手な子どもや、攻撃的になりがちな子どもも含めて、全員が相手を傷つけずに自分の意見を伝える方法を学びます。具体的には、「アイメッセージ」の活用や、落ち着いた口調で話す練習などを行います。
③ ソーシャルスキルトレーニング(SST)(#12~15参照)
>#12 子どもたちの人間関係をよりスムーズに! 発達段階に合わせて学級でできる、ソーシャルスキルトレーニング ~総論~
>#13 低学年の子どもに、少しずつ相手の身になって考えられるトレーニングを! 学級でできるソーシャルスキルトレーニング ~低学年編~
>#14 発達著しいギャング・エイジの子どもたちへ! 共通の行動様式で、良いグループ化を!! ソーシャルスキルトレーニング ~中学年編~
>#15 思春期にさしかかった高学年。他者との適切な距離感がとれるようにしていこう!! 学級でできるソーシャルスキルトレーニング ~高学年編~
児童の姿:対人関係のスキルが未熟で、小さなトラブルが頻発している。
先生の願い:学級や日常の生活で必要なスキルを上達させ、トラブルを防ぎたい。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)は、子どもが円滑な対人関係を築くために必要な社会的スキルを学ぶプログラムです。具体的には、あいさつやお願いの仕方、断り方、協力する方法などをロールプレイや実践的な活動を通じて身につけます。小学校では、学級生活の中で対人関係のトラブルを防ぎ、協調性や自己表現力を高めることを目的とします。
④ レジリエンスを育む教育(#16~18参照)
>#16 しなやかな心を育てる! 小学校の教室で育むレジリエンス ~低学年編~
>#17 困難に負けない、柔らかくて強い心を育てよう! 小学校の教室で育むレジリエンス ~中学年編~
>#18 自分の強みを知り、困難に負けない心の力を養おう! 小学校の教室で育むレジリエンス ~高学年編~
児童の姿:なんでもすぐにあきらめたり、逃げたりする。
先生の願い:多少の困難にもめげずに、たくましく乗り越えてほしい。
レジリエンス教育は、子どもたちが困難に直面した際に適応し、乗り越える力を育むためのプログラムです。これは単に「我慢する力」ではなく、困難な状況から学び、前向きに対応できるようになるための心の柔軟性を高めることを目的としています。
⑤ アンガーマネジメント教育(#21~24参照)
>#21 小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育 ~総論~
>#22 小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育(低学年編) ~怒りの感情を知り、上手に付き合う~
>#23 小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育(中学年編) ~怒りの仕組みを理解し、自分でコントロールする力を育む~
>#24 小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育(高学年編) ~自己コントロール力と対話スキルを磨く~
児童の姿:イライラすると手が付けられず、人や物に当たってしまう。
先生の願い:怒りを上手にコントロールできるようになってほしい。
アンガーマネジメント教育は、子どもが怒りの感情を適切に理解し、コントロールする力を育むための教育です。怒りの仕組みを学び、自分の感情に気づくことや、衝動的な行動を抑える方法を身につけます。具体的には、深呼吸やカウントダウンなどのクールダウン技法、感情表現の練習などを行います。自己理解を深めることで、対人関係の向上にも役立ちます。


