教師の笑顔が消えないように。笑顔を取り戻すリセット術|俵原流!子供を笑顔にする学級づくり #5


子供の笑顔を育てる「笑育」という実践のもと、安全で明るい学校、学級をつくってきた俵原正仁先生。これまで培ってきた学級づくりのアイデアやメソッドを、ユーモアを交えつつ、新任の先生にも分かりやすく解説します。月1回公開。
執筆/兵庫県公立小学校校長・俵原正仁
目次
はじめに
「笑顔の教師が笑顔の子どもを育てる」……これは、私が提唱している「笑育(しょういく)」の基本コンセプトです。
笑顔あふれる子供を育てるためには、まず教師自身が笑顔でいなければいけません。そうは言っても、子供たちを前にして、笑顔になれないことってありますよね。実際、一部の子供との関係がうまくいかなかったり、保護者対応で苦労したり、学年の先生に気をつかいまくったり、なんとなくやる気が出なかったり、ということが1学期にあったかもしれません。それでも、教師はクラスの子供たちに笑顔で接するべきだということは、先生方も理解されているはずです。ただ、追い詰められた状況において、それが容易ではないこともまた事実です。
そこで、今回は、比較的気持ちにゆとりの生まれる夏休みだからこそ、教師の笑顔を取り戻すためのリセット術をいくつか紹介したいと思います。少し心が疲れてしまった時に思い出していただければ、きっとお役に立てるはずです。
楽しくなくてもとりあえず笑う
もし、身の回りに起こることが楽しいことばかりだったら、あえて意識をしなくても、自然に笑顔があふれてくるものです。でも、人生、そううまくはいきません。ガムを踏んでしまったり、タクシーが渋滞で動かなかったり、ごひいき球団が連敗したり、行きたいライブのチケットが当たらなかったりするなど、楽しくないことがいろいろと起こってしまうことがあります。そんな時、私は、次の言葉を思い出すようにしています。
楽しいから笑うのではない。笑うから楽しいのだ。(ウィリアム・ジェームズ)
普通は「楽しいことがあったから笑う」という順序を思い浮かべますが、実は逆も成り立つのです。なんと、顔の筋肉を笑顔の形にすると、その情報が脳にフィードバックされ、脳が「楽しい」と感じてしまうそうです。つまり、楽しいことがなくても、無理やり笑顔をつくっていれば、脳が「今は楽しい状況なんだ」と勘違いし、やがて本当に気分が明るくなってくるのです。だからこそ、どんなにつらいときでも、「なにくそ」と笑顔をつくってみる。そうするうちに、気持ちもついてきて、状況が少しずつ好転していくものです。まさに「笑う門には福来る」――このことわざは、脳科学的にも理にかなっているということです。
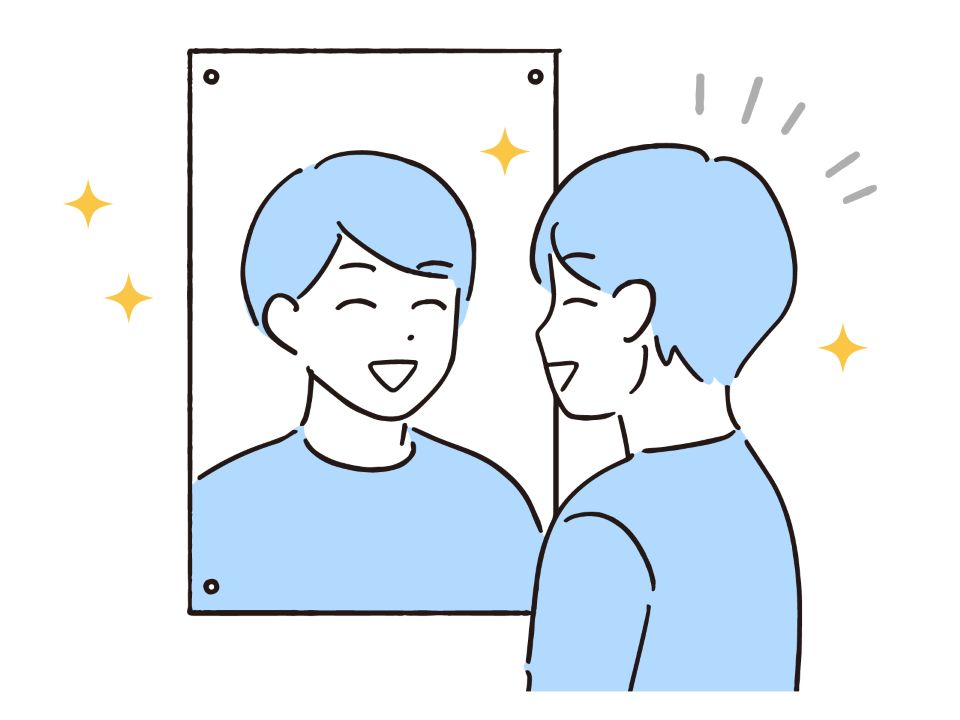
私の師匠である有田和正先生は、若かりし頃、毎日鏡に向かって笑顔の練習をしていたそうです。あの授業の名人でさえ、笑顔を意識して日々を過ごしていたのです。私たち凡人が無頓着でいい理由が見つかりません。教室に入る前に、意識して笑顔をつくってください。笑顔の教師は笑顔の子供を育てます。教師の笑顔を目にし続けることで、子供たちも何だか分からないうちに、楽しい気分になっていくはずです。教師と子供たちとの距離もぐっと近づきます。たとえ、身の回りに楽しいことがなかったとしても、とりあえず笑顔をつくる……このことをまず意識してください。
幸せを感じ取る力を高める
……とは言っても、身の回りに楽しいことがたくさん起こる方がいいに決まっています。私は、卒業間際の子供たちによく次のような話をしていました。実は気付いていないだけで、私たちの身の回りには既に楽しいことが満ちあふれているのです。
世の中には、地位や名声があっても不幸せそうな顔をしている人がいます。また、その逆の人もいます。どちらが良い人生だと思いますか。どんな状況でも、ニコニコと笑顔で前向きに生きている方が良い人生ですよね。そのためには「自分の幸せを感じ取る力」を高めてください。たとえつらい状況になったとしても、そのことを嘆くのではなく、今、身近にある幸せを感じ取ってほしいのです。そうすることで、きっと道は開けます。今の自分が幸せだと感じるポイントを自分で探し、「よくやっている」と自分自身をほめてください。
教師も同じです。「幸せを感じとる力」を高めてください。例えば、「佐藤さん、最近、漢字がんばっているな」や「大山さんは、いつも教室の花の水替えをしてくれているな」というような子供たちのちょっとしたがんばりに気付いた時、教師として嬉しくなりますよね。そんな小さな幸せを感じ取ってください。もちろん、「ふと時計を見たら、11時11分」でも、「昨日の晩御飯、おいしかったなぁ」のような教育とは全く関係のない小さな幸せでもかまいません。
「できるわけない」と思っておく
ももいろクローバーZのあーりんこと佐々木彩夏さんがパーソナリティを務めるラジオ番組(※1)に、リスナーから次のような質問が届いたことがあります。
「なにか失敗したり、思い通りにいかないことがあったりすると『自分はダメだ』と落ち込みやすいです。モチベーションを維持したり、上げたりするにはどんなことを意識すればいいですか?」
それに対して、あーりんは次のように答えていました。
失敗したら落ち込むのはもちろん当然ですけど、成功すると過信していたから、落ち込むんじゃないかな?(中略)私はポジティブなイメージをもたれるんだけど、「できる!」と思っているわけではなくて、「できるわけない」と思っているんだよね。(中略)ライブで(他のメンバーが)「間違えたらどうしよう」って言っていたから、「間違える可能性はぜんぜんあるじゃん」って言って。間違えた時にどうフォローするかとか、失敗した時の準備をしていた方がいいんじゃないのかな、って。
※1 2023年9月3日放送『ももクロくらぶxoxo』(ニッポン放送)
このあーりんの言葉は、以前、若き日の私が運動会の企画運営であたふたしていた時に、先輩から教えていただいた「当日までは悲観主義で準備して、いざ当日になったら楽観主義で対応しろ」というアドバイスに通じます。
「うまくいくはずがない」と悲観的に考えることで、当日までは、自分の力を過信することなく、より綿密に丁寧に準備をおこなう気になります。そして、万が一、うまくいかなかった場合でも、もともと「うまくいくはずがない」と思っているのですから、必要以上に落ち込むことなく冷静に対応できるということです。
また、うまくいかないことが前提ですから、うまくいった場合は喜び倍増です。何も期待していなかったのに、サプライズプレゼントをもらったようなものです。「うまくいくはずがない」と考えることで、うまくいかなくてもよし、うまくいったらさらによしになるのです。つまり、悲観的に考えることで、結果を楽観的に受け止めることができるということです。
過信しなければ落ち込まない
同じようなことは、明石家さんまさんも言われています。あるテレビ番組(※2)で「最近、お仕事で落ち込んだことはありませんか?」というさんま師匠への質問に対して、「ない」と即答した上で、次のような落ち込まない極意を話されていました。
己を過信しているから落ち込むだけ。俺とか俺の周り、みんな過信なんかしていないよ。「できたはずなのに」とか。ストレスとかたまる人、みんな過信している。
このさんま師匠の言葉は「成功すると過信していたから、落ち込むんじゃないかな」というあーりんの言葉とほとんど同じです。さんま師匠もあーりんもいつも明るく元気で、楽観的なイメージです。そのような2人が、「楽観的な考え方を捨てると、悩まなくなる」と言っているのが、実に面白いと思いませんか。
※2 2016年5月28日放送『メレンゲの気持ち』(日本テレビ系)
悲観から楽観が生まれているのです。悲観的に考えておくことで、リスク耐性が高まるということです。特に、壁にぶち当たっている若い先生には、「最初からうまくいくはずがない」という考えを受け入れてほしいと思っています。そう思うことで、「なのに、休まず学校に来ている私はえらい」と自分をほめることもできます。職場のできる先輩も、若い頃には必ずどこかで壁にぶち当たっています。誰もが通ってきた道です。落ち込む必要はありません。今できることを淡々と続けていけば道は開けます。そう、ゴールはハッピーエンドに決まっているのです。
メタ認知で自分を客観的にとらえる
ただ、「失敗は常に想定内」と考えることで、誰もが落ち込まなくなるかと言えば、それは違います。想定内の失敗でも、自分を責めてしまい、落ち込む人もいるはずです。
私は、あーりんやさんま師匠が「ちょっとやそっとのことでダメージを受けない」のは、それなりの理由があると考えています。それは、メタ認知ができるということです。メタ認知で客観的な自分をもう一人つくり、「もともとうまくいくと思っていなかったんだから、想定内。だから、落ち込むことはない」と、落ち込みそうな自分を楽観的に励ますことができるから、落ち込まないのです。
ただ、いきなり、あーりんやさんま師匠の境地に達するのは難しいかもしれません。でも、自分自身を客観的に捉え、過信せずに行動しようと意識することは、明日からでもできるはずです。少しずつでいいんです。
次回予告

あっという間に夏休みも残り1か月。ちょっぴり寂しく感じるかもしれませんが、ご心配なく! これからが夏のハイライトです。熱い音楽が響き渡るサマソニやロッキン、興奮と熱狂渦巻く夏の馬鹿騒ぎにG1クライマックス決勝(新日本プロレス)、そして、のんびり過ごせるお盆休みも待っています。
そう、夏休みはこれからが本番! 1学期、頑張った自分へのご褒美に、心と体にエネルギーをチャージする最高の夏にしてください! 私も、思いっきり楽しんで、笑顔の貯金をするつもりです。
次回のテーマは、「2学期開幕 子供も教師もバージョンアップするために!」です。フル充電が完了した先生方へ、充実した2学期を送るための情報をお届けします。

俵原正仁(たわらはら・まさひと)●兵庫県公立小学校校長。座右の銘は、「ゴールはハッピーエンドに決まっている」。著書に『プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術 』(学陽書房)、『なぜかクラスがうまくいく教師のちょっとした習慣』(学陽書房)、『スペシャリスト直伝! 全員をひきつける「話し方」の極意 』(明治図書出版)など多数。
俵原正仁先生執筆!校長におすすめの講話文例集↓
俵原正仁先生執筆!校長におすすめの学校経営術↓
【俵原正仁先生の著書】
プロ教師のクラスがうまくいく「叱らない」指導術(学陽書房)
スペシャリスト直伝! 全員をひきつける「話し方」の極意(明治図書出版)
若い教師のための1年生が絶対こっちを向く指導(学陽書房)
イラスト/イラストAC

