インタビュー/松尾英明さん|「働き方改革」は、居心地がよく協力し合える職員室づくりから【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは⑧】

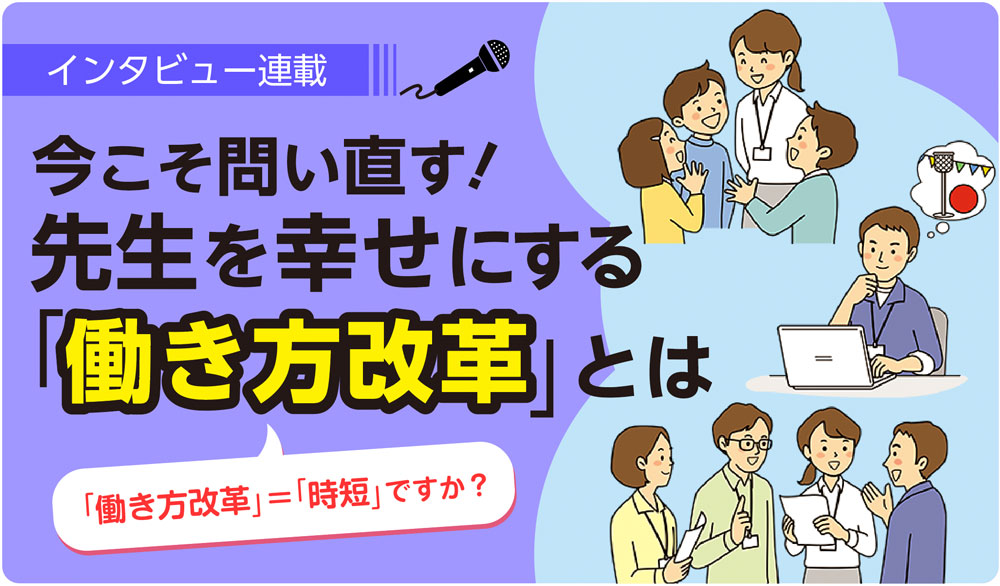
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載第8回は、千葉県袖ヶ浦市立蔵波小学校教諭の松尾英明先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
松尾英明(まつお・ひであき)
千葉県の袖ケ浦市立蔵波小学校教諭として、1年生の学級担任及び学年主任を務める。これまでに「クラス会議」を手法の中心とした「自治的学級づくり」について、千葉大附属小特活部で研究。またチーム担任制や教科担任制について千葉大学大学院教育学研究科でも研究。現場の経験や様々な場で学んだことを生かして、単行本や雑誌の執筆の他、全国で教員や保護者に向けたセミナーや研修会講師、講話等を行っている。近著に『不親切教師のススメ』(さくら社 2022)『学級経営がラクになる! 聞き上手なクラスのつくり方』(学陽書房 2023)がある。学級づくり修養会「HOPE」主宰。
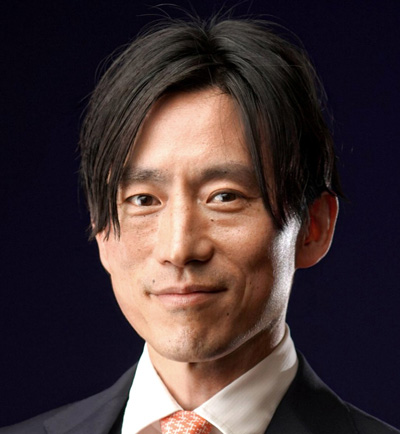
目次
「働き方改革」で、学校は働きやすくなったのか
教員としてこれまでに複数の学校で勤務してきましたが、最初の頃はどこもきつい職場環境でした。それが時代の変化とともにだんだん良くなってきたと感じます。
ある小学校は研究熱心で知られ、「不夜城」と呼ばれるほどで、「早く帰れないのが当たり前」の状態でした。それが今ではそれぞれの生活スタイル、個人の働き方に合わせて、「研究したい人はすればいい」という方針に変わっています。
世間の人が思うほど、今の学校は異常な状況ではなくなっていると思います。マスコミで取り上げられるようなひどい働き方を強いる学校も一部にはあるのかもしれませんが、少なくとも「どの学校もみんなひどい」と思うのは大間違いです。まだまだ改善の余地はあるものの、私が教員になった20年前よりも、働きやすくなった学校が確実に増えています。
おそらく現任校は比較的恵まれている部類に入るのだろうと思いますが、教員がどんな働き方をしているのかというと、本当にいろいろです。それぞれの生活リズムで働く時間を決めていますし、「早く帰れ」と強制されることもありません。「早く帰りたい」人もいれば、「職場のほうが落ち着くから」と遅くまで残る人もいます。子育て中の人は毎日必ず早く帰るのかというとそうでもなくて、「普段は早く帰るけれど、今日は残ってがっつりやる」というように自分のペースでメリハリをつけている人もいます。
若手教員については、学校全体に「若いうちはちょっと頑張ってみれば?」といった雰囲気があります。 陸上の大会に向けた指導、合唱部の補助、運動会の時期はグラウンドに線を引く……など若手教員にはやることがいろいろあります。今の学校は20代の若手教員が10人以上いるのですが、若手教員たちに話を聞くと、「すぐに帰るよりも、いろいろやりたいです」と言っている人もいて、必ずしも嫌々残っているわけではないようです。
私の働き方をご紹介しますと、私は学年の中で一番早く帰ります。子供の幸せのために何が最も大事かというと、それは担任が元気で上機嫌であることだと思うからです。反対に、もしも担任が嫌々仕事をしている、負担に思っている、必死に頑張っている状態になると、子供の前で上機嫌でいられず、不幸の還元という悪影響が出ると思うのです。
さらに、他の教職員に対しても「自分が頑張っているからお前も頑張れ」のような雰囲気が伝わってしまうでしょう。それが嫌なので、一番いいのは無理をしないことだと思っています。 だから、早く帰ります。
ただし、自分だけの残業デイをつくっています。飲み会のない金曜日の夜などを残業デイにして、教材研究や図工の準備など、やりたいことをやりたいだけやって帰ります。といっても遅くても20時ぐらいまでです。若い頃は毎日22時まで学校に残っていたものですが、今は20時を過ぎたら体力が尽きてしまいます。残業デイでも19時台に帰ることが多いです。
「時短」ばかり強調するのは無意味
今、全国の多くの学校で「働き方改革」を進めていると思いますが、「時短」ばかり強調するのは無意味だと感じます。時短はあくまでも手段だからです。
教員によって仕事量が違いますし、事情も違います。6年生の担任は、他の学年の担任よりも仕事が多くなります。同じ学年主任でも、厳しい学年かそうでないかで仕事量が違います。にもかかわらず、全員に「同じ時刻に帰れ」と言うのは横暴でしょう。それをさせたいのなら、学年主任や体育主任、研究主任の仕事などを、全教員に均等に割り振るべきだと思います。
「早く帰れ」と命じることは、教員をただの数字として扱っているように感じられますし、肝心なことが抜けています。それは「働き方改革」の目的です。そもそも「働き方改革」の目的は何かというと、誰もが幸せに働ける職場環境づくりです。これに尽きます。
子供のためを思えば、教員が早朝から夜まで働き続け、教材研究を寝ないでやったほうがいいのかもしれません。しかし、そんなことをしていたら教員が倒れます。教員が不幸になるような働き方は長続きしません。子供たちの持続可能な幸せを願うなら、まずは「教職員ファースト」です。それが最終的には「子供ファースト」につながります。この順番を間違えてはいけないと思います。

