【木村泰子の「学びは楽しい」#33】子どもの人権について考えたことはありますか?

子どもたちが自分らしく生き生きと成長できる教育のあり方について、木村泰子先生がアドバイスする連載の33回目。今回は、「子どもの権利条約」をもとに子どもの人権について考えていきます。(エッセイのご感想や木村先生へのご質問など、ページの最後にある質問募集フォームから編集部にお寄せください)【 毎月22日更新予定 】
執筆/大阪市立大空小学校初代校長・木村泰子

目次
「子どもの権利条約」について知っていますか?
今回は視点を変えて、「子どもの権利条約」について学びましょう。全国の学校に行かせていただいていますが、「子どもの権利条約」については知らない先生方が多いようです。先生方が知らないということは、子どもも知らないですよね。まずは、子ども自身が「子どもの権利条約」のことを知らなければならないのです。
令和6年、岐阜県の本巣市では、「子どもが主語の学校」をつくる一つの手段として、教育委員会が岐阜県ユニセフ協会に依頼し、すべての小中学校で「子どもの権利条約」についての授業をしてもらいました。この授業で子どもたちは、これまで知らなかった自分たちの権利がこのように保障されるのだという事実を知りましたが、実は大人たちも子どもたち同様に知らないことが多かったようです。
そこから新たなプロジェクトが立ち上がり、教育長のリーダーシップのもと、市教委と学校がワンチームになって、本気で「子どもが主語の学校づくり」への挑戦を始めることになりました。
子どもがつくる子どもの権利条例
「子どもが主語」とはいうものの、全国の学校現場はモヤモヤし続けているのが現状です。そんな中で、本巣市では、子どものことは子どもたちに決めさせようと、「子どもがつくる子どもの権利条例」へのチャレンジが始まりました。
子どもが主語の学校づくりを本気で問い続ける中で、まずは、本巣市のすべての子ども(学校に行っていない子どもも含めて)が「子どもの権利条例」についての自分なりの考えを書きました。約2500人の子どもの考えを、教育長はじめ、関わる委員会のメンバーが読みました。一人一人の子どもの思いはみんな違っていて、大人が思いつかないような権利や胸に迫る内容まで様々で、非常に心が動かされたと皆さん語っておられました。子どものことは子どもに教えてもらわないと分からないのです。
ミッションは「すべての友達が幸せになるために」です。そのための本巣の「子どもの権利条例」の制定に向けて、すべての子どもが「自分がつくる、とびっきりの子どもの権利条例」をつくっている最中です。子ども同士が、これから互いに対話を重ねて、各校から持ち寄った「子どもの権利条例」をもとに、児童会サミットや生徒会サミットで条例を決めていく予定です。大人が学べることが満載です。
この機会に、読者のみなさんに「子どもの権利条約」についてお伝えします。
「子どもの権利条約」とは
「子どもの権利条約」とは、1989年に国連総会において採択された、子どもの権利(人権)に関する包括的な条約で、現在196の国・地域が締約しています。日本は、1994年、158番目に批准しました。
「子どもの権利条約」は、子どもは権利をもつ主体であるという考え方に基づいており、条約の定める様々な権利は次の「4つの原則」を基本としています。
【第2条】どの子どもにもこの条約が定める権利を尊重し、その権利を確かに守る。
【第3条】子どもに関して何かするときは、子どもにとって一番いいことは何かをまっさきに考えなくてはならない。
【第6条】すべての子どもには生きる権利があり、締約国は子どもの生存と発達を全力をあげて確かに見守る。
【第12条】子どもは自分に関係があるあらゆることについて自分の思いや願いを自由に述べる権利があり、その思いや願いは子どもの年齢や成長に応じて十分に尊重される。
また、「子どもの権利条約」は以下の条文において、「暴力の防止」や「学ぶ権利」についても定めています。
【子どもに対する暴力の防止】
・暴力を受けない(19条)
・健康を害する伝統的な慣行(24条)
・学校のルールは子どもの権利条約に従うこと(28条)
・非人道的な扱いなどの被害者の子どもの回復と社会復帰(39条)
【学べる・休む・遊ぶ・文化的生活や芸術に親しむ権利】
・学べる権利(28条)
・学びが指向すべき内容(29条)
・休む・遊ぶ・文化的に生活し芸術に親しむ権利(31条)
また、先に挙げた「4つの原則」は、2023年4月に日本で施行となった「こども基本法」にも取り入れられました。
こども基本法
すべての子どもや若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる社会をつくっていくための法律。
【基本理念】
・差別の禁止
・生命、生存及び発達に対する権利
・子どもの意見表明権とその尊重
・子どもの最善の利益
これに基づき、2024年6月には「こどもまんなか実行計画2024」が策定されました。
「校門をくぐっても人権を失わない」
自校の子どもの周りの環境はどうでしょうか。「子どもの権利条約」が学校の基盤として守られているでしょうか。
この機会に職員室で雑談してみませんか。
〇子どもが主語の学校づくりを行う上で、まずは「子どもの権利条約」について知り、子どもの人権について学ぼう。
〇「子どもの権利条約」が学校の基盤として守られているか、職員室の話題にし、みんなで考えていこう。
【関連記事はコチラ】
【木村泰子の「学びは楽しい」#32】現状に悩んだら、学校のシステムを抜本的に見直しませんか
【木村泰子の「学びは楽しい」#31】見えないところを見ようとする大人に
【木村泰子の「学びは楽しい」#30】想定外を生き延びる力をつけるために
※木村泰子先生へのメッセージを募集しております。 エッセイへのご感想、教職に関して感じている悩み、木村先生に聞いてみたいこと、テーマとして取り上げてほしいこと等ありましたら、下記よりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。
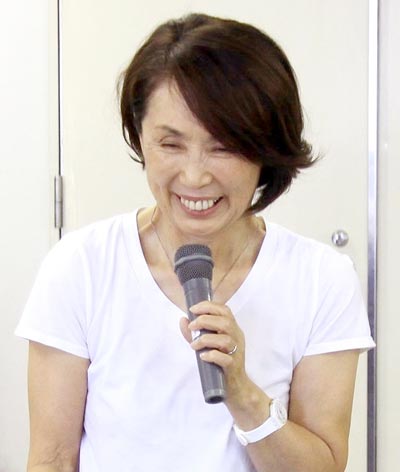
きむら・やすこ●映画「みんなの学校」の舞台となった、全ての子供の学習権を保障する学校、大阪市立大空小学校の初代校長。全職員・保護者・地域の人々が一丸となり、障害の有無にかかわらず「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに尽力する。著書に『「みんなの学校」が教えてくれたこと』『「みんなの学校」流・自ら学ぶ子の育て方』(ともに小学館)ほか。

