インタビュー/赤坂真二さん|コロナ禍×「働き方改革」により学校から奪われたのは「つながり」【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは⑦】

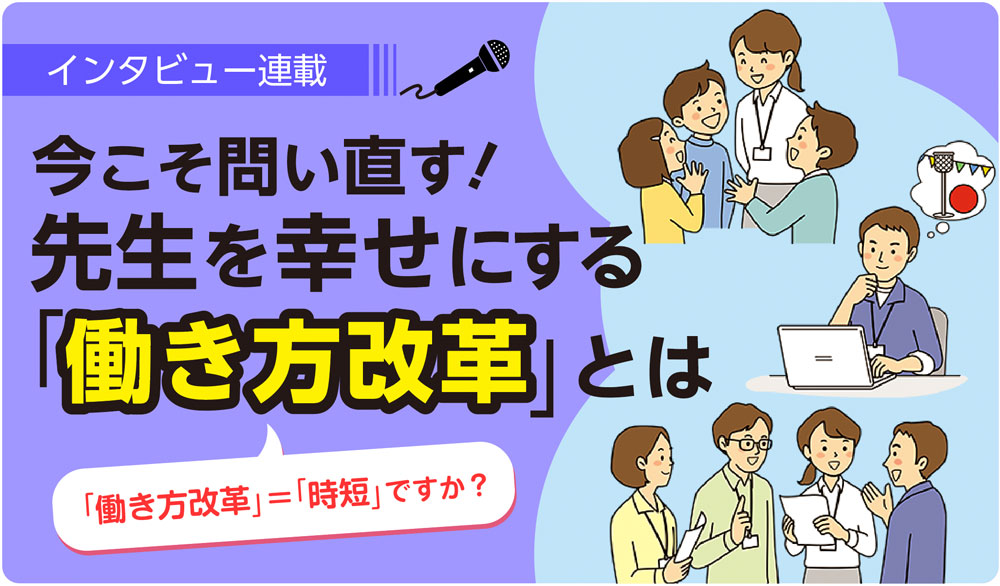
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載第7回は、上越教育大学教職大学院の赤坂真二教授にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
赤坂真二(あかさか・しんじ)
1965年、新潟県生まれ。19年間の小学校での学級担任を経て2008年4月より現所属。現職教員や大学院生の指導を行う一方で、学校や自治体の教育改善のアドバイザーとして活動中。2018年3月より日本学級経営学会共同代表理事。『最高の学級づくり パーフェクトガイド』(明治図書出版、2018)など著書多数。編著に『ウェルビーイングの教室』(明治図書出版、2024)がある。

目次
コロナ禍と「働き方改革」が学校から奪ったもの①…つながり
「働き方改革」の話を単独で考えることも大事ですが、コロナ禍の3年間に始められて今も継続されている取組がたくさんありますので、コロナ禍の要因も合わせて考える必要があると思います。なぜなら、コロナ禍の非常に差し迫った状況のせいで、「働き方改革」が歪められた形で展開してしまったのではないかと私は感じているからです。
まず、コロナ禍と「働き方改革」によって学校から奪われてしまったものを二つ挙げておきます。一つ目は「つながり」です。
コロナ禍の3年間でオンライン授業が普及しました。当初は大変現場が混乱したものの、先生方の優れた適応力によりオンライン授業がすぐに開始されました。当時は文部科学省を中心に、教育関係者の間では「学びを止めない」が合言葉のようになっていましたが、これに関しては実現できたと言えます。学習の遅れはほとんどありませんでした。それは2022年に実施されたOECDのPISA(Programme for International Student Assessment)調査の結果で、日本の子供たちの学力が高かったことからも明らかです。
その一方で、「学びを止めない」ことだけではなく、「つながりを断ち切らない」こと、「居場所としての学校」の重要性も指摘されていたのですが、こちらがどうなったかの検証、検討は十分になされていないようです。今の時点で言えるのは、コロナ禍が明けた学校では、子供同士のトラブルが頻発している現場もあるということです。
そんなある小学校の教頭先生に話を聞きました。コロナ禍後は高学年のケンカが絶えないそうです。コロナ禍の最中には子供同士の接触が少なかったのでトラブルは少なかったのですが、コロナ後には接触が増えてトラブルも増えました。例えば、子供たちが「あいつが先に『死ね』って言ったのに、なんで僕が言っちゃいけないの?」といった具合に、自分が傷つけられたら相手を傷つけていいのだと、当然のように主張するのだそうです。こうしたことが特別のことではなく、「よくあること」になっているというのです。
担任はケンカした子供たちを指導するのと同時に、保護者に連絡をします。そうすると、保護者は家で子供をきつく叱ります。家で叱られてストレスが溜まった子供たちは再び学校でトラブルを起こし、担任がまた指導し、保護者もまた叱る、という悪循環になっています。
この悪循環の背景には、 教員と保護者の関係の変化があります。子供が問題行動をしたときに電話で保護者に伝えること自体は、教員がコロナ前にもしてきたことです。しかし、今の保護者の受け取り方は以前とはだいぶ変わったのです。
コロナ前には、子供の良かったところを見つけたら、保護者に電話をして「お母さん、ちょっと聞いてください。今日、感動したんですよ。〇〇さんがこんなことをしました」といった姿が見られたものでした。私も教員時代には連絡帳にその日にあった子供の良いところを書きましたし、ときには電話をして直接お知らせしていました。すると保護者は、「先生から電話が来たからびっくりしちゃった」などと言いながらも、次の日の連絡帳に「子供の良かったところを食卓で話題にできて嬉しかったです」といったお返事をいただいたりすることがありました。
しかし、コロナ禍の3年間には、 保護者とこうしたコミュニケーションを取らなかった学校もあり、そのような現場では上記のような温かな関わりが希薄になりました。その結果、保護者は担任からいきなりわが子に関するネガティブな情報を聞かされ、学校に不信感を抱いたり、必要以上に子供を強く指導したりしてしまう人が増えたようです。
私が最近訪問したある学校では、赴任したばかりの校長先生が悩んでおられました。あまりにも保護者からのクレームが多いからです。「教員は一緒に子供を見守り、育てる協力者」だと保護者は思っていないのです。そのため、子供同士のトラブルを保護者に伝えるときにコミュニケーションがうまくいかず、教員は反発をくらってしまいます。この学校の先生方は放課後になると保護者対応でとても忙しくしているそうです。
ここまで読んで、どこが「働き方改革」と関係してくるのか、と疑問を感じた方もいるかもしれません。
コロナ前には、「人と人との付き合いは煩わしいけど、大事にしないといけないよね」という風潮が社会全体にあったと思うのです。しかし、コロナ禍には「人と接触してはならない」という、制限のある世の中になったことにより、「無理して人間関係なんてつくらなくていい」という考え方にお墨付きを与えた形になりました。それにより、学校では以前から教員が「面倒くさいな」「煩わしいな」と思ったことを削除・削減するという方向に、「働き方改革」を進行させてしまったのではないでしょうか。保護者と積極的にコミュニケーションを取ることよりも、「早く帰ること」を優先させたのです。
今学校で起きているのは、子供同士のトラブルの増加、教員と保護者の相互不信だけではありません。もう一つ、大事なつながりが失われたと見ています。それは教員同士の関係性の希薄化です。学校では「働き方改革」により、教員は仕事を早く終わらせて帰らなくてはなりませんから、教員同士が勤務時間中に雑談をする暇はありません。飲み会等もほとんどなくなり、教員間のコミュニケーションが決定的に不足しています。
これは放置できない問題です。職員室に協力し合う雰囲気がない学校では、教員は皆一人で戦わなくてはなりません。荒れた学級があっても手を差し伸べる余裕がなく、その状況を改善することができません。職員室の雰囲気を改善しなければ、子供のトラブルは続き、前述したような悪循環が続くのです。
コロナ禍と「働き方改革」が学校から奪ったもの②…学校の充実感
コロナ禍と「働き方改革」が学校から奪ったものの二つ目は、充実感です。
コロナ禍の3年間は、日本の公教育の長い歴史の中で、初めて学校がカリキュラムマネジメントを積極的に行ったといえます。問題は、その際に何を削ったのかです。多くの学校が行ったのは、学校に潤いや充実感をもたらしてきた特別活動を大幅に削り、教科指導の時数を確保することでした。
2020年のコロナの第一波の頃、中学校の先生たちからたくさんのメールや電話をいただきました。部活が縮小され、大会は中止となり、合唱祭や体育祭などの行事も中止になって、生徒たちは学校生活に張り合いがなくなり、お祭り騒ぎで盛り上がる機会もなくなり、学校がつまらないものになってしまった、というのです。
学校から楽しい部分を削り取る際に、一役買っているのが「働き方改革」です。どの学校でも当然のように行事を縮減し、「〇〇を減らした、〇〇をなくした」ことは話題になりましたが、その結果、学校生活にどんな影響を与えたのか、子供の発達にどんな影響を与えたのかは全く検討されていないのではないでしょうか。
運動会を午前中で終わらせるために競技種目を減らし、その分、練習時間が少なくなって、「負担が軽くなった」と答える先生もいないわけではありません。しかし、 学校行事は子供たちの非認知能力を育み、協働性などを感じ取らせるためのとても大事な時間だと認識している先生の中には、危機感をもっている方もいます。「教員の負担を軽減する」という理由で、安易に行事を削減することには疑問を感じます。
例えば、多くの学校で運動会が縮小されましたが、練習時間が減ることにより、子供たちの運動会に対する意欲は確実に低下し、淡々となんとなく行事をこなすようになったそうです。教員たちも一生懸命準備をしてきたわけではないため、たいした思い入れもなく、なんとなく半日で終わる、といった形になり、運動会そのものがもはや教育の場でなくなり、ただの「こなし業務」になっている学校もあります。

